東日本大震災をきっ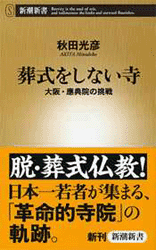 かけに、ボランティアへの関心が高まっています。宗教者はどんな貢献ができるでしょう?
かけに、ボランティアへの関心が高まっています。宗教者はどんな貢献ができるでしょう?
被災地でボランティア活動に取り組むある僧侶によると、避難所を訪ねて「心の相談を引き受けたい」と申し出たところ、「今、お坊さんの姿を見ると死者を 想い出すから、遠慮してほしい」「こんな時に布教活動をするなんて不謹慎だ」と断られたそうです。日本では、お坊さんと言えば葬式を連想します。では、生 きている人のために、仏教は何ができるのか?こんな疑問から、1997年に大阪の應典院というお寺を再建して、NPOとして運営し、すべての人に開かれ た場にしようと挑戦してきたのが、秋田光彦さんです。
秋田さんが應典院を「開かれた寺」にしようとしたきっかけは、いくつかあります。一つは1990年代前半のオウム真理教の台頭です。若 者たちはなぜオウム真理教のようなカルトに走るのか、とつぶやく秋田さんに、ある檀家さんは「あんたがたお坊さんがボヤボヤしてるからだ」と言われて、 ハッとします。仏教が葬式とお墓を経営の柱としてのんびりしている間に、カルト教団は悩める若者たちのニーズに応えて、彼らを取り込んだのです。
もう一つのきっかけは、阪神大震災です。秋田さんも避難所で「心の相談」を引き受けたのですが、誰も利用しようとしなかったそうです。本来は心の問題の専門家であるはずのお坊さんが、葬式の時にだけお世話になる人と見られていたのです。
それとは反対に、社会に積極的に関わる仏教者との出会いもありました。タイやベトナムなどで活動する「エンゲイジド・ブッディズム(社会参加仏教)」の 開発僧との出会いでした。こうして秋田さんは、お寺の本来の存在意義とは、「社会に生きているすべての人に、交流と学びの場を提供すること」だと考え、應 典院をその場としていくのです。
このことに気づいたのは、秋田さんだけではありませんでした。全国で貧困や自殺の問題に関わるお坊さんたちの姿を描いたのが、『ルポ 仏教、貧困・自殺に挑む』です。
この本では、さまざまな現場で活動する僧侶たちの姿が描かれています。東京の浅草や新宿で炊き出しをする僧。宮城県で駆け込み寺を運営する僧。滋賀県で フードバンク(食糧配給)を始めた僧。大阪で野宿の人のためにシャワールームを始めた僧。釜ヶ崎でケースワークをする僧。東京・墨田区で野宿の人のために 寮を運営する尼僧。全国各地で、自殺を考える人たちのために相談室を作ったり、電話やインターネットを通して相談にのる僧たち。社会の中で苦しんでいる人 たちに寄り添い、その叫びに耳を傾ける僧侶たちの姿が、そこにはあります。
日本には、コンビニエンスストアが約4万、お寺は7万8千、神社が8万あると言われています。 もともと、お寺や神社は庶民にとって身近な存在でした。 そうした神社やお寺が「非営利機関」(NPO)の原点だ-と指摘したのは、米国の経営学者、P.F.ドラッカー(Drucker)です。秋田さんは、お寺 の公益機能として、「学び」「癒し」「楽しみ」を挙げます。「学び」とは「寺子屋」、プライベート・スクールとしての役割です。「癒し」とは「病院・薬 局・社会福祉施設」としての役割。「楽しみ」とは「芸能興業」、つまりお寺の新築の資金を集めるための興業です。このように、お寺は民間の「公共機関」と しての役割を担ってきたのです。
もともと、お寺や神社は庶民にとって身近な存在でした。 そうした神社やお寺が「非営利機関」(NPO)の原点だ-と指摘したのは、米国の経営学者、P.F.ドラッカー(Drucker)です。秋田さんは、お寺 の公益機能として、「学び」「癒し」「楽しみ」を挙げます。「学び」とは「寺子屋」、プライベート・スクールとしての役割です。「癒し」とは「病院・薬 局・社会福祉施設」としての役割。「楽しみ」とは「芸能興業」、つまりお寺の新築の資金を集めるための興業です。このように、お寺は民間の「公共機関」と しての役割を担ってきたのです。
「お寺」を「教会」と置き換えてもかまいません。カトリック教会もまたコミュニティ・センターとしての役割を担ってきました。神戸の教会は、阪神大震災 を通して、地域に開かれることの重要性を再確認しました。コミュニティの崩壊が叫ばれる今こそ、教会は開かれた場となるよう求められています。