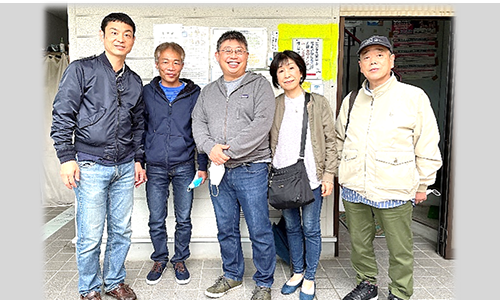尹〈ユン〉大統領時代の韓国 : 挑戦と教会への示唆
デニス キム ウソン SJ
イエズス会司祭、韓国・西江〈ソガン〉大学社会学部教授
新たに就任した韓国の尹錫悦〈ユン・ソンニョル〉大統領は、文在寅〈ムン・ジェイン〉前大統領時代にこじれてしまった日本との関係改善を図りたいと、すでに方針を示しています。このことは、韓国の大統領交代が、内政だけでなく外交にもどれほど影響を及ぼすかを表しています。大統領の交代に応じて、韓国の人々は社会・政治・経済的に重大な変化を定期的に経験してきました。尹大統領時代の韓国を、教会についての簡単な考察とともに展望することは、意義深いことだと考えます。

置かれている状況と任務
大統領は、自らの統治哲学に沿って政策設計をしたいと考えますが、政策の優先順位と履行は、常に時代から求められる歴史的な要請により条件付けられます。大統領の任務には、相互に関連する、内政と外交という2つの側面があります。
コロナ禍後の経済成長と「公平性」
内政面において、尹大統領は、韓国社会がイデオロギー的に二極化したために誕生した大統領と言えます。文在寅前大統領に対抗する感情の象徴として、検察総長を辞任した直後に、保守党により大統領候補に選出されました。つまり、尹大統領は新任というだけでなく、外交面においても、内政面においても、問題に対処した経験が不足しています。
また、文在寅大統領は、朴槿恵〈パク・クネ〉大統領を追放した「ろうそくデモ」の結果として政権を握り、大統領職を通じて比較的大きな支持を得ました。しかしながら尹大統領は、僅差で選挙に勝ったに過ぎません。このような背景から、尹大統領の政治力と韓国を取り巻く情勢の進展によっては、政治的に脆弱な立場に置かれるであろうと見込まれています。
事前の備えがどうであれ、尹大統領の内政における主な任務は、コロナ禍によって不況に見舞われた経済を、どのように後押しするかでしょう。特に、自営業者支援の必要性と不動産市場の安定という、2つの分野に対応しなければなりません。自営業者は、コロナ禍の間、人々が距離を取った「新しい生活様式」により、大きな打撃を受けました。不動産市場の問題は、支持者の深刻な文在寅離れを引き起こし、最終的には革新系の政党から保守政党へと権力が移行されました。また、尹氏は、若年層の失業率の高まりとともに焦点となっている、経済の二極化の緩和と「公平性」に取り組まなければならないでしょう。
地政学的ビジョン
誰が韓国大統領になろうとも、国際的な要因は極めて重要です。韓国の大統領は、幾重にも折り重なる歴史と、複雑な関係を持っている朝鮮半島の地政学に直面しなければならず、とりわけ、北朝鮮とその核兵器計画に対処しなければなりません。同時に大統領は、従来ライバル関係にある日中の地政学のみならず、厳しさを増す米中の覇権争いの中に韓国を置かなければなりません。北朝鮮の核問題は、南北間でのやり取りだけによって対応することはできず、韓国を取り巻く、米国、中国、日本、ロシア等すべての近隣諸国による取り組みが求められます。
さらに、韓国の大統領は、外需に依存する中規模のアジア太平洋諸国のリーダーであることの難しさに対処しなければなりませんし、貿易、安全保障、外交の優先順位のバランスをとる必要もあります。このバランスを失えば、韓国を危険にさらすことになるでしょう。

特に、米中間の激化する対立と、ウクライナにおける戦争の影響により、韓国は安全保障の観点から、相互に関連する2つの基本的な目標を掲げるべきでしょう。まず、第二次朝鮮戦争の抑止。次に、米中あるいは日中により、部外者の覇権争いを緩和するための「はけ口」として利用(乱用)されないよう朝鮮半島を守ることです。
前者の目標は明確ですが、後者には説明が必要でしょう。日本と中国は16世紀以来、歴史上3度交戦しました。〔訳注:日本では文禄・慶長の役と称される〕壬辰戦争(1592-1598)と2つの戦争(日清戦争:1894-95、日中戦争:1927-45)です。2つの戦争の主な戦場は、朝鮮半島でした。3つの戦争はすべて、「トゥキディデスの罠」の良い例です。
つまり、新興勢力が支配勢力を脅かし取って代わる時に生じる、危険な戦争のダイナミズムです。再び統一され維新を経た日本が、この地域での覇権を野心的に求めた時に韓国を侵略しました。しかし、韓国の政治指導者が責任を免れる訳ではありません。2つの戦争における韓国の指導部は、戦略的な展望と技量を欠いている点において、腐敗ではないにしても、無能であったと非難されるに値するでしょう。
したがって、尹氏を含む韓国の大統領にとって、最も重要な任務は、すでに重武装してしまっている地域である朝鮮半島での戦争を防ぐことです。むしろ、尹氏を含むこの地域の政治指導者は、平和のために先を見越して取り組むべきでしょう。
政治姿勢:法の下の正義
尹大統領の政治的な能力により、自国内および外交分野における政治的ビジョンと統治思想が具体化されます。政界の新入生として、尹氏は保守党の党勢拡大を、親米・親日路線に見出さなければなりません。李明博〈イ・ミョンバク〉元大統領、朴槿恵元大統領のような、保守的な政治路線をとることは当然予想されます。
外交においては、北朝鮮に対してより厳しく接し、日米とより緊密な関係を築き、韓国の最大の経済的パートナーである中国に対し、嫌々ながらも親しげな立場をとることが期待されています。国内では、より成長志向の政策を持ち、社会正義よりも法に照らした正義に焦点を当てるでしょう。社会正義には、平等、疎外、差別の分野が含まれますが、法の下の正義は、法的に正しいか間違っているかに焦点を当てます。
しかし、注意を引くのは、尹大統領の法的な感覚が、バランスを欠いている可能性があるということです。韓国の司法試験に合格するためだけに、20代のすべてを含め、ほぼ一生を法律の世界で過ごしてきました。これは、尹氏が法のレンズを通して世界を解釈していることを示しています。複雑で脆弱な状況に身をさらし、法的な推論を超えた柔軟な思考や知恵を育む機会を欠いていた可能性もあります。すでに多くの検察出身者が、大統領秘書官として働いています。法的推論は検察総長にとっては良いことですが、大統領にとっては十分ではありません。したがって、尹大統領の治世が、対話・説得・社会的な妥協よりも法的推論に支配され、社会的に懸念されている環境・労働・女性問題より、経済成長を優先させるのではないかと懸念されています。
韓国と東アジアにおける教会の使命:平和を執り成す者
韓国と東アジアにおける教会の使命は、大統領の交代によって重大な影響を受けることはありません。私たちは、常に福音宣教と共通善のために働きます。しかしながら拙文において、尹大統領による韓国の地政学的な挑戦、すなわち戦争を避け平和を促進することを強調しました。韓国と海外の両方の政治的な指導力により、この基本的な課題に対応することが主に求められています。
同時に、平和を促進するという対応は、教会の使命でもあります。2022年の教会は、世界および地域の現実に真剣に向き合う必要があります。まず、近隣諸国の覇権主義的競争の激化、軍拡競争、地域における植民地化と戦争の歴史。次に、ウクライナでの現在の戦争と国際政治の再構築。そして最後に、新たなナショナリズムとポピュリズムの世界的な増進。現代世界の現実に立ち向かうことにより、教会は和解と平和のための貴重な使命を再発見し、教区と国家の境界を越えて出会いや対話を推し進め、架け橋となることができます。この使命は、主の教え「平和を実現する人々は幸いである」(マタイ5:9)にかなうものであり、地元の小教区や学校から始められるべきでしょう。
〔原文:英語〕
ウクライナ侵攻と平和
小山 英之 SJ
イエズス会司祭、上智大学神学部教授
21世紀になぜこのような戦場が生まれてしまったのか? しかし、プーチン批判一辺倒には危惧を覚える。
「平和は神が望まれる秩序を追究することによって、日々構築されていくもの」(『教会の社会教説綱要』495)とあるが、プーチン大統領の反抗は、その前に神が望まれない秩序があって、それに対する反応ということができる。プーチンの暴挙といえる侵攻も、まずはその背後にある怒りを理解することから始めない限り、停戦合意、新しい世界秩序の構築はありえない。
2008年のNATO首脳会議(ブカレスト)において、アメリカがウクライナとグルジア(ジョージア)のNATO加盟を支持した時、「止まらないNATO拡大、新たな加盟国への軍の配備、アメリカの戦略的なミサイル防衛システムの配備はすべて私たちの協力関係を損なうものだ。国境に配備された強力なミサイルをロシアは国防上の脅威とみなす」とプーチン大統領が強く反発感を露わにした。その時に少しでも安心感を与えることができたならば、今回のロシアのウクライナ侵攻を防ぐことができたのではないだろうか。西側の外交的失敗である。プーチン大統領は、「もう我慢の限界だった」としてウクライナ侵攻を開始してしまった。
(1) あらゆる紛争で必須な態度は、暴力――テロ組織によるものであれ、国家によるものであれ――をただ非難するのではなく、理解しようとすることである。国連事務総長のグテレス氏がプーチン大統領との会談の冒頭でいきなり、「他国の領土の一体性を侵害する行為は、国連憲章に全く合致しない」と切り出しては、相手が態度を軟化することは期待できない。
筆者は刑務所で教誨師をしているが、初対面の受刑者に、「お前はそんな罪を犯すべきではなかった」と言って始めることは考えられない。また、北アイルランド紛争と長年かかわってきたが、プロテスタントの武装組織のメンバーで刑務所に長く服役した後、和平プロセスに身を投じることになった一人が、自分に対する教会の唯一のメッセージは、「そんなことをすべきではなかった」であったと述べていたのを思い出す。

北アイルランド紛争の和平プロセスにおいて決定的な役割を果した、レデンプトール会のアレク・リード(Alec Reid)神父は、「暴力をただ非難することは助けにならない」と述べている。教皇フランシスコは、回勅『兄弟の皆さん』(283)で「このようなテロリズムは、その形態や標榜するものにかかわらず、徹底して非難すべき」と述べているが、それだけでは十分ではない。アレク・リード神父は述べる。「仕えるキリスト者は紛争の真っただ中に立って、個人的な経験の知識でもって理解するようになるまで生身の現実にある紛争と出会わなければならない。これが紛争を生じさせている善悪の道徳的次元をつきとめる唯一の知識である」。
ここで彼は、イエスのアプローチを説明するために、受肉という神学的概念を思い起こさせる。「イエスは、人間の命のかかわる紛争の状況で神の仲介者としての彼の役割をいかに果たすであろうか? 生身の人間になるまでその紛争の真っただ中に生きることによってである……彼は善悪のすべての次元――個人のレヴェルから政治的宗教的な力を行使する人々の次元にいたるまでの――にとらわれるのに任せた。しかし、常に神の正義と慈しみの仲介者としてであった」。
メイズ刑務所のカトリックの武装組織アイルランド共和軍(IRA)の服役囚への奉仕の結果、彼は、IRAのあらゆるレヴェルの活動家、リーダーたちと独自の形で知り合うことになった。IRAと深くかかわることを通して、暴力に代わる手段を可能にし、暴力を捨てさせることに成功した例である。
(2) もう一つ大事なのは、対立する相手もいかほどかの真実と正義の正当なヴィジョンによって動かされていると信じることである。
ウクライナの人々は、ヨーロッパの人々の方が明らかにいい暮らしをしているのを見て、民主主義への動きを強めてきた。一方、プーチン大統領は、NATOの東方拡大、アメリカの戦略的防衛ミサイルシステムの配備に対する強い反発もあって、2021年、「ロシア人とウクライナ人の歴史的一体性について」という論文を発表する。「ロシア人もウクライナ人も言語や信仰を同じくし、密接なつながりが先祖から受け継がれてきた。血のつながりの中に両国はある」という神話か幻想にどんどんとらわれていった。
ヨーロッパに接近し、2004年のオレンジ革命、2014年のマイダン革命を経て、民主化を進めようとするウクライナ。ロシアとウクライナの一体性を主張するプーチン。どちらかが善で他方が悪とは言い切れない。二元論を超える必要がある。
そもそもNATO拡大は何のためであったのか。ヨーロッパでは冷戦が終結し、ロシアはもはや大きな脅威ではなくなっていたのに、いたずらに敵視し、相手に恐れを抱かせたのはなぜか。それは、アメリカは常に敵を必要としてきたからではないか。かつては、日本がアメリカの敵であった。その後もロシア、中国とたえず敵を作り出すのがアメリカの政策であった。それによって軍需産業は、限りなく潤ってきた。
今日も大勢のウクライナ人が殺傷され、混迷を極める中、アメリカ、NATOはウクライナに武器を供与し、ますます軍需産業が喜ぶ状況となってきている。極限まで肥大化した軍産複合体によって成り立っている経済秩序、世界秩序をこの機会にあらためて見直さなければならない。プーチンが怒った対象は、NATOのみならずロシアもそのうちにある、気候変動をも引き起こしている「開発・安全保障パラダイム」であり、「平和パラダイム」への転換が求められる。
(3) いかにしてこの戦争が終結するか。両者とも何かを諦めながらも何かをつかむ、勝つ・負けるを超えてwin‐winの状況を創り出すことが必要であるが、ウクライナの人々の大勢はますますロシアを敵とみなすようになってきており、ロシアとの合意はますます困難になってきている。ゼレンスキー政権の存続、クリミア半島割譲、東部地区のドネツク州・ルガンスク州独立、そしてウクライナがEU加盟への方向性は明らかにしながらも、NATO加盟は断念すると宣言することによってか。あるいは、戦争が長期化し、プーチン大統領が失脚し、ロシアの独裁政権が崩壊することによってか。
G7が一つになってロシアを非難し、欧米+日本対ロシアの単純な構図になっていることを危惧する。日本には他に取るべき道がないのであろうか。
5月15日には、沖縄本土復帰50周年を迎えたが、自民党政権は、沖縄の米軍基地は戦争抑止のために不可欠、さらに抑止力を高めるために反撃能力の所有を主張し、それを支持する世論が強くなってきている。防衛費を増額して自衛隊を強化し、米軍との一体化をさらに深化・拡大しようとしている。こうして防衛費を増加することは、軍需産業を喜ばせることはあっても中国との不信感を高めるだけである。抑止力としても不十分であり、決して東アジアの平和構築に寄与するものではない。
アメリカの「核の傘」の名の下でアメリカの核兵器使用に協力さえするという政策から離れ、戦後日本が大切にしてきた平和主義を生かして、軍備そのものへの依存を減らすような安全保障を切り開いてゆくべきである。アメリカ、ロシアとも中国とも距離を保ち、等距離の友好関係を維持してゆくべきである。そして核兵器禁止条約を締結すべく、その第一歩としてドイツのように核兵器禁止条約交渉会議にオブザーバーとして参加すべきである。たとえ軍事バランスがとれていたとしても、テロリストによって、あるいはどこかの国家元首によって一度核兵器が使用されたならば、どれほどの人的被害、恐ろしい環境破壊が引き起こされるかを考えなければならない。

「軍備の均衡が平和の条件であるという理解を、真の平和は相互の信頼の上にしか構築できないという原則に置き換える必要があります」(教皇ヨハネ23世回勅『パーチェム・イン・テリス――地上の平和』61)、「軍備拡張競争は、貴重な資源の無駄遣いです。本来それは、人々の全人的発展と自然環境の保全に使われるべきものです」(教皇フランシスコ、長崎、2019年11月24日)の言葉の重みを、これまで以上にかみしめたい。
参考文献
- 小山英之、「平和をもたらす人は幸いである」、越前喜六編著、『真福 ここに幸あり』、教友社、2021年
- 小山英之、横山正樹、平井朗編、『平和学のいま 地球・自分・未来をつなぐ見取図』、法律文化社、2022年
施政権返還50年の沖縄から
高橋 年男
公益社団法人沖縄県精神保健福祉会連合会 理事
はじめに 構造的沖縄差別
昨年暮れから今年初めの沖縄の地元紙では、「沖縄のコロナ感染、米軍基地から拡大」「水際対策に穴、対策は米軍任せ 地位協定が壁」などの見出しが、連日、大文字で1面トップを飾った。
感染力の強いオミクロン株に備えるため、沖縄県は米軍に感染者のウイルス・ゲノム解析を求めたが、米軍は部隊移動の履歴が公になることをいやがって、「兵士の個人情報を守る」という理由で、日本側の検疫を拒否した。基地内での防疫・隔離の状況や、外出禁止などの感染防止策についても情報開示がされることはない。一昨年7月にも、米軍関係者の独立記念日でのどんちゃん騒ぎから、基地内で300名のメガクラスターが発生し、県民の間に感染が一気に拡大したことは記憶に新しい。
今回は、米国から出国前の感染検査チェックもなく、直接、嘉手納基地に到着した数百名の部隊が感染源だ。その彼らがマスクをつけないまま、家族連れで買い物に出る、タクシーに相乗りして歓楽街に夜遊びに繰り出す、住民の憩いの場である公園や住宅街をジョギングする等、私たち県民生活の至る所が、米兵と「三密」状態である。
世界最大の感染大国である米国。しかも軍隊は集団での移動や訓練が多く、狭い兵舎で長時間の生活を共にするため、彼らの感染率は国民一般よりも格段に高い。沖縄では今年1月の1か月間の米軍の感染者は約6000名で、人口当たりの感染率は世界一だとマスコミが集計している。日本政府が、「コロナ鎖国」と言われるほどの水際対策を取っていても、出入国管理をすり抜ける米軍基地が抜け穴となって、それもバケツの底が抜けたようなアウト・オブ・コントロール事態になっている。
今年、沖縄は施政権返還50周年を迎えたが、「辺野古が唯一」などと、沖縄に一方的に犠牲を押し付ける構造的差別が、一連のコロナ・リスクによって暴き出された格好だ。日本全体の米軍基地の7割以上が集中する沖縄の被害は、コロナ感染ばかりではない。米兵による凶悪犯罪。戦闘機による爆音や部品落下。有毒な化学物質PFAS流出で飲み水や川・海・土壌の汚染が人体に蓄積し、命と健康を脅かす。さらに辺野古の埋め立てに莫大な国家予算を投入し、「敵基地攻撃」のための長距離極超音速ミサイル配備など、琉球弧全ての島々を要塞化し、再び沖縄を戦場に突き落とすような話は、数え上げればきりがない。
2月24日からのロシア軍によるウクライナ侵攻に乗じて、自民党から安倍元首相や高市早苗政調会長などの「核共有論」が飛び出した。米軍政下の沖縄には、1300発もの核兵器が配備されいつでも発射できる態勢だった。「基地も核もない本土並み」になったはずの施政権返還後の沖縄だが、核の運用施設は辺野古と嘉手納の米軍弾薬庫に置かれている。密約が暴かれた今は、いつでも核兵器を持ち込み使用できるように訓練が実施されている。全国を見わたしても、核兵器の施設は沖縄以外にはない。核が持ち込まれるところは沖縄である。構造的差別によって、沖縄は再び戦場にされ全滅する危機に直面している。
構造的差別のボトムに、精神病者の私宅監置
1952年4月28日、サンフランシスコ講和条約の発効と同時に、日本では1945年敗戦後に敷かれた米軍占領状態を脱した。その一方で、沖縄は昭和天皇のGHQマッカーサー司令官へのメッセージ(1947年9月)などにより、憲法番外地の米軍政下に投げ入れられた。
そのために、戦後間もなく1950年に制定された日本の精神衛生法は、沖縄には適用されず、戦前からの精神病者監護法による私宅監置が続いた。精神医療環境が追いつかず、「社会の治安を守るため」の私宅監置という社会的隔離が容認されていった。
沖縄戦の地獄で心の均衡を失い、戦後は医療保険制度もない困窮の中で、治療から見放された病者は、地域で生活する場を失い、故郷を追われた。島のあちこちで、彼らに対する傷害事件や強姦被害などが相次いだ。琉球警察は、「優生保護、社会風紀、都市の浄化」のためとして、収容保護施設を琉球政府に訴え、那覇市では公営の監置所が造られた。

この当時の私宅監置の跡が、沖縄北部「ヤンバル」というところに今も残っている。家族の一人は、「監置所に入れられている人たちは人間扱いどころの話ではない。ブタやイヌでもまさかあんな取扱いは受けて いない」と回想を記録に残している。
このような窮状に追い詰められた精神病者の家族が発起人となり、精神医療充実のための全県的な精神衛生実態調査や立法促進の結果、日本の精神衛生法から10年遅れて、1960年に「琉球精神衛生法」が制定された。しかし、精神医療資源の絶対的不足から、「病院以外の場所で保護拘束」の条項が残り、1972年施政権返還まで、私宅監置は公認・放置されていた。沖縄返還により国内法が適用されるようになった後も、水面下では私宅監置から脱することができない事例がたくさん残っていた。
映画『夜明け前のうた~消された沖縄の障害者』

私宅監置の歴史を世に問うドキュメンタリー映画『夜明け前のうた~消された沖縄の障害者』(2021年度文化庁映画賞の優秀賞受賞作品)が、昨年2021年から全国で劇場上映中である。沖縄に残る「監置小屋」は、戦場の地獄からその後の米軍統治という戦後沖縄の精神医療の歴史を物語る。この小屋は、沖縄が生贄として米軍占領の<犠牲>にされた「4・28」の1952年に建てられた。小屋は「牢屋」と呼ばれ、監置することを「牢込(ろうぐみ)」と言った。監置された本人はもとより、家族もまた、世間からタブー視され、深い傷を負った。
この作品は、原義和監督が、沖縄の「日本復帰」前に撮影された写真を手がかりに、牢込の過去と現在を問い返す。カメラがとらえた真実は、沖縄県史や市町村史からも消されており、人権云々以前に存在しないものとされて、闇に隠されてきた真実である。
現存する牢屋の遺構は、沖縄の置かれてきた歴史を照射するとともに、私たち一人一人の心に潜む見えない檻をも可視化するものだ。
人間の尊厳を問い返す
私宅監置は、決して過去の話ではない。呉秀三(医学博士)が、「この病を受けたるの不幸の他に、この国に生まれたるの不幸を重ぬるものというべし」と、百年も前に告発した悪弊だが、今もなお形を変えた、家族に重荷を背負わせる強制入院制度や、精神病院での長期の社会的入院や身体拘束などの人権侵害が続いている。
昨年、沖縄においても精神科病院でクラスターが相次ぎ、感染症治療のための転院ができないまま、たくさんの犠牲者を出してしまった。精神科病院の閉鎖的な構造と密室性、精神科特例という制度的差別によるマンパワー不足などが相乗的に作用して大型クラスターを引き起こしたことは、偶然のアクシデントではなく起こるべくして起きた事態であった。
沖縄という歴史的構造的差別のもとにおいて、コロナ禍によってあぶりだされたものは、精神障害者の尊厳を奪う社会的トリアージというさらに一層根深い差別であり、精神科病院の存在そのものを問う課題が浮かび上がったのだ。形を変えた私宅監置、現在の精神科病院のあり方そのものの人権蹂躙をただすのが人の道ではないか。
誰一人取り残さない、ボトムから人間の尊厳を問い返す「沖縄返還50周年」にしたい。
この世界でもサニーに
山中 大樹 SJ
イエズス会司祭
サニーですか、レイニーですか?
同じ1つの出来事に対しても、人によって反応の仕方が違うことを、日々の生活の中で経験していると思います。そのようなときに、ポジティブな傾向が強い人はネガティブな傾向の強い人の反応を見て「やれやれ」と思ったり、ネガティブな傾向が強い人はポジティブな傾向の強い人の反応を見て「やれやれ」と思ったりするのではないでしょうか。

オックスフォードの心理学者・脳神経科学者エレーヌ・フォックスは著書『脳科学は人格を変えられるか?』で、すべての人はサニーブレイン(楽観脳)とレイニーブレイン(悲観脳)を持っていても、外からの刺激に対してそれらがどのように働くかは人によって異なり、ポジティブな人かネガティブな人かの違いが生まれると言っています。そして、ある人の中でサニーブレインとレイニーブレインの働きの傾向を決めるのには遺伝子、経験、解釈の仕方の3つの要素があって、もし自分の傾向を変えたい人がいれば、遺伝子や経験は変えられないので、解釈の仕方に働きかければいいのだそうです。つまり、悲観的に生きるのをやめたければ、ポジティブな見方・解釈を身につければいいのだと言っています。
なぜこのような話題から始めたのかといえば、私たちが生きる現代世界、例えば地球環境の劇的変化や悲壮な紛争を眼前にし、そこに渦巻く人々の思い、特に人の苦悩や死を前にしても自分の利益を引き出そうとする人々の意図を目の当たりにするときに、100%に近く悲観的にならざるをえない人が少なからずおられるのではないかと感じるからです。サニーブレインとレイニーブレインといった脳科学でポジティブになるスキルを身につけることは役に立つとしても、人類がこの地球に存在する積極的価値があるのか、この世界で生きる希望をどこに求められるのかなどといった問いが私たちに突きつけられているように感じるとき、それだけで十分とはいえないでしょう。
このような根源的な問いに対して目を隠したり、耳を塞いだりしないと覚悟するときには、この世界を創造し完成へと導く神への信頼と、自身苦難を身に受け、苦悩する人々と共にいまも歩まれるイエス・キリストへの信頼こそ、この現代世界の中で100%ポジティブに生きる道を劈(ひら)きうると思われます。
サニーな弟子たち
神とイエス・キリストに信頼しつつ、困難な状況に生きた人々の例を、新約聖書の「使徒行伝」に見出したいと思います。この書はルカ福音書の著者が福音書の続編として、イエスの弟子たちがどのような状況でどのようにイエスの活動を続けていったのかを描きます。実際、ルカ福音書の最後と使徒行伝の最初の箇所にはイエスの昇天が描かれ、これら2つの書が継続することを示しますが、この昇天の場面には興味深いことが見出されます。
マタイ福音書、マルコ福音書、ルカ福音書はイエス・キリストについての語りの近さから「共観福音書」と呼ばれますが、相違する部分もあり、復活後の記述に違いがあるのです。マルコ福音書とマタイ福音書では、復活したイエスが弟子たちに(表現は違うものの)「神の国をのべ伝え、人々に洗礼を施すよう」指示します(マルコ16章15-16節、マタイ28章19-20節)。マタイ福音書ではより詳細に、「父と子と聖霊の名において人々に洗礼を施すように」と言われます。しかし、ルカ福音書では、復活後、昇天を前に、イエスは弟子たちに「宣教するよう」にと語りつつ(ルカ24章47-48節)、近い時期に「弟子たちが聖霊による洗礼を受ける」と言います(ルカ24章49節、使1章5節)。
ルカで言われる弟子たちの洗礼は、弟子以外の人々が洗礼を受ける必要がないと言っているのではなく、聖霊によって洗礼を受ける弟子たちは、聖霊によって洗われ(罪が赦され)、聖霊に満たされて聖霊によって生きるキリスト者のモデルになるのだと言わんとするのでしょう。聖霊によって満たされた弟子たちの生きざまは使徒行伝に描かれ、そこでは特にペトロとパウロ、その他ステファノやバルナバといった人々が、いかに神とイエス・キリストに信頼し、神の救いの使信をのべ伝えたかが語られます。
大雑把に言えば、イエスの弟子たちはユダヤ人やギリシア人やローマ人、宗教や政治・行政を司る人々から少なからぬ反対を受けつつも福音宣教を続けます。パウロにあっては、キリスト者の仲間内からも彼に反対する人が現れ(使15章1-2節)、宣教の旅仲間・バルナバと袂を分かっても(15章39-40節)宣教活動を続けます。イエスの弟子たちは、彼らを取り巻く状況が芳しくなくとも、それでも積極的に活動し続けるのです。その原動力はどこにあるのでしょうか。
パウロはキリスト者を迫害した者だという強い自覚を持っていますし(26章9-11節)、使徒たちは無学な者、つまり教えるには相応しくない者たちとしてエルサレムの権威者たちから蔑まれています(4章13節)。楽観的とさえ言えるほどに宣教活動を続ける理由は、弟子たち自身には見出されません。ネガティブな状況でもポジティブに行動した理由が彼らの内にないのだとすれば、それは外側にあるはずです。
実際、使徒行伝に見つけうる弟子たちの宣教理由は、イエスによる任命(使1章8節、9章15-16節)と聖霊の扶け(1章5節、2章、3章29-31節、13章9-11節など)ですから、彼らのポジティブさは神(とイエスと聖霊)への信頼に根拠を置きます。聖霊に満たされ、神の栄光とイエスを目にした時にこそ、弟子の一人ステファノは彼を殺そうとする人々を前にしつつ「彼らに罪を負わさないように」と神に祈ります(7章54-60節)。
しかし暴力は甘受すべきものではない
ところで、ネガティブな状況であってもポジティブに生きた弟子たちの姿は、暴力は甘受されるべきものと教えていると捉えてはなりません。彼らの師であるイエスのエルサレムでの様子はそれを裏付けます。ルカ福音書22-23章がイエスに対する不正な逮捕と暴行と裁判を描くときに、確かにイエスは抵抗しません。しかし、イエスは一連の不正・暴力が起こる前に、オリーブ山での祈りの中で、苦しみ悶えながら、彼に起こる事柄を神に意図されている限り受け入れます(ルカ22章39-46節)。そして、復活後イエスは、彼の苦しみは(旧約)聖書によって預言された、神の救いのわざの一環だったとの理解を示します(24章25-27節)。
つまり、イエスはネガティブな事柄を単純に甘受しているのではなく、人々の救いになればこそ暴力・死をも覚悟して受け入れていているのです。弟子たちがネガティブな状況にあってもポジティブに活動するには、彼らもイエスと同様に神が人々を救おうとすることへの理解や、彼らもそこに参与するという覚悟があったのでしょう。
この世界でもサニーに

私たちも神とその救いに基を置く限り、この世界においてポジティブ、サニーに生きることが可能となるでしょう。そのときこの世界で正義・平和・愛を目指した生き方が劈(ひら)かれるのだと思います。