【追悼】 教皇フランシスコの12年間という恵み
アイダル ホアン SJ
上智大学神学部教授
私は、教皇フランシスコの生涯は、「現実への忠実さ」と「聖霊への忠実さ」によって説明できると考えています。一方では、彼は現実から目を背けることのない人物でした。問題から逃げることはなく、ましてや人生の途上で目の前にもたらされた問題を抱える人々から逃げることもありませんでした。しかし、他方では、この美しい人生の秘密は、「イエスの霊と共に生きた」ことにもあると理解することが極めて重要です。教皇フランシスコは多くのことを行い、多くの人々を助けてきましたが、それはイエスの霊と“共に”でした。
このような人生について語ることは容易ではありませんが、イエスにこの任務を助けてもらうなら、主の言葉を思い起こすことができます。「木はその結ぶ実によって知られる」(ルカ6:44)。それでは、この世界が12年間享受できた恵みを理解し、感謝する手助けとなることを願って、その実の一部を挙げてみようと思います。
1 教会の中心への回帰
何よりもまず、そしてこれが私個人として教皇フランシスコの在位期間で最も感謝している点ですが、フランシスコは教会をその中心に戻したと感じます。イエスの教会の中心は、伝統や教義、ましてや教会の組織的な成功にあるのではなく、具体的な人々、特に最も助けを必要としている人々にあるのです。教皇の友人であるマルティーニ枢機卿が適切に述べたように、「キリスト教は、私の目の前にいる人々の宗教」なのです。

| 教皇に選ばれる数日前のベルゴリオ枢機卿(当時) |
フランシスコは教会の教えをほとんど変えませんでした。しかし、その方向性を変えたのです。教会では「すべてが司牧的でなければならない」と、教皇就任の初めに述べました。「私は、すべてを造り替えるような宣教という選択肢にあこがれています。それは自己防衛ではなく、習慣も、様式も、時間も、言語も、そして教会のあらゆる組織的構造も、現代の福音化にふさわしい手段となるものです」(使徒的勧告『福音の喜び』27)。教会はピラミッドであることはやめられませんが、人々が上に、機関とその役職者が下に位置する「逆ピラミッド」となることはできます。「野戦病院」のようなものでなければならないのです。
しかし、教会は神が望まれるとおりの社会に他なりません。そのため彼は、「自己保存」と「自己成長」を目的とし、人々の具体的な顔や具体的な問題を無視する経済に対して批判的でした。『福音の喜び』の中で、教皇は社会について、教会についての言葉を思い出させることを述べています。「貧しい人々の問題が抜本的に解決されないかぎりは、世界が抱える問題は何一つ決定的には解決されません」(202)。
教皇在位中、サンタ・マルタの家でのサプライズ滞在から始まり、フランシスコは人々に寄り添うためにあらゆる努力をしました。教皇フランシスコに近く、長年バチカンで働いた人物は「これほど簡単に会える教皇は見たことがない」と言います。また、バチカン自体を「野戦病院」のような場所にするよう努めました。フランシスコは、バチカン内にホームレスのためのシャワーと避難所を設置するよう求め、困窮者向けの医療サービスなどを組織しました。2016年、ギリシャのレスボス島(数千人の難民がいた場所)を訪問した際、12人のシリア人ムスリム難民をバチカンの保護下でローマに住まわせるよう連れて帰りました。このような例は数え切れないほどあります。
ローマ教皇庁の改革と、彼の最後の大きな願いである「シノドス的教会」は、この教会のビジョンから生まれたものです。「シノドス的教会は、聴く教会である」とフランシスコは定義していました。
2 教会の扉を開く
次に、フランシスコは教会の扉を開いたと私は思います。教皇自身が言ったように、「家のドアは二つの目的で開けられます。家の中にいる人が外に出られるようにするためと、外にいる人が中に入れるようにするためです」。彼がこの12年間でやろうとしたのは、まさにこれだったのです。
2023年、リスボンで開催されたワールドユースデーで若者たちと徹夜で祈った際、教皇フランシスコは心の底から湧き出た言葉「みんな(Todos)、みんな、みんな!」を使いました。いかなる状態、過去、または個人的な状況に関係なく、神と教会の愛からは誰も除外されるべきではないことを明確にするために。彼は亡くなる直前にも、車椅子姿で、一生懸命にこの言葉を繰り返しました。
教会が教皇の望んだように「外へ出る」ことができたかどうか、私にはあまり確信が持てません。おそらくこれは、フランシスコが未来の教会に残した多くの課題の一つかもしれません。しかし、私が明確に感じているのは、教会から離れていた多くの人々が受け入れられたということです。実際に、教皇フランシスコの在位中、多くの人が教会に戻ってきました。離婚・再婚した人々、無信仰者、教会に失望した人々、LGBTQ+の人々、先住民などです。
個人的に、フランシスコの在位中に起きた歩み寄りの中で最も感謝しているのは、カトリック教会と完全な一致のうちにはないものの、より良い社会のために働く多くの個人やグループです。つまり、教会の教えから一部離れているかもしれませんが、最も重要な点では一致している人々です。教皇フランシスコの在位前、そのような多くの人々は、教会からほぼ離れており、あるいは教会と敵対する状況にさえありました。

| 教皇になってからもスラムに足を運んだ |
教皇フランシスコのこの言葉が特に気に入っています。「世の中には二種類の人がいます : 他者の苦痛の前に立ち止まる人と、通り過ぎる人。倒れた人を助ける人と、見て見ぬふりをして通り過ぎる人」。教皇は世界を「信者」と「非信者」に分けるのではなく、ましてや「カトリック」と「非カトリック」に分けるのではなく、他者の苦痛に対して慈悲深い人と無関心な人に分けるのです。それが、教会の門を内外に開くための態度なのです。
このような姿勢の例をいくつも挙げることができますが、ここでは教皇フランシスコと民衆運動の代表者との関係を取りあげたいと思います。教皇フランシスコは、教皇に選出された当初から、これらの運動の指導者たちに対して、彼らと集まりたいと希望していることを表明していました。2014年には教皇が招集した第1回民衆運動に関する世界会議がローマで開催され、2015年には教皇自らボリビアに赴き、第2回会議が開催されました。2016年11月にはローマで再び会合が開かれました。
これらの運動やそのメンバーの多くはカトリック教徒ではなく、いくつかの問題については教会の教えに反する立場をとっていますが、それでも教皇は様々な社会活動に従事するこれらの運動に聖霊の存在を見ているのです。聖霊は常に私たちを周縁や路傍に向かわせます。
「皆さんを見ていると、私は時々こう思います。組織化された貧しい人たちが自分たちの仕事を創設するとき、協同組合を作り、倒産した工場を再建し、廃棄された工場を再稼働させたり、悪天候をものともせずに広場で販売したり、農地を取り戻して飢えた人々に食料を供給するために農作業に従事したりするとき、このように働く皆さんはイエスに倣う者となっていると思います」 (第2回民衆運動に関する世界会議、ボリビア、2015年)
「自分の手を汚す」ことを恐れず、批判されることを恐れずに、教会内にとどまらない人々と集う教皇のこのような態度は、教会にとってだけでなく、対話相手にとっても善いことであり、「対話の文化」を生み出すものです。2014年にローマで開催された第1回の会合に参加した、ある運動の代表者が以下のような言葉を記しています。
「その場には、宗教や信条、民族、年齢、地理的にも多様な、世界中の労働者運動の代表者が180人以上集まりました。教皇フランシスコやバチカンからはいかなる制限も条件も課されず、歴史的な会合となりました。そこで私たちは、労働者が直面している問題、その原因、そして打開策の提案を一緒に分析したのです」
3 希望を取り戻す
最後に、私の見解では、教皇フランシスコの生涯は多くの人々に希望を取り戻させました。そして、これはおそらく、教皇の88年の生涯を通じて神が私たちに与えてくださった最も大きな恵みです。善人であることが不可能であり、少なくとも無意味であるように思えるこの世界において、教皇フランシスコは、イエスの弟子として生きることは可能であり、また美しいことであることを私たちに思い出させてくれました。
【論稿】 香港におけるキリスト教の現状と課題
―プロテスタントとカトリックの視点から―
松谷 曄介
金城学院大学准教授・宗教主事
はじめに[1]
2010年代以降、香港社会は二度にわたる大規模な民主化運動(雨傘運動および逃亡犯条例改正案反対運動)を経験してきた。これらの運動はそれぞれ異なる側面を持っていたが、共通していたのは、政治・経済・文化などあらゆる領域で進行する「中国化」の中で、香港社会の民主主義と自由をいかに確立・維持するかという問いに向き合っていた点である。
しかし、2020年に香港国家安全維持法が施行されて以降、これらの運動はすべて取り締まりの対象となり、香港政治史の専門家である倉田徹は「過去30年以上にわたり続いてきた漸進的な民主化が事実上終わった」[2] と断じている。
本稿では、そうした香港におけるキリスト教の現状と課題を分析することを目的とする。そのために、まず背景として中国大陸におけるキリスト教の状況を踏まえた上で、香港におけるキリスト教全般の動向を考察し、最後に特にカトリック教会に焦点を当てながら、今後の課題を明らかにする。
1 中国大陸におけるキリスト教
1-1 新中国におけるキリスト教の苦難
香港におけるキリスト教の現状を理解するためには、中国大陸における宗教政策と教会への統制のあり方を概観しておくことが不可欠である。
1949年に中華人民共和国が建国されると、宗教は新たな国家体制の下で再定義されることになった。共産党は無神論を掲げ、宗教を「迷信」や「旧時代の遺物」として扱ったが、特にキリスト教は西洋帝国主義と結びつけられ、排除と再編の対象となった。新政権は朝鮮戦争を契機にすべての外国人宣教師の国外退去を命じ、多くのミッションスクールを閉鎖、教会も活動を縮小させた。1960年代後半からの文化大革命期には、キリスト教も攻撃対象とされ、教会堂の破壊や聖職者の迫害が広がり、信徒たちは公の信仰活動を禁じられ、山中や自宅で密かに礼拝を行う、いわば中国版「隠れキリシタン」のような状態に追い込まれた。
1-2 迫害後の信者数の急増
こうした過酷な時期を経て、1978年の改革開放政策以降、社会に一定の自由が戻ると、キリスト教も都市・農村を問わず急速に拡大していった。1950年当時の信者数はプロテスタント約100万人、カトリック約300万人だったが、1980年にはプロテスタントが約300万人に達し、2010年には政府統計でプロテスタントとカトリックを合わせて約2900万人、ピュー・リサーチ・センターの推計では非公認教会を含め約6600万人とされた。
2018年には公認教会のみでプロテスタントが約3800万人、カトリックが約600万人と報告されており、これに非公認教会を含めた場合には総数は8000万人から1億人に迫る勢いとも推計される。[3] これは共産党員数に匹敵する規模であり、国家にとっても無視できない存在となっている。都市化による人間関係の希薄化、共産主義価値観への幻滅、天安門事件を経験した世代の政治不信などが背景にあり、教会は信頼できる人間関係と人生の意味を提供する場として多くの人々に受け入れられていった。
1-3 国家による宗教統制
しかし、中国政府はこうしたキリスト教の急拡大を単に容認していたわけではない。中国憲法第36条は信教の自由を認める一方、「宗教団体は外国勢力の支配を受けてはならない」とも規定しており、特に欧米諸国と関係が強いキリスト教は、常に政治的な監視の対象とされてきた。
中国政府は「五大公認宗教制度」を導入し、仏教・道教・イスラム教・カトリック・プロテスタントを、それぞれ公的団体の下に組織した。プロテスタントの場合は「中国三自愛国運動委員会」と「中国基督教協会」、カトリックの場合は「中国天主教愛国会」と「中国天主教主教団」への所属が義務付けられている。これらは名目上は宗教組織だが、実際には国家の宗教政策を実行する機能を有する機関でもある。この枠組みに加わらないプロテスタントの「家庭教会」やカトリックの「地下教会(忠貞教会)」は、違法組織と見なされ、繰り返し監視や取り締まりの対象となってきた。
近年では、習近平政権の下で「宗教の中国化」[4]が国家的スローガンとして掲げられている。宗教活動に対して、愛国主義教育や社会主義的価値の導入が求められ、宗教的自律はさらに制約されつつある。2014年には浙江省を中心に、公認教会であっても十字架が強制的に撤去される事例が相次ぎ、2017年には宗教事務条例の改正によって規制が一層強化された。2018年以降は、著名な家庭教会の閉鎖や牧師の逮捕が相次ぎ、宗教の自由は厳しい状況に置かれている。
2 香港におけるキリスト教
2-1 教育・福祉におけるキリスト教の影響力
こうした中国大陸とは異なり、「一国二制度」の枠内にある香港では、キリスト教が公共空間において広範な役割を担ってきた。特に教育や福祉の分野において、教会系団体の存在は際立っており、香港社会におけるキリスト教の信頼度の高さを物語っている。その背景には、1997年の中国返還以前、イギリス植民地下で長年にわたり培われてきた宗教的自由と教会主導の社会貢献の伝統がある。

| 香港 無原罪の聖母大聖堂 |
2022年時点で香港の総人口約740万人のうち、キリスト教徒は約86万人(約12%)とされ、その内訳はカトリック約38万人、プロテスタント約48万人であった(『香港便覧』2022年)。これに対し2024年には、キリスト教徒人口は約144万人(約19%)とされ、その内訳はカトリック約39万人、プロテスタント約104万人となっているが、プロテスタントに関しては「実際に教会に出席する信徒は約30万人」とも付記されているため、これが実数に近いと言える(同2024年)。
香港では教育面におけるキリスト教会の影響力が大きいのが特徴である。香港の小中高等学校のうち、半数以上がカトリックまたはプロテスタントの教会系学校であり、2024年時点で、カトリック系の教育機関(幼稚園含む)は249校、プロテスタント系は776校にのぼる。これは、公教育の担い手としての教会の地位を示している。
香港のミニ憲法とも言われる「香港基本法」は宗教の自由を保障しており、宗教団体は中国大陸の宗教機関から独立した存在としての地位を認められてきた。布教活動、教派の設立、学校や施設の運営においても、制度上の障壁は少なく、こうした点でも香港の宗教的自由度は際立っていたと言える。
2-2 2010年代の民主化運動とキリスト教
だが、2010年代に入ると、社会情勢の変化に伴って、教会は新たな政治的課題に直面するようになる。 普通選挙の実現を求める2013年の「セントラル占拠運動」[5] と、2014年に始まった「雨傘運動」[6] は、非暴力的な市民的不服従運動であり、特に雨傘運動では約79日間にわたって香港中心部が学生や若者を中心とする抗議デモ隊によって占拠された。これに対し、香港のキリスト教会として組織的な参与はなかったものの、キリスト教徒個人や有志での運動の参与が多く見られた。特に学生リーダーであった黄之鋒(ジョシュア・ウォン)や法学者の戴耀廷(ベニー・タイ)、牧師の朱耀明らは、キリスト教信仰を明言し、「信仰に基づく正義の追求」を行動の根拠に据えていた。ほかにも、有志による祈りや賛美歌、またテント張りの「路上教会」の出現など宗教的要素が抗議デモ現場に見られ、信仰と政治が交差する公共空間が生み出されていた。
こうした状況に対し、香港の教会内部では、キリスト教は政治的に中立であるべきなのか、道路占拠という違法活動に参与して良いのか、不正義に対しては抵抗・抗議すべきなのか、といった諸問題をめぐり大きな論争が起こった。2013~14年にかけての社会運動(広義の民主化運動)は、必ずしも政治的成果を挙げることができず収束していったが、多くのキリスト教徒たちが改めて「教会と政治」、あるいは「信仰と正義」の問題を真剣に考える契機となったと言える。
しばらくは大きな社会運動は見られなかったが、2019年、「逃亡犯条例改正案」に反対する抗議デモが勃発し、6月9日には103万人、6月16日には200万人以上が街頭に立ち、抗議活動は激化していった。警察の対応も次第にエスカレートし、デモ参加者に対する過剰な取り締まりが相次いだ。同条例案では中国への身柄引き渡しが可能となるため、香港社会全体の自由が侵害されることが懸念され、2014年の雨傘運動の時とは異なり、2019年の抗議活動では多くのキリスト教会も法案に対する反対や懸念の声明、さらに警察の暴力的取り締まりに対する抗議声明などを公表した。
その背景には、中国大陸におけるキリスト教への弾圧が強まる状況を身近に見ていた香港の教会にとって、香港における「宗教の自由」が守られるか否かが、極めて現実的かつ切迫した課題であったという事情がある。
2-3 香港国家安全維持法施行後のキリスト教
しかし2020年6月、「香港国家安全維持法」(いわゆる国安法)が施行されると、状況は急速に変化する。国家分裂や政権転覆、外国勢力との結託などを広義に解釈可能なこの法律の下で、政治活動・社会活動が萎縮し、多くの民主派団体・民間団体が解散や活動停止に追い込まれ、民主活動家たちは相次いで逮捕・起訴された。
国安法は宗教活動そのものを直接規制する条文を持たず、現在までのところ教会に対する迫害や取り締まりといったものは見られないが、キリスト教会が運営する教育機関などでは、愛国主義教育の導入など、確実に圧力が及び始めている。
また2022年5月、カトリック教会の元香港教区司教の陳日君枢機卿が「612人道支援基金」(2019年の抗議運動で逮捕・起訴された市民を支援する民間組織)への関与を理由に一時拘束された事件は、たとえ著名な宗教指導者であっても、政治活動における国安法違反の取り締まりからは逃れられないことを印象付けた。また、かつて「香港天主教正義和平委員会」が主催していた「天安門事件追悼ミサ」が2022年を最後に中止され、さらには同委員会が「全人発展委員会」へと改称されたことは、キリスト教会の政治参与に大きな制限が課せられたことを象徴している。
こうした香港の政治・社会情勢において、若者の教会離れや海外移民が相次ぎ、プロテスタント教会もカトリック教会も教勢が下がり始めている。プロテスタントに関しては、過去五年間で礼拝出席者が7万人減少したという統計がある。[7] またカトリックに関しては、少なくとも8千人の信徒減少が報告されている。[8]
3 中国政府とローマ教皇庁の関係と香港カトリック教会
3-1 愛国会と地下教会の対立
中国大陸におけるカトリック教会の状況は、宗教的・政治的に複雑な問題を抱えている。その核心にあるのは、ローマ教皇庁と中国政府とのあいだで未解決のままとなってきた司教任命権の帰属をめぐる問題である。[9]
1957年、中国政府は「中国天主教愛国会」を設立し、国家による教会管理の枠組みを明確化した。この組織の下で、政府承認による無認可の叙階が繰り返され、中国のカトリック教会は事実上、愛国会と地下教会に分裂することとなった。前者は中国政府の管理統制を受け入れるのに対し、後者はそれを拒否し、むしろローマ教皇への忠誠を堅持しつつ、国家による抑圧と監視の下で信仰を守ってきた。そのため、両者間には根深い不信感があり、統一的な一つの「中国カトリック教会」の形成は長く困難とされてきた。
3-2 司教任命に関する暫定合意
対立状況を打開すべく、教皇庁と中国政府は断続的な接触を続け、2018年9月に「司教任命に関する暫定合意」が両者の間で締結された。[10] 詳細は非公開だが、中国側推薦に教皇が承認する方式と理解されている。この枠組みによって、形式上は中国大陸のすべての司教が教皇とのフル・コミュニオン状態に復帰したことになる。以後、この合意は2020年、2022年、2024年と2年ごとに更新されており、基本的枠組みに大きな変更はないとされる。
しかし、この合意に対しては、国内外のカトリック関係者から賛否が分かれている。香港を拠点とする神学者・陳剣光は、その著書Understanding World Christianity: China(2019年)において、この合意を中国教会の「教会的正常化」に向けた現実的な一歩として評価している。彼は、分断されていた愛国会と地下教会の司教がともに教皇との交わりを回復した点を重視しつつも、地下教会の司教の位置づけや教区再編のあり方について、今後の課題として指摘している。
香港の陳日君枢機卿は、この合意が地下教会を見捨て、国家に迎合した妥協に過ぎないと断じてきた。とりわけ彼が問題視するのは、①非公開性、②非法司教の正当化、③「中国教会事務委員会」(前々教皇ベネディクト16世の下で設置された、中国カトリック教会に関する諸課題に対応するための教皇庁内の委員会)の解散である。これらを陳枢機卿は、「教会の自己崩壊を招く三部曲」と呼び、教皇庁が原則を曲げて中国政府に屈した結果、中国におけるカトリックの信仰的基盤が揺らぎかねないと警鐘を鳴らしている。
3-3 中国大陸と香港のカトリック教会の接近

| 北京教区の李山大司教(中央)と 北京を訪問した周守仁司教(左から2人目) |
さまざまな見解の相違があるなかで、2023年4月、香港教区の周守仁司教は、北京教区の李山大司教の招請を受けて公式訪問を行った。現職の香港教区司教が北京を訪れるのは、1994年以来、約30年ぶりのことであった。周司教は滞在中、マテオ・リッチの列福祈祷会に参加し、北京各地のカトリック教会での共同司式や、中国天主教神哲学院の視察、教職者や神学生との交流などを通じて、香港と中国大陸の教会間の関係強化を図った。
中国政府と教皇庁の関係回復や香港教区と北京教区の接近などは、これまで中国大陸の愛国会と地下教会、そして教皇庁との間の「橋渡し」の役割を果たしていた香港カトリック教会の位置づけにも変化を及ぼすだけでなく、いわゆる「台湾問題」にも影響を及ぼしかねない。現在、教皇庁は台湾(中華民国)と外交関係をもつ欧州で唯一の存在である。前述の「司教任命に関する暫定合意」は、あくまで教会内の司教任命に関する事項に限定しており、外交問題には触れていないとみられるが、中国政府がこの合意を梃子として、将来的に教皇庁に対して中国との外交関係正常化(すなわち台湾/中華民国との断交)を働きかける可能性も否定できない。
おわりに
香港社会において「言論の自由」などが大きく後退する中、プロテスタント・カトリックを問わず、「宗教の自由」が今後どの程度維持されるのかは、重要な課題の一つである。また、移民による信徒の流出や、次世代の聖職者・信徒の育成への対応も、喫緊の課題と言えよう。
さらにカトリックに関しては、暫定合意を締結した教皇フランシスコが2025年4月に逝去し、同年5月には新たに教皇レオ14世が選出されたばかりである。今後、新体制の下で教皇庁の対中外交がどのように展開されるのか、またその過程で香港や台湾の問題にいかなる影響が及ぶのか、引き続き注視する必要がある。
[1] 本稿は、2025年3月19日にイエズス会社会司牧センター主催の講演会で使用された講演資料をもとに執筆したものである。
[2] 倉田徹「2021年の香港特別行政区 民主化の終わりと民主派の徹底弾圧」、『アジア動向年報2021』アジア経済研究所、2022年、128頁。
[3] ただし、家庭教会の正確な統計は困難であり、数値には幅がある点にも留意が必要である。中国におけるキリスト教人口についての諸議論は、以下の文献を参照。
Kim-kwong Chan, Understanding World Christianity: China (Augsburg: Fortress Press, 2019), 32-36.
[4] 「宗教の中国化」については、以下の論稿を参照。村上志保「宗教中国化とキリスト教の『洋』――中国プロテスタント教会に見られる変化」『明治学院大学キリスト教研究所紀要』第54巻(2022年)、185-211頁。
[5] セントラル占拠運動(Occupy Central)は、2013年に法学者の戴耀廷、牧師の朱耀明、社会学者の陳健民の三人が呼びかけ人となって始まった運動である。2017年の普通選挙実施に見通しが立たない場合には、香港の金融街「中環(セントラル)」を占拠して政府に圧力をかけると主張した。翌年の「雨傘運動」とは厳密には区別されるが、その導火線となり、両者を併せて「オキュパイ運動」と呼ぶこともある。
[6] 2014年8月31日、中国政府は香港における2017年の普通選挙実施に関する方針を発表したが、立候補者に対する事前審査などが含まれており、民主的な選挙制度とは言えないとして、学生を中心とする抗議活動が激化した。9月から12月にかけての79日間、立法会周辺などの道路を占拠する運動が展開された。この運動は、警察当局による催涙ガスの使用に対し、デモ参加者が雨傘で防御したことに由来し、「雨傘運動(Umbrella Movement)」と呼ばれている。
[7] 「『香港教会調査』で報告会 礼拝出席者は5年前から約7万人減」『キリスト新聞』2025年4月1日、https://www.kirishin. com/2025/04/01/72137/(2025年5月8日閲覧)。
[8] カトリック香港教区の公開統計によれば、2019年の信者総数は40万3千人(うち永住権を持たない外国人信者が21万7千人)、2024年は39万人(同21万2千人)とされている。このことから、2019年の香港人カトリック信者数は18万6千人、2024年は17万8千人と推計される。参照:香港天主教教区『統計資料』、https://archives.catholic.org.hk/Statistic/ST-Index.htm(2025年5月8日閲覧)。
[9] 近現代の中国カトリック教会については、近刊の以下の文献に詳しい。Chan, Kim-kwong. Dancing to an Ever-Changing Melody: The Communist Party of China and the Catholic Church. Hong Kong: Holy Spirit Study Centre, 2024.
[10] 教皇庁と中国政府の間の交渉については、以下の論文を参照。中津俊樹「バチカン・中国関係の展開をめぐって――『原則』と『一致』のあいだで――」『アジア経済』第65巻第1号(日本貿易振興機構アジア経済研究所、2024年)、2-28頁。
日本の近現代史を学ぶ書籍紹介シリーズ 【3】
沖縄戦を振り返る
編集部
――「沖縄戦」から80年の年月が流れる。その沖縄戦が現在の私たちに問いかけるものは何か。歴史研究書だけではなく、証言集や絵本、写真集、小説、コミックも挙げてみた。
1) 林 博史 『沖縄戦 なぜ20万人が犠牲になったのか』集英社新書 2025年
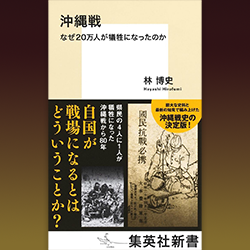
目次
序 なぜ今、沖縄戦か / 第1章 沖縄戦への道 / 第2章 戦争・戦場に動員されていく人々 / 第3章 沖縄戦の展開と地域・島々の特徴 / 第4章 戦場のなかの人々 / 第5章 沖縄戦の帰結とその後も続く軍事支配
『沖縄戦と民衆』(大月書店、2001年)や『沖縄戦が問うもの』(大月書店、2010年)、『沖縄戦 強制された「集団自決」』(吉川弘文館、2009年)などの著者が、近年の調査研究の成果を踏まえて、全体像を描く。その視点は、これほど多くの犠牲の根本的な原因と責任はどこにあるかという問いかけである。沖縄戦について知ろうとするとき、まずこの本をお勧めする。
2) 前田勇樹 古波藏契 秋山道宏 編 『増補版 つながる沖縄近現代史 : 沖縄のいまを考えるための十五章と二十五のコラム』 ボーダーインク 2025年

目次
第1部 狙われた島々(「琉球処分」の一四〇年など) / 第2部 「日本人」への扉(沖縄の人々にとって「日本人」になるってどういうこと? など) / 第3部 「沖縄戦」に潜むもうひとつの歴史(エスニック・マイノリティの沖縄戦など) / 第4部 アメリカ世と日本復帰にひきさかれて(何が人々を「島ぐるみ闘争」へと駆り立てたのかなど) / 第5部 沖縄社会を編みなおす(くりかえす沖縄ブームと基地問題など
比較的若手の研究者29人が、入門書となることを目指して、沖縄の近現代史を通史的に15の課題に分け、さらに25のトピックをコラムとして取り上げている。2021年に出版されたものに、「鉄道のある県民生活」や「女性と琉球人形から考える戦後」など5本のコラムと「つなげて読んでほしい編者オススメのブックレビュー」が加えられた。
本書はペリー来琉の話から始まる。この時期が近代沖縄の前史にあたり、さらに現在につながるアメリカの太平洋進出の歴史と琉球沖縄史の起点となるためである。沖縄戦自体については詳細を述べていないが、沖縄戦を沖縄近代史全体の中で見直すための視点を与えてくれる。ちなみに、ボーダーインクは沖縄の出版社である。
3) 前田勇樹 古波藏契 編 『かたりあう沖縄近現代史 : 沖縄のこれからを引き継ぐための七つのムヌガタイ』 ボーダーインク 2025年

目次
第1章 シン・琉球史の時代へ / 第2章 現在進行形の「沖縄民衆史」を記す / 第3章 歴史としての地元を掘る/ 第4章 島嶼としての沖縄経済の自立は可能か / 第5章 「うない」が広げた女性たちの結(ゆい) / 第6章 伊波普猷(いはふゆう)を読むということ / 第7章 教育熱心な沖縄をひも解く
『つながる沖縄近現代史』の続編。若手の研究者たちが、高良倉吉や謝花直美、冨山一郎といった上の世代の研究者などと7つの主題をめぐって語り合う、沖縄近現代の物語り[ムヌガタイ]である。さまざまな角度から沖縄の近現代史を問いかけ、また私たちがどのような立場から沖縄、そして世界に相対していけばよいかを問いかける。
4)吉浜 忍 林 博史 吉川由紀 編 『沖縄戦を知る事典 非体験世代が語り継ぐ』 吉川弘文館 2019年

目次
第1章 どうして今、沖縄戦なのか / 第2章 沖縄戦とはどのようなものだったのか / 第3章 沖縄戦の諸相(「集団自決」 日本軍「慰安婦」 米軍にとっての沖縄戦など) / 第4章 人々の沖縄戦体験 / 第5章 沖縄戦が残したもの
「ただ“生まれなかった”とおもったらそれでいいんじゃなか、と」 これは沖縄北部のジャングルで、少年ゲリラ兵として最前線に立たされた当時一六歳だった男性が、戦後七〇年近くなってようやく語り始めた体験談です。一〇キロの爆弾を抱えて敵戦車に体ごと突っ込む「特攻隊」に任命されたときの気持ちを「あっという間に、わかんないうちに亡くなるから。別に苦しんで死ぬわけではないから」とおっしゃった後、冒頭の言葉が続きました。(本書冒頭より)
沖縄戦が終わって80年が経つ。16歳の少年に「この世に生まれてこなかったと思えばいいのだ」と死を受け入れさせ、それを70年も語らせなかったあの沖縄戦とは何だったのかという問いかけが本書の根底に流れている。本書は沖縄で暮らす27人と沖縄に頻繁に通う1人の計28人、全員戦争経験のない人が執筆している。
5) 古賀徳子 吉川由紀 川満 彰 編 『続・沖縄戦を知る事典 戦場になった町や村』 吉川弘文館 2024年

目次
第1章 南部 / 第2章 中部 / 第3章 北部 / 第4章 周辺離島・大東島 / 第5章 宮古・八重山
前掲書が全体として時系列的にまとめられているのに対して、本書は地域別に編集されている。沖縄では1970年代に『沖縄県史』『那覇市史』が刊行されたことをきっかけに、80年代以降、ほとんどの市町村が沖縄戦に関する聞き取りなどの調査に取り組んできた。本書はその成果を基に、24の市町村を選び、その地域や島々が沖縄戦によってどうなったのか、それぞれの特徴とは何かを問うている。各項目には、「那覇市―沖縄戦以前に空爆で壊滅した街」「宮古島市―空襲と飢餓」のように、その地域の特色が一目でわかる見出しがつけられている。また、名護市の項目では、「沖縄愛楽園―隔離と排除の中で生きたハンセン病者」も含まれている。
6) 琉球新報社 『沖縄戦新聞 当時の状況をいまの情報、視点で』 琉球新報社 2005年
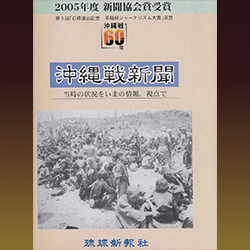
「戦時下の新聞は、戦争の正当性を流布し戦意高揚に加担、国民を戦争へと駆り立てた負の歴史を背負っています。琉球新報社も例外ではありません」。本書発刊の言葉の一部である。第1号「サイパン陥落」に始まり、第7号「米軍、本島上陸」、第10号「第32軍、首里放棄」、そして第14号「南西諸島の日本軍が降伏調印」で終わる。学校教育の教材にもふさわしい
7) 大田昌秀 『決定版 写真記録 沖縄戦 国内唯一の“戦場”から“基地の島”へ』 高文研 2014年

著者は沖縄師範学校在学中に鉄血勤皇師範隊の一員となる経験を持ち、1990年から沖縄県知事を2期8年務めた。著者がアメリカ公文書館に通い続け、米軍報道班が撮影した膨大な写真から厳選した写真記録である。
8) 謝花直美 『戦場の童 沖縄戦の孤児たち』 沖縄タイムス社 2005年

目次
戦場で生まれた子どもたち / 戦場の童(渡具知のカマデー; 赤いランドセル; 義勇軍と奉公; きょうだい捜し; 愛隣園1期生; 「つるちゃん」の戦後)
「二十万人余が亡くなった沖縄戦。命を奪い尽くす戦場の中で、赤ん坊が生まれた。母親は胎内の子どもを必死に守り、避難先や壕や山中、収容所で出産した。おびただしい死に直面し、希望を忘れかけていた人々も、みずみずしい命に、「生きる」という勇気を与えられたに違いない。戦後六十年の今年、その「赤ん坊」は還暦を迎える。第二の人生を祝う節目の年に、思いを語ってもらった。」(本書冒頭より)
子どものころ沖縄戦を体験した方々の生の声を載せている。
9) 丸木 俊 丸木位里 『おきなわ 島のこえ : ヌチドゥ タカラ 〈いのちこそ たから〉』 (記録のえほん3) 小峰書店 1984年
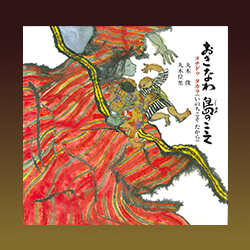
丸木 俊『ひろしまのピカ』(記録のえほん1)、石牟礼道子文、丸木 俊・丸木位里絵 『みなまた海のこえ』(記録のえほん2)に続くものである。
「イクサユン シマチ、ミルクユン ヤガティ(せんそうは もうじき おわる、へいわで ゆたかな ときがくる) ナギクナヨ シンカ、 ヌチドゥ タカラ(なくなよ みんな、いのちこそ たから)」という歌が本書に二度出てくる。作者の願いであり、沖縄の祈りであり、平和を求めるすべての人の祈りである。
10) 豊永浩平 『月ぬ走いや、馬ぬ走い』 講談社 2024年

著者は、2003年、那覇市生まれ。琉球大学在学中に本書を出し、第67回群像新人文学賞、第46回野間文芸新人賞を受賞した。
先祖の魂が還ってくる盆の中日、幼い少年と少女の前に、78年前に死んだ日本兵の亡霊が現れる・・・タイトルは光陰矢のごとしという意味に近い。14の断片によって構成され、14人の語り手がいくつかの事件や遺品で関係を持ちつつ進行する。暴力と性の連鎖の中で、希望とは何かを問う。
11) 高 妍 『隙間』 (ビームコミックス) KADOKAWA 2025年 全4巻

著者は、1996年、台北市生まれ。台湾芸術大学視覚伝達デザイン学系卒業、沖縄県立芸術大学絵画専攻に短期留学の経験を持つ。
台北に暮らす女子大生の楊洋(ヤンヤン)。懸命に介護を続けていた大切な祖母を亡くし、さらに想いを寄せていた男性には別の恋人がいて…すべてから逃げるように、楊洋(ヤンヤン)は交換留学生として、近くて遠い異国・沖縄へと旅立つ。沖縄の人々との交流やその地に刻まれた歴史に触れる中で、少しずつ自分を取り戻していく。「“戦争”が“破壊”なら “破壊”と相対するものが“創造”なんだ」と問う言葉が印象的である。
UAPsに関するイエズス会総長書簡
『イエズス会使徒職全体の方向づけ』(Universal Apostolic Preferences=UAPs)は、教皇フランシスコの承認を得たうえで、イエズス会総長アルトゥーロ・ソーサ神父が2019年に全イエズス会員と協力者宛に出した文書である。その主な内容は、A)霊操及び識別を通して神への道を示すこと、B)和解と正義のミッションにおいて、貧しい人々、世界から排除された人々、人間としての尊厳が侵害された人々とともに歩むこと、 C)希望に満ちた未来の創造において若い人々とともに歩むこと、D)「ともに暮らす家」(地球)への配慮と世話を協働して行うことである。この度、総長はその内容を刷新した書簡を出したので、邦訳をお届けする。
主における愛する友の皆さんへ
5年前、識別の期間を経て、私たちは教皇フランシスコから、「イエズス会使徒職全体の方向づけ 2019- 2029」(UAPs)を受け取りました。教皇フランシスコは、イエズス会への宣教書簡の中で、教皇の通常教導権、シノドス、司教協議会を通して、特に使徒的勧告『福音の喜び』発行以来表明されているように、UAPsが教会の優先事項と一致していることを明確にされました。
2024年6月、UAPs実施の第二段階開始に際して、私たちはイエズス会の社会正義とエコロジー事務局に、使徒職全体としてUAPsの第4項目「ともに暮らす家(地球)への配慮と世話を協働して行うこと」に、どのように対応しているかを調べるよう依頼しました。
調査の結果、イエズス会の地区、管区、上級長上協議会にわたって、数多くの前向きの進展が世界中で起きていることが明らかになりました。それは、私たちが抱いていた善き意図を超えるものでした。私たちは大きな進歩を遂げましたが、まだ直面すべき課題があります。
- 私たちの計画には、常に貧しい人々や社会から排除された人々が含まれているべきであり、彼らの声を聴き、それに応えなければならない。
- 私たちは、「ともに暮らす家」(地球)を大切にするために、管区、地区、ネットワーク、上級長上協議会を通して、より一層協力し合う必要がある。
- 私たちは、気候正義を提唱するために、自分たちの使徒職以外の他のグループとも協力しなければならない。
私たちは皆、聖イグナチオの霊性とその教育法の賜物を分かち合い、享受し、持続可能で統合的な発展のために責任をもって管理する文化を受け入れ、貧しい人々と彼らが直面する重大な課題に寄り添い、世界的な環境悪化を逆転させるために合意された行動を確実に履行する公共政策を推進するよう求められています。これらの計画には、主要なエネルギー源の化石燃料からの代替、環境を破壊する鉱物資源の採掘・搾取の抑制、水源、土地、生物多様性の保全などが含まれています。
このように相互につながっているUAPsは、私たちがカリスマの源からインスピレーションと霊的な力を引き出すよう招いています。「ともに暮らす家への配慮と世話を協働して行うこと」とは、私たちが神との関係、お互いとすべての被造物との関係を新たにする道義的責任を果たすということです。「ともに暮らす家への配慮と世話を協働して行うこと」とは、気候変動が貧しい人々や社会的弱者の苦しみを増大させ、不公正な構造を生み出す原因を永続させる中で、彼らと共に歩むことです。「ともに暮らす家への配慮と世話を協働して行うこと」とは、教皇フランシスコが「いま現在において未来を築いている人々」として称える若者たちに同伴することです。支配的な経済システムによって引き起こされる環境破壊は、現在地球に住んでいる人々に影響を与えるだけではなく、将来の世代の生活にも影響を及ぼし、危険にさらします。ネイティブ・アメリカンのシアトル酋長の言葉にあるように、「我々は、大地を受け継ぐのではなく、子どもたちから借りているのです」。
イエズス会の社会正義とエコロジー事務局は、社会正義とエコロジーに対する私たちの信仰と献身において、イエズス会の使徒職全体を導き、活気づける特別な役割を担っています。それでもなお、UAPsの4つ目の項目は、私たち全員の責任です。これからもアイデア、時間、資源を結集し、私たちの「ともに暮らす家」をよりよく世話するために、願い、意志、計画を団結させましょう。
この「希望の聖年」の間、私たちがUAPsを深く理解し、実践し続ける中で、神への信頼を見出し、神にのみ信頼を置くことができますように。キリストにおける万物の和解のために効果的に協力できるように、聖母が私たちのために、いのちの誠実さの恵みをお与えくださいますように。
(2025年4月22日、アルトゥーロ・ソーサ総長)
心にかかり続けた“加害者家族”のそれから
~オウム事件と私の30年~
長塚 洋(よう)
映像作家・ジャーナリスト
地下鉄サリン事件から30年となる今年3月には、オウム真理教より長く問題視されてきたカルト教団である統一教会への解散命令が同時期にあったこともあり、さまざまな回顧報道がされた。だが、オウム事件の直接の当事者たちにとってもっと大きな「30周年」は5月16日、教祖・麻原彰晃こと松本智津夫の逮捕のそれかもしれない。教団が拠点として築いた「サティアン」なる建物に機動隊員らが突入し、教祖の身柄を確保したものものしい映像は、同時代人の多くが記憶しているだろう。
異様な反応
私自身は、その5年ほど前から在京の民放テレビ局に席を与えられて事件報道に従事していたのだが、オウム事件が“はじけた”3月20日から教祖逮捕までの7週間とその後しばらくは、連日組まれた特番の担当デスクの一人として、不眠不休に近い日々を過ごすことになった。刻々と洪水のように押し寄せる情報を一つ一つ確認していく中で、社会の側の異様な反応を感じることも少なくなかった。末端の信者が、自転車のライトをつけていなかった「無灯火」だけで逮捕されたりしていた。オウムそれ自体が社会の脅威と見なされたいわば緊急の状況だからといって、ここまでの人権侵害が許容されるのか。だがそうしたささやかな疑問も、怒濤の報道業務の中でかき消されていった。
それでもなお私の目を釘付けにしたもの、それが「オウムの子たち」を写し出した報道だった。なかには、当時まだ12歳の「教祖の娘」が教団施設を取り囲む報道陣に不敵な態度を取る姿を捉えた写真を、敵意をにじませて掲載するスポーツ紙や写真週刊誌まであった。

| 原田正治(左)と松本麗華(右) ドキュメンタリー映画『それでも私は Though I’m His Daughter』より © Yo-Pro |
それまでの他の殺人事件などの取材で、私は被害者家族だけでなく、加害者側の家族たちにも数々出会ってきた。彼らの多くが事件発生直後、自分の家族が犯罪を起こしたとされることに戸惑い、こちらの問いに答えるのもやっとだという姿を今も記憶している。教団で育った子らが、身近な人にかけられた犯罪の嫌疑を受け入れられず、迫る強制捜査や押し寄せるメディアに反発するのも自然な感情だろうと、感じざるを得なかった。そしてこの子こそはあの5月16日、彼女にとっては大切な人である父親と引き裂かれる衝撃を、経験することになるのだ。
この子にはこの後、どんな人生が待っているのか?
犯罪に関わっていないのに
それから20年余りが経ったある日。事件の当事者の「その後」を追うことに注力するようになっていた私は、あのときの「教祖の娘」と出会い、やがて彼女を主人公にドキュメンタリー取材を始めることになる。そのきっかけとなった人物は、原田正治。実弟を殺害した死刑囚と面会し、交流したことで有名な男であり、私も交流させていただいていた。その原田が2018年2月、どうしても会って話したいというので私が引き合わせたその相手が松本麗華(りか)。このとき34歳、あの教祖の娘だ。27人の命を奪い数千人を負傷させた一連の事件の首謀者と認定された父・智津夫は、いまや死刑囚となって獄中にいる。
被害者家族と加害者家族という、真逆とも言える二人だが、この日、「当事者」としての痛みで共感し合うことになった。原田は弟を殺害した死刑囚の息子が自ら命を絶ったことに触れ、加害者の家族も被害者であり謝罪は必要ない、自殺にまで追いつめた社会にこそ責任があると、強い口調で言い切った。麗華の方は、父親が逮捕の後、言動に異常を来し、面会しても会話が成り立たなかったために、父の事件への関与が分からない、もし関与が事実だとしても「父の口から聞いて受け入れたい」と吐露。加害者家族の苦しみは、20年以上が経っても去っていなかった。
「加害者家族」という、もう一つの「被害者」の現実を伝えたいと願い、この後も麗華を撮り続けようと筆者が決めた矢先、父・智津夫の死刑が執行された。麗華が事件をめぐる真実に近づく機会は、永遠に失われてしまう。
家族に責めを負わせる社会
執行の直後から、本人のSNSアカウントには以下のような匿名のコメントが次々と書き込まれた。
「ざまあみろ。てめえもさっさと後追いでくたばれ」
「お前の臓器でも売って、被害者に1円でも多く差し上げろ」
「あなたは幸せにはなってはいけない人生」
罪の報いとは言え、親が命を奪われた相手に投げつける言葉として余りに残酷な言葉の数々はネット社会ならではとも思えるが、実はSNSのない時代にも、加害者家族に脅迫めいた手紙が届くことは起きていた。報道の一角を担ってきた私は、ときに暗い思いに囚われる。事件報道そのものは、捜査側の発表に頼らず、取材者の責任で情報と視点を人々に提供し考えてもらう大切な営みだと今でも考えるが、他方でそれは家族を攻撃する材料も提供する結果になるからだ。
麗華は、自分には愛おしい父親の死を日本中が望んだのだという絶望に苛まれながら、それでもこの社会で生きようとあがく。すくむ心を励まして就職を試みるが、松本智津夫の娘だと知られ解雇される。銀行では口座の開設を断られる。差別されない世界に逃れたくて海外旅行を試みても、入国を拒否される。これらの出来事の背景には国が、麗華をオウムの後継教団の「幹部」とする認定を今も取り消さないことがある。彼女のいた教団から社会を揺るがす凶行が生まれたのは事実だが、だからと言って本人が犯罪どころかその準備に関わった証拠も示さないまま、将来の危険という可能性だけを理由に、国が個人の幸福追求権を奪っているのだ。



| ドキュメンタリー映画『それでも私は Though I’m His Daughter』より © Yo-Pro |
だがそうした国の振る舞いを支える、死刑囚だけでなくその子もモンスターであるかのように見て排除しようとする社会の側の心理の存在も、忘れるわけにはいかない。前述の書き込みほどの残酷な表現は取らずとも、私たちの心のどこかに「これだけの罪を犯した者の家族が責めを負うことは仕方ない…」というような感覚が、潜んではいないだろうか? そんなことをスタッフとずっと論じ合いながら、ドキュメンタリーを作り続けた。
取材中、麗華は何度も「死にたい」と漏らす。死刑囚の家族は、大切な人の生存を社会から否定されている。死刑執行の恐怖やトラウマは時を経ても麗華から消えることはなく、自分自身が社会から否定されていると感じるたびに、その痛みが蘇る。
そして自分が関与していない犯罪であっても起こる、罪責感情。犯罪事実について父親から聞けずに終った麗華は分かりやすい「お詫び」を口にはしないが、被害者のことを思う時「私が生きてて申し訳ない」との悲痛な思いに囚われると、カメラの前で吐露した。
それでも彼女が何とか死を選ばずに自分の人生を再生しようとしていく様は、ぜひドキュメンタリー映画で見届けていただきたい。映画『それでも私は Though I’m His Daughter』は今年完成し、この6月から順次公開される。私たちの同時代で最も憎しみを集めたと思われる加害者の家族が主人公である本作は、彼女が41歳になるまでの6年間を記録することになった。父親との別れからこの5月で30年を超え、松本麗華は今も必死に生きている。
「受容」に向かうために
日本社会は欧米に比べて家族主義が強いとされる。そこには良さもあるかもしれない半面、犯罪に手を染めてもいない家族も同罪、あるいは連帯責任があるかのごとくに責め立てる空気が根強いこともまた、感じざるを得ない。
だが「異質」と見なした他者への「排除」は事件の周囲に限らず、そして日本に限らず、世界のあちこちでよりむき出しになり力を増しているという危惧を抱く。それぞれの国で思想、人種や民族、あるいは生活保護受給者などという属性をもとに行われる排除や差別。様々な国際紛争で、相手の命を奪うまでに至る分断。
私たちを引き裂く心の闇をどう克服して「排除」から「受容」に向かえるのかを、考え続けるしかない。そのためにも多くの人に、私たちの隣人である「加害者家族」のことを知り、向き合ってもらえたらと願う。

