私たちはさらに何をしなければならないのか?
アルトゥーロ・ソーサ総長の 「世界社会正義の日」 メッセージ
アルトゥーロ ソーサ SJ
イエズス会総長

2024年2月20日の「世界社会正義の日」に寄せた短いビデオメッセージにおいて、イエズス会総長のアルトゥーロ・ソーサ神父は、「ますます不公正になる世界」の中で続く不正義を指摘したうえ、正義、平和、和解のためにたゆまぬ努力を続けている人々を称えつつ、「主イエスとともにこうした犠牲者を十字架から降ろす」ため、さらに尽力する必要性を喚起しています。
「私たちはますます不公正な世界に生きています。
2022年以降、40万8000人以上が戦争や武力紛争で命を落としています。(世界平和度指数、武力紛争発生地・発生事象データプロジェクト)
2023年だけでも、1億1000万人以上が避難を余儀なくされています。(国連難民高等弁務官事務所)
毎時、砂漠化が6.4平方キロメートルの肥沃な土地を脅かしています。(The World Counts)
2024年、世界人口の半数が選挙に参加します。2005年から2021年の間に、60か国が民主的自由度を低下させました。210か国中125か国では、民主主義が制限されているか、もしくは存在していません。(世界の自由2023)
2022年、7億3600万人の女性がジェンダー暴力の犠牲になりました。(国連女性機関)
約25万トンのプラスチックが世界中の海を汚染しています。(科学誌「プロス ワン」)
5歳未満の子どものうち、10人に3人が急性栄養失調に苦しんでいます。(ユニセフ)
私たちはこの世界に何をしてきたのでしょうか?
私たちは虐げられている人々のために何をしているのでしょうか?
イエスとともにこうした犠牲者を十字架から降ろすため、私たちはさらに何をしなければならないのでしょうか?」
次世代のこと
~マラウィの難民とインドネシアの先住民との出会いから~
成井 大介
カトリック新潟教区司教 / 「ラウダート・シ」 デスク責任司教
良心において、また、人々の行動がもたらした損害の付けを払わされるであろう子どもたちを前にして、意味を問う問いが迫ります。――わたしの人生の意味は何か。この地上でわたしに与えられている時間の意味は何か。わたしの働きと努力のすべてには、究極的にどんな意味があるのか。
(使徒的勧告『ラウダーテ・デウム』33)

いかに短い時間でより多くの成果を上げるかを追求する功利主義。自分にとって役に立つ物や人、それも今役に立つものだけを一時的に利用し、捨てる、使い捨て文化。自分の行動の結果が、自分が生きている社会の仕組みが、次の世代にどのような影響を与えるのかを知ろうともしない傲慢な生き方。こうしたことが当たり前の社会の中で生きるわたしに、この言葉は深く突き刺さります。
わたしは、カリタスジャパンや、所属する修道会の仕事で、慢性的な貧困地帯、先住民の権利が脅かされている地域、難民キャンプや紛争の直中にある地域などを訪問し、非常に厳しい生活環境で生きている子どもたちに出会ってきました。ここでは、次世代との関係で大切な気づきを与えてくれた二つの出会いを紹介したいと思います。
一つ目は、マラウィの難民キャンプの子どもたちです。JRS(イエズス会難民サービス)はアフリカ南東部にあるマラウィの首都、リロングウェ北部のザレカにある難民キャンプで活動しています。このキャンプには、周辺国、特にコンゴ民主共和国の紛争地域から逃れてくる人が多く住んでいますが、マラウィでは難民の定住が認められておらず、難民キャンプから出て町の中で住むことができません。基本的に人々の選択肢は、自分の国に戻るか、アメリカやオーストラリアなどの第三国定住に望みをかけるか、またはずっと難民キャンプにいるかしかありません。自国への帰還は難しく、第三国への定住が実現する人も非常に少ないのですが、難民キャンプに来る人は多いので、キャンプの人口は増え続けることになります。わたしが訪問した2019年には、4万人以上の難民が住んでいました。
JRSはこのキャンプで、初等、高等教育を行う傍ら、生計向上支援、心理社会的サポートなどを行っています。当時、わたしの所属する神言会は一人の司祭と、一人の神学生をこのキャンプのJRS事務所に派遣し、心理社会的サポート活動に関わっていました。わたしは彼らを訪問し、3日間ほど活動をともにしました。
この難民キャンプで子どもたちや青年は、「いつ第三国に行ってもいいように、英語を勉強しようね」とか、「第三国に行ったらすぐに就職できるように、ミシンの使い方を覚えよう」と呼びかけられ、学びます。しかし、周りを見ても第三国に行く人はあまりいません。代わりに新しい難民と墓が増えていきます。「英語を勉強したって、ミシンの使い方を覚えたって、どうせここから出ることはできないじゃないか。」当然、子どもたちはそのように思うでしょう。
JRSは世界の難民支援の場で教育や生活支援などを行いますが、それは「希望を与えるため」に行われています。しかし、上記のような、何年経ってもキャンプから出ることができないような状況で、はたして希望を与えることなどできるのでしょうか。
神言会が派遣した司祭と神学生は、心理社会的サポート活動として、ミサ、赦しの秘跡などの秘跡、家庭訪問、自助グループの設立とアニメーション、自助グループごとの家庭ミサや祈りの集い、近隣の清掃活動、青年グループ活動、子どもたちのレクリエーションなどを行っていました。先の見えない困難な状況にあって、子どもも青年も親も精神的に厳しい状態にある人が多くいました。
しかし、そんな状況だからこそ、ともに祈ること、互いを思いやること、支え合うことは、彼ら、彼女らが日々生きていく中でとても大きな意味を持つことなのだと強く感じました。学校で学ぶのも、将来役に立つか立たないかというよりは、そうした歩みの一部なのだと感じました。希望というのは、将来にむけた計画を実現するのに必要な要件がそろっている時に生まれるものなのではなく、たとえ全くの暗闇の中で何の肯定的な要素もない中でも、神に自分を投げ出し、人々と日々ともに歩む中で自然に生まれてくる小さな喜び、今を生きる喜びのことをいうのだと思い知らされました。
翻って、日本での生活はどうでしょうか。住む家や着るもの、食べるもの、教育や就労の機会などは難民キャンプとは比べものにならないほど整っていますが、祈りや支え合い、小さな喜びを大切にしてともに歩む生き方が子どもにも大人にもあるでしょうか。
二つ目は、インドネシアの熱帯雨林に住む先住民の人々です。赤道直下に位置するインドネシアは広大な熱帯雨林を抱える生物多様性の豊かな国です。先住民の人々は、森で自然の恵みを受けながら生きてきました。食用の植物や動物、薬用の植物を得ることができるというだけでなく、先住民にとって森は神聖な場所であり、霊的、文化的な側面でも生きるのに必要なものです。しかし開発が進み、広大な地域で森林を切り開いてアブラヤシ農園などが作られています。
わたしは2017年に、アブラヤシ農園開発で森を失った先住民を訪ねました。サグという椰子の木の幹から取れるデンプンを乾燥させ、固めた食糧の作り方。森で弓を使って鹿を取る方法、自然と密接に関係する信仰の持ち方など、生きていくために大切な事柄を教えてくれました。

セスナ機に乗って、上空からアブラヤシ農園を見ましたが、地平線の先まで農園は続いていました。生物多様性の宝庫であった熱帯雨林は、アブラヤシが生えるだけの土地にされています。
先住民のリーダーの人が言っていました。「森が無くなるのはわたしたちのいのちを左右すること。でも、それはまだ良い。いずれ何とかする。一番困っていて、全くどうしたらいいのかわからないのは、自分たちの子どもたちがスマートフォンに夢中で、森とともに生きる生き方や昔からの知恵に興味を示さないことだ。」
わたしはこの言葉を聞いたとき、なんと声をかけたらいいのかわからず、言葉に詰まりました。先住民の人々が先祖代々大切にしてきたいのちのあり方、人生の意味、大地に根ざした生き方を次の世代に伝えるのに困っているのです。先住民の人々ですら困っているのに、日本に住むわたしたちは一体どうやって『ラウダート・シ』が教えるインテグラル・エコロジーを生き、次の世代に伝えればいいのでしょうか。
どのような世界を後世に残したいかと自問するとき、わたしたちはまず、その世界がどちらに向かい、どのような意味を帯び、どんな価値があるものなのかを考えます。
(回勅『ラウダート・シ』160)
わたしたちは、この『ラウダート・シ』の問いかけに対して応える言葉、生き方を持っているでしょうか。次の世代に良い環境や社会を残したいというとき、どれほど豊かな自然環境があるか、温暖化が抑えられているか、一人一人が大切にされる社会であるかということを考えることが多いかと思います。しかし、いのちの尊厳や、神と、自然と、人々とつながって調和のうちに生きることの意味や価値を深め、それを次の世代に積極的に教えていくことが欠けてしまっては、自然も社会もいずれ壊れていってしまうでしょう。マラウィの難民の皆さんと、インドネシアの先住民の皆さんは、このことをわたしに教えてくれました。日々、つながりの中で豊かにされるいのちの恵みに感謝し、次世代に伝えていけたらと願っています。

「ラウダート・シ」デスクは、2022年に日本カトリック司教協議会に設立された部門で、日本の教会が、教皇フランシスコの回勅『ラウダート・シ』で示されるインテグラル・エコロジーの歩みをともにするためのサポートを行っています。 ⇒ https://laudatosi.jp/
未来への警告~原発事故から13年を迎えて~
鴨下 美和
福島県いわき市からの避難者、二児の母 福島原発被害東京訴訟原告
2022年秋、私は福島県いわき市の共同墓地にいました。市内を見渡せる小高い山の中腹。紅葉した木々に囲まれた墓地の中央には、大きな白い石の十字架。周囲には花期を終えたワレモコウや、赤いサンキライの実。
やっと、訪れることができた懐かしい風景に、自然と涙が溢れました。しかしその足元の土には、今でも数千Bq/kgの放射性物質が含まれているのです。

原発事故当時は、その数十倍から数百倍の放射能汚染があったにもかかわらず、私たちの住んでいた街には、一度も避難指示が出されませんでした。私は、被曝を逃れるために子どもたちを連れて避難した、いわゆる自主避難者です。家があった場所は、爆発した原発から南に40km。事故当時、長男は8歳、次男は3歳。ひとときもじっとしていられないような、やんちゃ盛りの子どもたちに、泥や埃や雨を避けるような生活ができるわけもありません。彼らを放射線被曝から守るためには、無理をしてでも、避難するしかありませんでした。
かつて私と夫は、大学の研究室で放射性物質を扱う実験をしており、その危険性を知る立場にありました。ですから私たち夫婦にとって、自分の家や、子どもたちが遊ぶ場所に、大量の放射性物質が降り注いだこと、そしてそれが全く管理されないまま、風雨で移動し、子どもたちが素手で触れられるようになってしまったことは、心が壊れる程の恐怖で、被曝回避のための避難は必須でした。
しかし避難生活は困難を極めました。始めは私の実家のある横浜へ。次は夫の親が暮らす東京へ。親族とは言え、そう長く居候もできませんから、その後はアパートやホテルを転々とし、4月の末にやっと都内の避難所に入り、夏には古い官舎の避難住宅へ。賠償金の出ない私たちには、避難の継続のためのお金が必要なので、夫は4月には福島へ戻って業務を再開しました。週末には、車で250kmの道のりを飛ばして、私たちに会いに来てくれましたが、日曜の夜、別れのたびに、4歳の次男が布団にもぐって声を殺して泣くので、胸がつぶれる想いでした。
放射能は目に見えません。仮に測定機器があっても、放射線に関する知識と事故前の数値を知らなければ、その危険性はわかりません。国の避難指示が無かったこともあり、いわきは汚染などしていない、全く問題がない、と信じている周囲の人たちの中で、除染や被曝防護を訴え続けた夫は、罵声を浴び、差別を受け、次第に孤立し、頭のおかしい人と思われるようになっていきました。更に、身近な若者の突然死が二度続き、それに関わってしまったこともあって、夫は心身共に壊れていきました。会うたびに髪が減り、皮膚が年寄りのようになり、やがてろれつがまわらなくなりました。見るに見かねた私は、夫に仕事を辞めて一緒に暮らすことを提案し、事故から2年後に、夫も避難者となりました。
避難所や避難住宅では、うちの子に限らず、鼻血を出す子が多くいました。ただの鼻血ではありません。見たこともない程、酷い鼻血です。吹くような、吐くような勢いで鼻血が両鼻から出て、それが喉をまわって口からも出る。綿やティッシュでは追い付かず、洗面器やレジ袋で、流れ出る血を受ける子どもたち。それが30分経っても治まらない。深夜に若い母親から、どうやったら娘の鼻血を止められるのかと相談を受けたこともあります。結局、息子は手術で鼻血を止めました。テレビでは環境大臣までが、原発事故と鼻血の関係を否定しましたが、科学は現実に起きていたことを否定できるものではありません。実際に、岡山大・熊本学園大・広島大らのプロジェクトチームによる疫学的調査でも、当時の鼻血には有意差があることが認められています。
福島県の中通りで暮らす友人からは、息子の学校には紫斑病の子が多く、入院してしまった子もいる、と聞きました。いわき市では、急性心筋梗塞で亡くなる方が全国平均の二倍を超えていると報道されています。小児甲状腺がんを患った子どもたちが原告となった裁判も起きています。病気の原因は医師でもわからないと聞きますが、政府に選ばれた学者たちが、事故との因果関係を否定したとしても、現実に小児甲状腺がんに罹患している子どもたちが、福島県内だけで300人を超えていることや、チェルノブイリ事故後に増加した急性心筋梗塞死が、福島県で非常に増えていることは、動かしようのない事実です。
安全な被曝などありません。放射線の人体への影響は、確率的なものです。少しの追加被曝なら大丈夫なのではなく、低い確率ではあっても、確実に被害は起きています。でも、そのような被害が起こりうることを、政府は完全に無視してきました。
殆どの人は、13年前の原発事故によって、今も東日本の広い範囲が、100Bq/kg以上の汚染土壌となってしまっていることを知りません。事故前であれば、黄色いドラム缶に入れて、厳重に管理しなければならないレベルの汚染が、今も東北と関東に広がっているのに、その危険をきちんと伝えず、被曝させ放題。こんな無責任極まりないこの国に、原発を動かす資格などあるでしょうか。
今、私たちは、低線量被曝によって病気を発症しても、原因は不明のまま。おそらくは生活習慣のせいと片付けられます。そんな「運の悪い人」が、静かにじわじわと増えている。壊れた原発からばらまかれたセシウム137の半減期は30年。今ここにいる全ての人が亡くなったあとも、放射能は静かに生命を蝕み続けるのです。
「原発事故の避難者は、十分な賠償金をもらって、新しい家に住んで贅沢な暮らしをしている」というような、事実とは全く異なる風評によって、私たちは、いじめや差別に遭いました。息子は当時受けた過酷ないじめによって、今も心を病んでいます。仮に多額の賠償金がもらえていたとしても、それで奪われた人生を取り戻せるものでも無いのに、ただひとこと、「辛い」と言葉をもらす自由さえも奪われるのです。原発によって歪められたお金は、人に幸せをもたらすことはありません。
私たち被害者は、その属性を知られるだけで、差別に晒されます。被害を訴えれば、復興を妨げる風評加害者だと攻撃されます。ましてや顔と名前を出して訴訟など起こせば、隣人や親せき、時には家族からも攻撃され、それまでの生活を失います。それでも、被害者が声を上げるのは、あまりの不正義と理不尽があるから。そして同じ苦しみを持つ人がたくさんいるからです。黒い雨を浴びた方々や、小児甲状腺がんに罹患した子どもたちが裁判を起こしたのも、同じ苦しみにある人たちがいたから。私たち被害者の声は、未来への警告です。

冒頭に述べた共同墓地には、まだ墓石の無い草地があります。そこが、いつか私が眠る場所です。死んだら福島に帰れる。そう決めた日から、少しだけ心が楽になりました。帰りたい、という言葉をずっと封印してきた13年。生まれた場所ではないけれど、夫と結婚し、初めて家を建て、子どもたちが生まれ、たくさんの幸せを育んできた福島が、今でも私のふるさとです。
願わくは、私たちのような思いをする人が、二度と出ないように。
これ以上、原発によって国土が汚染され、人々の暮らしが歪められないように。
そして全ての原発事故被害者が相応しい賠償や救済を受け、差別に怯えることなく平和に暮らす未来が訪れますように。
祈りを込めて、これからも私は原発事故被害を訴え続けます。
「シノドス」 による2023-2024年の連続セミナーの刷新
原 敬子
援助修道会 / シノダるチーム
イエズス会社会司牧センターが開催する連続セミナーには長い歴史があります。このセミナーは、これまで、その時々に、社会や教会が直面する問題を取り上げ、私たちが人として、キリスト者としてどう考え、生きるべきかのヒントを提供してくれました。私もこの連続セミナーに参加し色々なことを学びましたし、また、講師としても、参加者の皆さんとともに考えを深めてまいりました。
2023年の連続セミナーのテーマは「『シノドス』 ともに歩む教会を目指して」でした。前半は、2021年から行われてきたシノドスの歩みを振り返りつつ、シノドスの霊的側面、社会的側面を概観しました。後半は、2022年10月に公布された「大陸ステージのための作業文書『あなたの天幕に場所を広く取りなさい』(イザヤ54.2)」で扱われたテーマを取り上げ、毎回、小グループでの分かち合いと全体会での発表を体験しました。

4月から12月までの9ヶ月間、11回のセッションすべてにおいて、小グループの分かち合いのためにファシリテーターが置かれました。ファシリテーターの存在によって、分かち合いが深まったと思います。これまでの連続セミナーの長い歴史の中で、これほどまで小グループでの分かち合いを中心に据えた連続セミナーがあったでしょうか。それは、主催者であるイエズス会社会司牧センターの方々が一番よくご存知だと思います。
2021年、シノドスは始まりました。2022年の「大陸ステージ文書」を経て、2023年7月には「世界代表司教会議 第16回通常総会『討議要綱』(INSTRUMENTUM LABORIS)」が公布されました。2023年後半の連続セミナーにおいて、私たちは「大陸ステージ文書(2022年)」と「討議要綱(2023年)」の両文書を一生懸命読みながら、今、世界の教会で何が問題になっているのかを、私たちの置かれている現場から考察したと思います。長い文書なので、読みきれない、追いついていかないという声も聞こえましたが、ほぼ、リアルタイムに歩んでいたと思います。
2023年10月、ローマで世界代表司教会議が円卓の分かち合い方式で行われていました。その様子を写真で見た時、世界代表司教会議がどこか雲の上で行われている会議なのではなく、まさに、私たちの小グループの経験と同じ地平で行われている会議なのだと理解しました。今、教会が直面している課題は私たちの課題なのだということを目の当たりにすることができたのです。しかし、考えてみれば当然のことです。2021年、世界の小教区宛に「意見聴取」が求められました。下から吸い上げられた課題が教会の課題なのです。教会の課題は私たちの現場からのものだったわけです。
私たちは人として、また、一人のキリスト者として、自分自身の意見を持ち、発言し、他者の意見に耳をしっかりと傾け、聴き取り、そして、他者から影響され、自分の意見も新たにすることができる。こうして、共同体の交わりのうちに、ともに聖霊の導きを探すことができる。私の属す教会共同体の課題は、世界の教会の課題にも通じます。ですから、2023年の連続セミナーは「霊における会話(『討議要綱』より)」という門を発見し、セミナーの刷新の始めの年だったのではないでしょうか。
ファシリテーター集団、名付けて「シノダるチーム(Team Synodal)」の面々は、ボネット神父様から2024年の連続セミナーでもファシリテーターを行うように言われました。嬉しいかぎりです! 2024年の連続セミナーのテーマは「シノドス的教会 ~皆が参加し、ともに歩んでみよう」です。2023年10月に公布された「第一会期『まとめ』報告書 宣教するシノドス的教会」の文書が根底にあります。さあ、2024年の連続セミナーでは、どんなことを発見することができるのでしょうか。
「旅路の里」の活動再開~「釜ヶ崎」というまちの変遷とメッセージ~
福田 紀子
「旅路の里」 スタッフ
「旅路の里」 活動再開
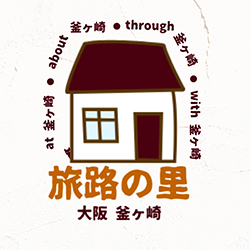
「旅路の里」は、コロナ禍等の時期の2年間以上の建て替え休業を経て、1982年の活動開始以来40年間の活動を行った同じ場所で、昨年9月に開所式を迎えました。今までに訪れた人が気づかずに通り過ぎてしまうほど様変わりした4階建ての建物は、1-2階を「旅路の里」、3-4階を「こどもの里 女子自立援助ホーム パレット」として活動していきます。
コロナ感染症はまだなくなったわけではありませんが、社会的にいろいろな規制が解けていった昨年後半から、高校を中心にした学校の研修事業が本格化しました。今の高校生にとっては中等教育(中学~高校)の時期にコロナ禍で様々な活動を制限され、特に通学範囲を超えた中長距離の移動を伴う研修などは「体験」することのできなかった環境を思えば、訪れる方々に貴重な時間であったと思います。
旅路の里は、「at:釜ヶ崎で、about:釜ヶ崎について、with:釜ヶ崎と共に、through:釜ヶ崎を通して」社会を学び、自分に気づき、これからを築こうとする施設です。訪問される方々の希望や状況に応じて、できるだけよい機会を提供できるように努めています。
成長と豊かさを支えた労働者のまちとして
「釜ヶ崎」という500㎡にも満たない地域が発信してきたテーマは、大きく2つの時期に分かれます。80年代までと90年代以降です。
1960年代から80年代までは、戦後復興を越えて高度成長、バブル経済の日本の豊かさを示す、都市基盤(電気、上下水道、一般道路、高速道路、新幹線、港湾、空港の整備)や学校、団地・マンションといった居住の場などの建築物の刷新、そのどの側面をとっても必ず必要とされる、広い意味での建設業現場の担い手の供給地でした。
まだ貧しさが見える形でまちの中に存在したこの時代に、一日単位での雇用、つまりその日が過ぎれば何の関係も保証もない雇用によって、さまざまな建設事業の現場は支えられてきました。公共事業にせよ、民間事業にせよ、1次受託者である大手建設会社等の社員は日常ではほとんど見当たらないのが現場の特徴です。2次・3次の現場責任者、監督者や専門職が主導し、立ち会うことがあっても、実際にものを運び、積み上げ、動かし、片づけている労働者は6次請けともいわれる日雇い労働者であることがほとんどです。
雇用関係が一日ということは、翌日に痛みの残ったケガや不調を訴えるところがない、ということを意味しています。「手配師」と呼ばれる仕事のあっせん者と、直接対面で仕事探しの交渉が行われ、その場でその日の仕事の有無が決まる「寄せ場」(労働者から見ると「寄り場」)が釜ヶ崎の役割でした。劣悪な労働環境や賃金不払いなどの労働問題、賃金の低さにつながる業界の構造的な問題、仕事に対する差別的な目線、人間らしく生活するという権利にはほど遠い居住環境、ケガや体の不調等で無収入になることと隣り合わせの働き方・暮らし方の問題が大きな課題でした。
当時2万人以上の仕事を求める人々がいた釜ヶ崎は、朝4時頃から続々と仕事を求める人々が集まり、バス(60年代にはトラックの荷台の場合も)に乗って出かけ、夕刻に戻ってくる(次の仕事のために寄せ場の近くで宿をとるため)のがルーティンでした。朝7時頃までにその日の仕事につけなければ、その日は失業、収入なしで定住場所もないため、公園や労働福祉センターなどの場所で休んだり、道路わきで昼間に飲酒する人々が車座になっていることも日常風景でした。

当時から旅路の里も加わっているキリスト教団体のネットワーク「釜ヶ崎キリスト教協友会」では、積極的にこの地域での「体験型研修」を行っていました。労働者たちがどこでどのように社会の変化に関与しているのか、産業構造の問題点がどこにどのように表れるのか、差別的な目線がどこに表れるのか、同時代的に「豊かさ」を求めて変化する社会を背景に、「日雇い建設労働者のまち」をどう見ていくのかを伝えるものでした。昼間から飲酒する人々が街頭にあふれるような異質さをどう受け止めていくのか。労働組合をはじめ、「しごと」「アルコール依存」「子ども」「高齢者」「傷病者」等に向けて、必要な「支援」に触れることから、自分たちの社会を知るリアルなインパクトに満ちたまちを背景に、多くの若者たちが学んでいきました。
高齢社会を生き抜くまちとして
このまちの様相の変化が顕著になったのが90年代です。これが今につながる2つ目の時代です。70年80年代から仕事をしてきた人々が50歳を越えた頃から、釜ヶ崎では「高齢化」が問題となりました。厳しい肉体労働の現場のリクルートでは、どんなに経験や技術があっても50代も半ばになると仕事の声がかからない、希望しても断られるという事態が起こっていました。まだまだ働くことができるのにという無念、これからのことを思う不安に、労働組合やキリスト教協友会は新たな団体を立ち上げ、行政に50代後半以上の人々も働くことのできる「しごと」と「居住(安心して寝ることのできる場所)」を求めていきました。
現在、炊き出しボランティアの受け入れ団体である「釜ヶ崎高齢日雇い労働者の仕事と生活を勝ち取る会(勝ち取る会)」が生まれたのも92年2月。翌年「釜ヶ崎就労・生活保障制度実現を目指す連絡会(反失連)」が立ち上がり、シェルター(安全に眠れる場所)や高齢者特別清掃事業(高齢になってもできる仕事)など、今の施策につながる様々な要求活動を行ってきました。
居住の保障も生活保護をはじめとする生活保障も、すでにある制度として受け止めがちですが、「釜ヶ崎」の歩みは、住民票もなく家族(保証人)もいない労働者たちが「だれでも安心して働き、暮らし続けられるまちをつくる」ために声を上げ、行動する不断の闘いから、一つひとつの合意や公的事業が生まれたことを示しています。
2000年代には日本全国で「非正規職」「貧困」の問題、特に若年男性の不安定雇用が顕著になり、社会保障の在り方も変わってきました。釜ヶ崎では、通年の緊急の宿泊施設としてのシェルターが整備されたのもこの時期からです。そして現在は、野宿者はかつての10分の1程度の人数になりました。とはいえ、30余名が地域内で野宿し、隣接する難波地域などでは厳しい寒さの中でも数十名の野宿者がいるという夜回り活動団体の報告があります。ただ、従前のような「建設業の構造的労働問題」「野宿者」「貧困」の理解だけでは、今の釜ヶ崎のもつメッセージを十分に受け取ることはできないと思います。
地域コミュニティとしての釜ヶ崎
現在、日本では全世帯数の中でも「単身世帯」が44%を超えています。地域の在り方として、釜ヶ崎は「高齢単身コミュニティ」の先端を行くものだともいえます。一人で、けれども地域の人々と生きていくために必要なことは何か、複層的な支援のネットワークも存在しています。それらのサービスの質もいろいろですが、高校生たちの感想の中にも「支援の重層性」に気づくものがあります。
このまちの様子をどのように読み取るのかも、リタラシー(読み解き)が必要です。体験ツアーの導入に行う「まちあるき」では、まちの歴史という時間的な変化を大きくとらえて伝えるようにしています。私たちがあたりまえに思っている「日常」がどのように生まれてきたのか。自分たちがより立っている社会の基盤といえるものがどの時期にどのように作られてきたのか。そのために必要なものを造ってきた「労働」があった背景を知り、高齢単身男性のまちで「人を大切にする」ための活動とその姿勢から何が学べるのか。
1970年に建てられた「あいりん総合センター」の建て替え問題を契機に、時代の影響を受けながらの「まちの変化」について、そこに住む人を大切にしながら議論する取り組みも連綿と続いています。行政との協働としてのまちづくりの会議には、労働組合、市民、医療や福祉の専門職、商店街や簡易宿所のオーナーたちそれぞれが参加し考え続けています。その模索する姿勢は他の地域にもまして「人と地域を大切にする」ことを中心に展開されています。
「労働」「まちづくり」「公的施策」「ジェンダー」、かつて仕事を求めて人々が集まったこのまちの取り組みの一つひとつは、訪れた自分自身の日常につながることでもあることを共に学んでいきたいと思います。高校生ばかりでなく、「旅路の里」が年齢にかかわらず様々な方と共に学ぶ場であるよう願っています。

