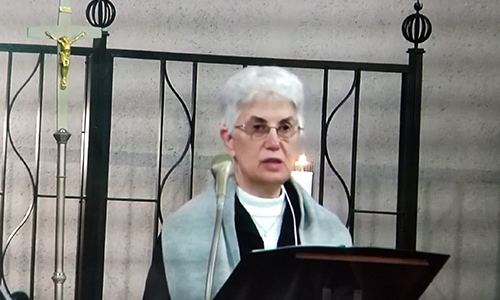「能登震災」 復興支援の体験を通して~司祭・修道者としての気づきと学び~
トマス 元田 勝哉 OFM
フランシスコ会司祭
はじめに
能登半島の震災から、はやいもので半年が経ちました。この半年をふり返り、気づいたことや感じたことを素直にお伝えしたいと思います。
震災発生から復興支援にたずさわる2月までの間、東京にいた私は、祈ってはいましたが、あまり真剣なものではありませんでした。しかし、神様はそんな私に、能登の復興支援にたずさわる恵みをくださいました。
その方法は、同い年である片岡義博神父様(名古屋教区/カリタスのとサポートセンター ベース長)の助けを求める声から始まりました。その声に、フランシスコ会日本管区と私が所属している瀬田修道院の兄弟たちが応え、私を能登に派遣してくれました。そのおかげで、震災から半年経った今も、継続して奉仕させていただいています。その体験と、その中での気づきや学びをお伝えし、皆様の祈りの一助、また能登の震災復興の呼びかけの一つとなれば幸いです。神様が、皆様の心の中にある宣教の火を燃え上がらせてくださいますように心から願い、祈っています。

奉仕の内容と学び
恥ずかしながら、私にとって被災地の支援というもの自体、初めて経験するものでした。しかし、神様は そんな私に「水支援」と「瓦礫撤去作業」という二つの大きな支援に従事する恵みを与えてくださいました。

まず一つ目の支援である「水支援」ですが、先に奉仕していたインセン神父様(神言会)と千葉道生さん(カリタス南三陸ベース長)からの引き継ぎを受けて、軽トラックに生活用水として使用する水を300ℓ積み、希望する方には飲料水と一緒に配布するという支援でした。この支援の中で学んだことは、断水という現実は想像以上に厳しいということです。少し考えたら分かることですが、単純に水は重たいですし、その水を運び続けることは決して楽ではありません。また、下水も使えなくなるため、トイレが使用できないという事態に見まわれます。かつ、地震で地中や屋内の見えない所にある配管がやられるため、復旧作業自体が難しく、復旧するまでに時間がかかります。
水支援の中で学んだもう一つのことは、奉仕する際に“自分自身の奉仕の基準をしっかり持つ”ということです。この基準がないと、困っている人たちのそれぞれに正しい意見を聞き過ぎ、自分自身が疲弊してしまうということが起こります。また、支援する水にも自分自身の体力にも限界があるため必要なのです。
ちなみに、水支援をしているときの私の基準は、“より厳しい状況にある人の所に水を届ける”というものでした。この当たり前のような基準によって私は守られたのです。言葉で書くと簡単なのですが、実際に被災した人たちの前に立ち、この基準に生きることは、本当に勇気がいることでした。なぜなら、断水して水を求めている方が多数いる場合、その中のより厳しい状況にある人以外の人たち全員に頭を下げて支援する水を減らすことをお願いしなければならないからです。困っている人に、より困っている人のために我慢をしてくださいと頼むだけのことなのですが、かなり神経を使う奉仕でした。けれども、何度も説明し、きちんと頼めば分かってもらえましたし、私は一貫してこの基準に従って水支援という奉仕をさせていただくことができましたので、感謝しかありません。
もう一つの奉仕の「瓦礫撤去作業」ですが、本当に神様の計らいなしには成しえなかった奉仕です。なぜかというと、七尾市社会福祉協議会(以下、社協)では、七尾市在住の人にしか運転ボランティアを募っていなかったからです。けれども、結論から述べますと、社協の責任者の方から特例で、この奉仕をさせてもらえることになりました。

| 聖木曜日の洗足式@七尾教会 |
まず、片岡神父様と千葉さんと私の3人で、社協の責任者の方と話をしました。その話の中で分かったことは、七尾市で既に行っていたカリタスの活動「じんのびカフェ(当時、じんのび食堂)」のことを、責任者の方が直接目にしていて、カリタスの活動を知っていてくださったのです。カリタスの奉仕者たちは、瓦礫撤去作業に結び付けるために奉仕していたわけではありません。しかし、この奉仕者たちの献身が知らないうちに信頼を勝ち取っていて、全く予想していなかった瓦礫撤去作業の運転ボランティアという奉仕へとつながったのです。この神様の計らいによって、私たちは瓦礫撤去作業を任されましたので、個人名ではなく、カリタスの名前で奉仕し続けました。
このことは私に、カリタスというカトリックの団体が、公に認められている団体であることの本当の意味を理解させてくれました。すなわち、公の信頼を得ている背景には、奉仕者たちの献身があるということです。私たちの奉仕が、神様によってより善いものへと変えられるように願ってやみません。
祈りとミサの大切さ
神様がこの復興支援の中で与えてくださった恵みの中で最高の恵みは、奉仕の前にミサを捧げさせていただいたことです。このことによって、ただのボランティアでなく、キリストのように自分自身を捧げる奉仕へと高めてくださったということを私は実感しています。また、多くの司祭・修道者、ならびに信者さんや志の高い未信者の方々と共に、祈りから始められたことを本当に嬉しく思っていますし、感謝しています。
特に、同年代である司祭3人(私、片岡神父さん、イエズス会の森晃太郎神父さん)で聖週間のミサをお捧げすることができたことは、私の一生の宝物となっています。そして、この関わりは私が東京に戻ってからも続いており、何度か共に能登での体験の報告会をしました。その中で不思議に思うことは、同じ体験をしたにもかかわらず、全く違う視点での話が聴けるということです。互いが互いの意見を尊重しながら、まだ体験していない人々にお伝えする時、神様からいただいた絆のようなものをより身近に感じさせていただきましたし、今も実感しています。そして、祈りとミサこそが奉仕の原点であり、頂点であることをも再確認させていただきました。
最後に
私が今回、自分自身の体験を話す中で意識していたことは、神様が主語(主役)になるということです。自分自身の体験を語る時、どうしても“自分が、自分が”となりやすいですし、その傾向に負けやすい自分の弱さも知っています。けれども、私たちの内に働いておられる神様が、皆様の体験してきたこと(人生の一場面一場面)を照らし、善き方向へと導いてくださいますように。
神様が、神の国の実現のために私たち一人一人を必要としてくださっていることを実感できますように。また、神様が、今も尚、災害によって苦しむ多くの人たちと共に居てくださり、希望を与えてくださいますように。特に、能登地震にて被災された人たちのことを心に留め、助けてくださいますように、共に祈り求めてまいりましょう。
大原猛神父インタビュー (前編) 「戦争体験と戦後79年」
大原 猛 (1940年生)
東京教区司祭
来年には、日本は「戦後」80年を迎える。戦後が長くなるということは、それだけ「戦争」のことを身をもって語れる世代がいなくなっていくことを意味する。そうした人々の声を聴き、記録し、語り継ぐことを目指して、手始めに、東京教区の大原猛神父(83歳)へのインタビューを行った。聞き取りは 7月14日、ペトロの家で、5時間近くにわたって行われた。予想以上に膨大な――それでも長い人生の記憶に比べればはるかに短い――語りの一端を、前後編に分けて紹介したい(後編は次号に掲載)。なお、文字化に際して、なるべく大原神父の語りの口調を保つように心がけ、全体の再構成を含めて適宜編集を加えた。
(聞き手: 柳川)

人生の最初の記憶 ~空襲体験と戦争トラウマ~
僕が生まれたのは1940年(昭和15年)ですね。僕の生まれた翌年に太平洋戦争が始まって、それはもちろん記憶にあるわけじゃなくて。非常に鮮明に覚えているのは1945年、戦争の終わった年ですよね。その7月6日の夜のことで、甲府の爆撃※から始まったんです。
3月に東京大空襲があって、その前何年かわからないんですが、前年(1944年)か45年の初めに母の故郷だった山梨県の甲府に疎開をすることになって。父は東京に残って、母と私の姉と兄と、あとおばさんなんかで疎開したんですね。
記憶がそこから始まるのは、母が私を揺り起こして、起きたんですね。そしたら目に浮かんだのは灯火管制で。電球に黒い布を被せて光が外に漏れないようにしているのが最初に目に入った。それからサイレンの音が聞こえていたんですよ。空襲が起こるということで起こされて、寝巻きのまま外に促されて出たんだけど、母とおばさんは家財をなんとかするっていうことで残ったんですね。母とどこで落ち合うかっていうことを約束して、姉と兄に連れられて、外に出て。
すごく鮮明に残っているのは、外に出た時、もちろん夜中ですよね。ちょうど50mぐらい前の家に焼夷弾が落ちたんですよ。ボンとぶつかったら、うわーっとすごい勢いで燃えていくんですね。それをアメリカ軍がどんどん落としていったわけですよ。すぐに火の海に包まれて、あまりの熱さに、小川に全員飛び込んで、防空頭巾をとにかく濡らして。僕は着の身着のままの寝巻き1枚だったから、防空頭巾を被って、そこで熱さをこらえて。どっかのおばさんが熱心にお経をあげていて、緊迫した感じで。
水をかけてまた立ち上がって、火の中をずっと歩いたんです。すごい猛火だったのを覚えています。大きなお屋敷の、虎の絵が描かれた屏風が燃えているのが目に焼きついて、今でもはっきり映像として残っている。お屋敷やいろんな家がメラメラ燃えている。その炎で空がすごく真っ赤になっていく。
田んぼの阿道みたいなところを通っていて、僕の数m先、左側に焼夷弾が落ちた。地面に落っこっていたらもちろん焼け死んでいただろうと思うんだけど、田んぼの水の中に落っこったので、すごく熱せられた泥水が足にかかった。すごく熱かったんですが、そしたら兄が横にあった川の中に僕を抱きかかえて飛び込んでくれて。そして少しは冷やすっていうか、でも後ずっと傷になって残ったんですがね。ずっと足の下の方まで、左足に傷が残ったんですけども。よく覚えてないんですが、もちろん、当然泣いていただろうし、怖くて怖くて。火の中を通る時の怖さは恐ろしかったですね。
それでやっと落ち合う場所に行って、母たちは無事に帰ってくるかどうかっていうことがすごく心配で。姉と兄と私とずっと不安の中にいたんですね。そこへ母とおばさんがやっとたどりついてきて、母が子どもたちを抱いて気を失ったっていうのを覚えているんですね。戦争っていうのは、それがもうなんかトラウマになっていて。なんていうかな、サイレンが鳴るとね、ものすごく怖くて怖くて。工場のサイレンとかいろんなものが鳴ると、いつも戦争の時の爆撃のことを思い出して怖かったんですね。
その年は3月10日に東京大空襲があって。その前に敵機が飛来していたんで、だんだん疎開するようになっていたけど、その日に10万人ぐらい亡くなっているわけですよ、一晩で。殺人が行われたって思っているんですが。それから甲府で七夕攻撃っていう。甲府の市の真ん中に落とすんじゃなくて、端から落としてくるんですよ。そして全部燃やして中で焼き殺すっていうやり方をした。甲府には軍事工場があったんですね。そこを狙ったっていうのもあるけども。いろんな都市の中心地は、もう米軍が爆弾を落としていって。
その年、4月には沖縄戦の上陸があって、首里に守備隊の本部のあったのを移動して南部に行ったから、南部に逃げていた住民が大量に亡くなっていった。そして6月23日、沖縄の組織的な戦闘が終わった「慰霊の日」って言っているけれども、結局沖縄が日本の「捨て石」になって、ものすごくたくさんの住民が9万何千人も亡くなっているわけですよね。
日本軍は、僕が生まれる前から中国大陸に侵略した。韓国・朝鮮とか中国に対する侵略で、南京大虐殺もあっただろうし、それから三光作戦というたくさんの人たちを殺すやり方があったと思うんですよね。東南アジアに侵略していく日本の軍国主義がひどくて。「従軍慰安婦」を特に朝鮮人に強制的にやらせたり、朝鮮からの徴用で炭鉱とかいろんなところで働かせたり、戦争にも駆り出した。
本当に日本軍がどんなひどいことをしたかっていうことを前提にしながら話すんですが。結局アメリカ軍の3月の東京大空襲とか4月から6月の沖縄戦。7月に僕らが経験した甲府爆撃。それから8月6日に原爆投下で広島で14万人ぐらいの人が亡くなって、8月9日の長崎では7万人。そうするとよく考えてみたら殺戮が一般の市民に対して行われたっていうことですね。日本軍がどんなひどいことをしたかっていうことをもちろん頭に置きながら、アメリカ軍も殺人行為をした。僕は、戦争はやっぱり殺人だって思うし、決して許されていいものではないと思うんですね。
浪人時代の悩み ~戦争と死刑~
高校受験に失敗して1年浪人したんですが、その頃によく考えていたことは、死刑の問題。死刑制度は、僕はあれも殺人行為だし、どんな理由にせよ人が人を殺すということは許されていいわけはない。刑罰ならね、長期的に投獄するとかはあっていいと思う。だから死刑というものに対しては、僕は認められなかったんですね。それから同時に戦争。もう1つはナチが非常にひどい残虐行為をしていた時に、ローマ教皇は何も言わなかったんですね。その時共産主義だけを警戒していて、ナチに対する戦争反対を言わなかったわけですよね。
僕は高校生ぐらいに、なぜ教会は戦争を認めるのかっていうことを、絶対に認められないという風に思っていて。それは子どもの体験がベースにあって、あの恐ろしさをもう二度と体験したくないし、戦争っていうものが許せないという風に思っていた。ところが教会はどっちかっていうと死刑も肯定していた。
確かにロシアとウクライナはロシアの責任が大きい。あの侵略する行為と、それからイスラエルがガザを攻撃することとか。ミャンマーでもそうだけれども軍部が少数民族を攻撃し、それに対する戦いがある。正当防衛的なところをある程度認めるにしても、でも死ぬのは一般の人たちであって、殺人はいかなる理由があるにせよ認められない。特に原爆とかそういう一瞬のうちに何万も殺すような行為は絶対に許されていいわけじゃない。
それが疑問に思っているうちに、その当時、神父に訊いても納得いくような答えがなくって。その時にイギリスがちょうど死刑制度を中止したっていうニュースを聞いて、ああこれが本当なんだって、僕はすーっと思った。教会はなぜ正式に死刑反対をしないのか、すごく大きな疑問だった。そんな背景があったり、自分の人生をどう生きるかっていうことから、神学校に勧められることもあって入ったんですけどね。
神学校入学と反戦デモ
18歳か19歳で神学校に入ったんだけど、ちょうどその頃は高度経済成長がわーって昇って1960年代、「所得倍増計画」が池田隼人首相から出て。その前に安保闘争があって、そっと国会議事堂の方に行ってデモ隊にちょっと入ったりとか。
社会的な意識っていうものを強く持ったのは、やっぱり子どもの頃の戦争体験であって。あと、父はもちろん党員ではないけれど、どちらかというと社会党を支持していたっていうか。だから社会的な目っていうのはやっぱり育てられたのかな。家庭は母なんかカトリックになっていたんで、そういう父の意識とは無関係な形で、どっちかっていうと保守的な教会の考え方を受け入れたっていうか。その中で揺れ動いたのが 1つの体験だったんですね。
僕は神父になったばっかりで、神学校でも守られている形で、社会に出ていくってことはほとんどなくて。67年に神父になって、68年に教会に赴任して、その時に学生運動が。東大闘争なんかもあったし、秋田明大の日大は火がついて学園闘争が始まる。そして「べ平連(ベトナムに平和を!市民連合)」も小田実やなんかで組織されて。僕はちょうどその頃に教会にいたんですが、すごく揺れ動いたんですよ。
戦争とか、あるいは保守的な教会の考え方に1つのきっかけを作ったのはヨハネ23世の『地上に平和を』という回勅で。あれまで教会の信徒に向けていたものが、共産主義でも何でもいろんな国の元首にも宛ててあの本を出しているんですね。
プロテスタントの神学者がいて、教会と共産主義との間の『対話の価値』っていう本がサイマル出版会から出されたんですよね。それを読んですごく悩んでいたんですが、1人で行くしかないと思って、時間を見つけては、ベ平連のデモに参加していた。いい経験したんだけど。催涙弾をバンバン打ち込まれたり、そういう中で若者たちがものすごく一生懸命、平和のことを言っていたんですね。とにかく「ベトナムに平和を!」って、戦争の問題をすごく取り上げていた。
沖縄への旅と多くの出会い
その頃によく歌われていたのが沖縄の返還の歌ですね。「固き土を破りて 民族の怒りに燃える島」「沖縄を返せ 沖縄を返せ」っていう歌があって、それをみんなで大きな声で歌って。72年に沖縄が返還されて、それから10年ぐらい経って沖縄に行くようになったんですね。(イエズス会司祭の)山田経三さんがたまたま沖縄に行ってきたっていうから、僕は向こうのフランシスコ修道院のシスターを紹介してもらって、JOC(カトリック青年労働者連盟、詳細は次号)の青年たちと一緒に沖縄に行ったんですね。
シスターにもいろんな人を紹介してもらって。米兵によって慰安婦みたいになった、本当に心が壊れていく女性たちのシェルターとして与那原の修道院がやっていたんです。そこに高里鈴代さんというプロテスタントの女性がいて、その人のお話を聞いてすごく衝撃を受けて。それから沖縄の戦跡を巡ったり基地を見に行ったり。読谷村に行って、村起しの中で民族の陶芸をやる陶芸家に会ったり。沖縄の民主主義を中心にやっていたのは学校の職員組合だったので、その中心的な方にもお会いして。そのうちに伊江島に行って阿波根昌鴻さんに会って、大きな変化があった。僕にとっては、すごく大きな出会いだったね。戦い方にもこういう戦いがあるんだっていうことをすごく理解して、それで沖縄が本当に身近なものになった。
今、どんどん自衛隊が進出していって、ミサイル基地とかいろんなものを作りながらやっている。米軍と日本がものすごく緊密に繋がって、「南西諸島の危機」っていうことを言いながら軍備をどんどんどんどん強くしている。沖縄が今でも「捨て石」のような状況になっている。だから今、もうこういうところ(ペトロの家)にしかいられなくて、あまり社会との繋がりが薄くなっていて残念なんですが、心ではいつでもね、意識としては、なるべく社会の人たちと繋がりを持っていこうという風に思っているし。
両親の影響と社会への関心
僕の出発点はやっぱり子どもの戦争体験が恐ろしい恐怖の体験だった。燃え盛る火の中を逃げてきて、母と会えたことは本当に喜んだし。その後しばらく、小学校に上がる寸前ぐらいまでを甲府で過ごして、それでこっち(東京)に帰ってきて。父もあの戦火の中、ひどい東京大空襲の中生き残っていて。それで父と再会できて。だからそれが戦争体験。そんなちっちゃな体験しかない。
それ以外の記憶として残っているのは、戦争が終わった後に、お寺の梅の木に登って梅を取って怒られて捕まったとか、人のうちの柿を盗って食べて赤痢になったとか。貧しかったからみんな。
まあ幼少期は普通にワンパクで遊んでいて。それから高校生ぐらいになってくるとだんだん文学が好きでよく読むようになって。どちらかというと私小説が好みで読んでいたんですが。それからドストエフスキーとかそういう人たちの本を読むように。だから感性がどんどんそういう本を通しながら。父の影響もあって社会的なものに対する意識も。
それから教会が2つのこと、死刑制度と戦争に対する反対はしなかった。むしろ「正戦」というような表現で肯定していたような形があって。でもやっぱり理解できなかったのが、ローマ教皇がなぜあの時に批判しなかったのか。もし批判したらたくさんの犠牲者が出たんだろうっていう気がするんだけど、でも、どうして批判しなかったのか、それがずっと分かんなくて。神学生時代にロルフ・ホーホフートっていう作家が『神の代理人』という、ピオ12世のことや戦争の問題について書いた本を読んだんですね。
そして、関心があったのは、労働司祭とか。『聖人 地獄に行く』っていう本があったんだよね、フランスの労働司祭の問題。子どもの頃から意識はずっと持ち続けただろうと思う。ただ、神学校の守られた生活の中ではあまり。「どうして社会との関わりを持たないんですか?」って院長に言うと、「あなたは批判的です。問題です」って言われて、いつもチェックされていて、「やめた方がいいですよ」っていう風に言われ続けた。
だけどもいつも、教会が社会と関わらない、そして神学生が閉じ込められた社会の中にいるっていうことが理解できなかったね。もっと人々の中に生きて養成すればいいじゃないか。神父を養成するんだったらそういう風な2つの心、人間的な成長の分とそれから社会の中で福音宣教をするんだとすれば、そういう状況の中でもっと僕らの中に社会の意識を芽生えるような形でやるべきだっていう風に思っていて。神学生やめようかなと思う時もあったんですけど。
平和への想い
原点といえば子どもの体験、それから家庭の中にあった1つひとつの出来事が積み重なっていったんじゃないかな。だからもう戦争は絶対に許せないし。でやっぱり、あまりアメリカ批判したくなくても、結局日本も殺人行為したけど、アメリカ軍もね、殺人行為をしたんですよ。本当に何十万の市民を殺したんですよ、焼き殺したり原爆で殺したり。日本が早く戦争を終わらせるために仕方なかったんだっていう言い方しているけど、それは理由にならないですよね。原爆2発で20何万人を殺しちゃうんですからね。こんな馬鹿な話はない。本当にゆるせることじゃないですよね。
沖縄も結局、牛島中将が「最後まで戦え」って言った軍国主義がたくさんの沖縄の人たちを戦火に巻き込んでいった。もう戦争に負けるのは分かっていて、それでも「最後の一兵卒まで戦って死ね」っていう言い方をする。そして沖縄に行ったらよく分かるんだけど、日本軍がどれだけ住民を外に追い出したり殺したりしたかっていうことをね。もう本当に戦争っていうのは愚かで、本当に意味がない殺人行為なんだっていう風に思う。
来年が戦後80年だけど、僕はずっとそういう戦争の中に生きてきたんだよね。僕の姉の名前は「國永」、国が永らえるっていう。戦時っていうか、日本が中国なんか侵略していく過程の中にあって、父がつけた名前だと。最初の長男が亡くなって、それで2番目の子どもは健康な子どもでありますようにって「康男」っていう名前がつけられて。僕は戦争がもうだんだんきな臭くなってきた頃だったんで、「猛」って名前をつけたんです、猛獣の猛で。だからそういう勇ましく強い名前、戦争の影響をすごく受けている名前ですよ。平和の時だったら僕、違う名前をつけられただろうと思うんですよね。僕が生まれたときからずっと。だから戦後80年。
1945年に終戦、戦争が終わって。その年に僕もいろんな経験をしているんですね。後でよくわかったのは、戦争の終わった年は沖縄戦とか原爆だとか東京大空襲とか様々なことがあった年で、そういうことを決して忘れてはいけない。日本が侵略していったことも忘れてはならない。南京大虐殺は嘘だっていう政治家たちの発言とかね。戦争でひどいことをしてきたことを忘れてはいけない。
韓国に行った時ね、池学淳司教さんにお会いしたんですね。司教さんが「私は決して日本がやったことを忘れません。やってきたことを私は忘れません。ただ、私たちの未来はそういう反省の上に立って、新しい未来を共に築き上げていくことなんだ。ただ、その現実にしっかり身を置いておかなければだめですよ」と言われたことを今でもよく覚えている。彼は徹底して戦ったでしょう? そういうことにすごく影響を受けた。
(次号、後編に続く)
※甲府空襲について
1945年7月6日23時47分~7日1時48分にかけて、甲府に米軍のB-29爆撃機131機が飛来して爆撃を行った。 甲府市によれば、市街地の約74%、18,094戸が焼き尽くされ、1,127名が死亡したとされる。
JCAP移住者・難民ネットワークの5カ年行動計画 (2023-2027)
中井 淳 SJ
JCAP移住者・難民ネットワーク コーディネーター

イエズス会アジア太平洋地域協議会(JCAP)の移住者・難民ネットワーク(MRN)の5カ年計画について紹介させていただきます。このネットワークは、アジア太平洋地域のイエズス会のJRS(イエズス会難民サービス)や移住者支援の施設で働く者たち、またそこに連なりながら協働する仲間たちによって構成されるネットワークです。
コーディネーターが事実上不在で動きのなかったネットワークの仲間たちが、2022年の3月にオンラインで再び繋がり直し、現代において私たちが望まれている使命・活動は何なのかを分かち合い、実現していきたいと思う具体的な事柄を挙げていきました。それらは4つのカテゴリーに分けられ、それに合わせた4つのチームが作られることになりました。
- ホスピタリティと和解の文化を作っていくために外部発信をしていくチーム
- メンバーが移住者・難民たちによりよく寄り添っていくために、ネットワーク内のキャパシティ・ビルディングをしていくチーム
- 強制移動を余儀なくされている根本的要因、問題を人々に知らせていくアドボカシーのチーム
- ネットワークの仲間たちがそれぞれ持っている資源を共有し、協力していくためのプラットフォームを作っていくチーム
2023年3月に東京で行われた会議で、より詳細にわたる5カ年計画が作られました。2024年3月に台北において行われた会議で、それを要約して、人々にわかりやすく伝えられる形にすることができました。それがここで紹介させていただくものです。
台北では、どうしても皆で共有したかった時間を取ることができました。それは、神が私たちと共に見たいと願っている夢を黙想し、分かち合うという、私たちの活動の霊的土台を作っていく時間です。神は、今のこの世界をどのようなまなざしで見つめ、私たちに何を望んでいるのか。私たちのアイデンティティ(存在)と活動が統合されるために何を大切にしなければならないのかを、沈黙の時間をとって一人ひとりが祈りました。そして、二人ずつのペアで散歩をしながら分かち合ったのち、4つのグループに分かれて祈りの内容を絵に描いて表現しました。発表されたものを私が一つの文章にまとめ、5カ年計画に添えました。「ネットワークの活動を支える霊的な土台」がそれです。
皆さんにお願いしたいのは、特にミャンマーのために何かアクションを起こすということです。私たちは会議の中で、ミャンマーで家を追われて避難している人々に最前線で命をかけながら寄り添っている仲間の声を聞き、アジアのネットワークとして、ミャンマーの人々と共に立つことを選びました。3年前に軍事クーデターが起き、現在、難民・国内避難民となっている人が200万人以上いると言われています。
私たちは、共同でフォーラムを行ってきました。また、それぞれの現場でミャンマーに繋がる活動をしています。関東では社会司牧センターやアルペなんみんセンターがイベントを行いながら、人々にこの問題を知ってもらい、アクションを起こしています。私が働く下関のロクスひよりやま(旧:下関労働教育センター)でも、下関の子ども食堂とミャンマーからタイに逃れている難民の子どもたちを繋げ、支援する活動が始まります。
教皇フランシスコも強調しているのですが、ネットワークを作り、人々と繋がることの大切さ、かけがえのなさを、私はこのネットワークに関わりながら体験してきました。互いに情報を共有し、励まし合い、互いに顔のわかる絆を深めていくならば、助けられる命があるということを体験してきました。ぜひ、読者の皆さまにも、特にはミャンマーのために、また移住者・難民問題に関して何かしらのアクションを起こすことと、このネットワークに繋がりながらできることを探していっていただけたらと願っています。
◆◇◆◇◆◇◆
JCAP MRN5カ年行動計画 (2023-2027)
1.序論
我々、JCAP移住者・難民ネットワーク(JCAP MRN)のメンバーは、移住者・難民・国内避難民(MRIDP)への支援におけるネットワークの中核となる優先事項を解決するために、4つのテーマ別サブチームを編成し、5カ年計画を実施することを提案する。
これを実現するため、年4回のオンライン会議と年 1回の現地会議を開催し、アジア太平洋地域全体の協働とリソースの共有を拡大し、深化させる予定である。
我々のビジョンは、移住者、難民、国内避難民と共に、そして彼らのために、公正で安全かつ包摂的な世界を築くことである。以下に今後5年間(2023-2027)のテーマ別サブチームとその重点領域、および提案された計画と行動を示す。
2.ビジョンとミッション
我々のビジョンは、移住者、難民、国内避難民と共に、そして彼らのために、公正で安全かつ包括的な世界を築くことである。以下に4つのテーマ別サブチームを示す。
A. リソースを共有し、社会および地域社会におけるホスピタリティと和解の文化を促進するための共同活動を探求する
アジア太平洋地域は、長引くパンデミックにより悪化した紛争と分断に見舞われた。移住者や難民は国境で押し戻され、必要な支援を拒否され、外国人嫌悪や悪意ある言説によって傷つけられている。移住者・難民ネットワーク(MRN)は、異邦人へのホスピタリティの文化と疎外された人々との和解を促進する(PCHR)。我々は、地域社会への証しにおいて成長すると共に、人々の心を変えることができるよう祈る。
B. 移動を余儀なくされた脆弱な人々が安全、安心、そして適切な生計を得られるよう、各センターの能力を向上させるための協働
UNHCRのデータによれば、アジア太平洋地域には、約920万人の難民、亡命希望者、国内避難民、無国籍者が存在している。この地域は世界で最も多くの無国籍者を抱えており、特にミャンマーでは近年、この強制的な離散と脆弱性が顕著に現れている。
この地域では、2019年には世界で最も多くの移住者が存在し、その数は1億700万人に達した。東南アジアからの移住者においては2,360万人が出身国外に住んでおり、2020年にはフィリピンが最も多くの移住者を抱えている。
移住者・難民ネットワークの使命において、これらの人々が基本的なサービス、人権、教育、法的支援、生計手段など、生存と安全確保に不可欠な支援へのアクセスから排除されてしまうことに対処することが急務である。したがって、次のような問いが生じる。「JCAP 移住者・難民ネットワークは、移動を余儀なくされた社会的に弱い立場にある人々が、安全、安心、そして適切な生計を得られるよう、各センターがどのように支援すれば良いのだろうか?」
C. 移住者・難民ネットワークとして社会的弱者の権利擁護(アドボカシー)を行い、強制移住を防ぐための根本原因に取り組む
アドボカシーは、公正で安全かつ包摂的な世界を築くための我々の使命の不可欠な部分である。コロナ禍によるパンデミックは、不法な拘留や非正規入国者の強制送還、国の保健政策や支援政策における排除など、社会的弱者に対する政策や計画的支援の欠如のために、深刻な影響を露呈した。
紛争と気候変動は、当地域における強制移動の強力な要因であり、脆弱性の増大に繋がっている。これは特にミャンマーにおいて顕著であり、現況は切迫している。我々の即時の対応が求められている。
D. 移住者・難民への奉仕、共同識別、相互扶助および協働的な行動のために、移住者・難民ネットワークメンバーの能力を向上させる
移住者・難民ネットワークメンバーは、多様なリソースと専門知識を有している。我々は、メンバーがより直接的かつ頻繁に互いにアクセスできるようにし、移住者・難民への奉仕をより良く支援できるようにする。オンライン会議によって、互いに連携するための多くの新しい機会が与えられることを理解している。
3.戦略的優先事項
*現地およびオンライン会議やサブチームの活動を通じ、JCAP MRNの再活性化と強化
*ミャンマーのための社会的弱者の権利擁護(アドボカシー)と協働
4.サブチームの具体的な行動計画
サブチームA: 社会と地域社会におけるホスピタリティと和解の文化を促進するためのネットワークとして、リソースを共有し、共同行動を模索する
1.「世界難民移住移動者の日」の教皇メッセージにおける内省と共に年次プロモーションを行う。
2.インスタグラムアカウント「JCP MRN」を作成し、運用する。ハッシュタグは、#befriendtheforeignerworkerと#welcomethestranger。
3.ホスピタリティの文化と和解の促進(PCHR)をテーマに、2025年JCAP MRNの年次集会を開催する。
4.イエズス会学校および提携校において、考案されたプログラムを通してPCHRの啓発活動を行う。
5.この「思いやりの文化」を、篤志家と奉仕協働者の間で推進する。募金活動や企業の社会的責任(CSR)の文化と結びつける。同時に、MRIDPのニーズや状況を伝え、認識を高める。これは各地域の状況に応じ、各地域レベルでアプローチする必要がある。
サブチームB: 移住者・難民ネットワークとして協働し、移動を余儀なくされた脆弱な人々が安全、安心、適切な生計を得られるよう、各移住者・難民センターの能力を向上させる
(既存のリソース、人脈、積極的な参加者を結集・連携させ、ネットワークを拡大する)
1.人道支援およびその他の支援のために、JCAPに参加する難民送出国が資金を受け取ることを容易にするオンラインプラットフォームを作成する。
2.移住者および難民の受入国における人道支援を評価し、あらゆるレベルの教育、住居、医療など、利用可能なすべてのリソースのリストを作成し、ニーズに応じて定期的に更新する。
3.アテネオ・デ・マニラ大学のロヨラ神学部と協力し、JCAPの司牧者のための教育・養成プログラムを確立する。
4.JCAPの送出国と受入国の司牧従事者および受益者との連携を調整する。例えば、受入国での奉仕に関心のある送出国の司牧従事者の育成、移住者・難民センターおよび奉仕における能力向上と同伴指導、JCAPでのイエズス会員養成プログラムなど。
サブチームC: 分断の架け橋となる社会的弱者の権利擁護(アドボカシー); 移住者・難民ネットワークとして社会的弱者の権利擁護を行い、強制移住を防ぐための根本原因に取り組む
1.我々は、緊急対応のためのアドボカシーとして、次のとおりミャンマーの架け橋となる。 a)JCAP声明に向けた重要なメッセージを策定:「平和と尊厳」、「人道援助へのアクセス」、「包括的ガバナンス」のための現在のASEANコンセンサスに関する首脳や特使との関わりについてのアドボカシー。 b) ミャンマー・フォーラムの開催。 c) 異なる信仰に基盤を持つ組織との連携と、より大きなアドボカシー運動の一翼を担う。
2.我々は、長期的なアドボカシーの取り組みと問題意識の向上により、人々の分断の架け橋となる。それは、(a) JCAPの旗艦プロジェクトである貧困問題に対するアドボカシー活動への支援、(b) JCAP管轄下での移住労働者、亡命希望者、難民、人身取引、その他の強制移住の問題に関するアドボカシー活動への支援、によって行われる。
3. 長期的なアドボカシーとして、JCAPの旗艦プロジェクトである「環境危機による移住」のアドボカシー活動を支援することで、「人」と「創造」の分断を埋める。
サブチームD: 移住者・難民のための奉仕、共同識別、相互扶助および協働的な行動のため、移住者・難民ネットワークメンバーの能力を向上させる
1. 少なくとも年に1回、移住者・難民ネットワークメンバーが基幹グループと協働し、適切なテーマやトピックを設定する。自らが置かれている状況やミッションの現状をアップデートし、内省と祈りの時間を持つために、定期的なオンラインミーティング(理想的には3か月に1回)と現地ミーティングを奨励する。
2. FacebookやInstagramのページ、WhatsApp、グループメールなど既存のオンラインプラットフォームやJCAPコミュニケーションチームと連携し、移住者・難民の体験談の共有やミャンマー情勢に関する最新情報を提供することで、移住者・難民ネットワークメンバーの士気を高める(少なくとも月1回)。
3. WhatsAppグループにオンラインヘルプデスクを統合し、移住者・難民ネットワークメンバーが助けを求めたり、アドバイスを提供したり、移住者・難民ネットワーク内の適切なリソースを紹介したりできるようにする。
4. ネットワークメンバーの関心、言語能力などの専門性を含む既存の情報リソースを整理し、メンバー間で情報を共有するためのデジタル・ライブラリーの利用を進める。
5. イグナチオの霊性を我々の進め方に根付かせる。
6. 各機関の研修情報を共有し、移住者・難民ネットワークメンバー、移住者・難民間の相互学習などの能力開発を行う。
5. 移住者・難民ネットワークの基幹グループと共通行動
基幹グループは、すべてのサブチームとの橋渡しをするコーディネーターと中核メンバーで構成され、連携が円滑に行われるようサポートする。各サブチームの領域は他のサブチームと深い繋がりがあるため、計画や行動が重なることもある。そのため、中核メンバーは、サブチームが効果的かつ同調的に活動するための進行役として機能する。
我々はJCAPコミュニケーションズと協働し、移住者・難民に関する情報について、JCAPニュース(jcapsj.org)をメンバー間で共有するツールとして活用する。ニュースレター内に移住・強制移住に関する全拠点・各地域の主なニュースやニーズ(資金調達の要望も含む)を共有できる専用スペースを設けることで、関連情報を社会に発信する。
結論
我々JCAP移住者・難民ネットワーク(JCAP MRN)のメンバーは、2022年3月以来、オンラインミーティングや対話を通し、特に2023年3月に東京で開催された会合での対話を通して練り上げ、実践してきた本計画を実現するために尽力したいと考えている。本計画をJCAPメンバーの皆に広く周知するため、この5カ年計画(2023年~2027年)の概要編をここに提出する。
JCAP移住者・難民ネットワーク
2024年3月6日 台北にて
「ネットワークの活動を支える霊的な土台として」
De Status Societatis(DSS)に基づくネットワークミーティング台北での黙想と分かち合い:
2か月前、2024年1月のオンラインミーティングで、我々JCAP移住者・難民ネットワークのメンバーは、DSSの第1章に基づいた黙想と分かち合いの時間を持ち、2022年3月からオンラインで集まり歩んできた道を振り返った。この2年間のオンラインミーティングと、特に2023年3月の東京での現地ミーティングを通して、我々はお互いの絆を再確認し、絆を深め、より多くのメンバーをネットワークに加えることができたことを確認した。このネットワークでの使命を支えるため、神が与えてくださった恵みに感謝した。
2024年3月に台北で集まったとき、我々はDSSの第2章と第3章に基づいて黙想の時間を持った。特に移動の最中にある人々と共に歩んできた自らの経験を振り返り、メンバーの分かち合いに耳を傾けながら、現代世界の現実を見つめる三位一体の受肉について黙想した。そして、我々のアイデンティティである「為す(doing)前に在る(being)こと」について黙想した。これらの黙想から得た実りの分かち合いが、今後の活動を支える霊的基盤となることを願っている。
現代世界の現実を見つめる三位一体は、苦しんでいる人々の痛みに憐れみの心を動かされた。神の憐れみのゆえに、三位一体は第二の人格の受肉を決意し、共に歩むことで苦しむ人々の友となられた。そうすることによって、その生き方によって、彼らの痛みが我々の痛みであることを教えてくださったのだ。したがって、彼らの痛みと喜びを分かち合い、キリストのいつくしみに突き動かされながら、我々は移住者や難民の友人として歩むことを願う。痛みと喜びを分かち合う行為を通して、我々は神から託された世界の希望となり、光となることができる。この希望と光が我々を導き、前進する力を与えてくれるであろう。
我々は、移住者や難民の友となり共に歩む精神のもと、本5カ年計画を実施する。実践において、「活動における観想」の精神を堅持する。即時の結果が求められる現代世界において、神のいつくしみの光の中で、一歩一歩進んでいきたいと思う。安らかに眠る幼子のように、時を越えて働く神に委ね、時間は空間に勝ることを忘れずに。我々のネットワークは、誰もが船を休め、現実の荒波で疲れ果てた人々が互いに繋がり、支え合い、命を蘇らせ、自由に羽ばたくことができる港のような場所であることを願っている。我々に蒔かれた種は、時とともに成長し、我々のネットワークは、より多くの移住者や難民を仲間として受け入れ、神の恵みに照らされ空に向かって成長する木々のように、深まり、広がっていくであろう。

JCAP MRN LOGO ロゴマークの各要素に込められた意味:
- 円形・・・善意のすべての人々と共に、ネットワークのうちに働くという努力の象徴。
- 緑の葉・・・JCAPの特徴を表す典型的なモチーフであり、緑色はよりよい未来への希望を意味する。
- 赤い炎と人々・・・聖霊によって個々人や諸機関が動かされている。それは奉仕のため、共に歩むため、そして移住者や難民と共にあるためである。
分断線を越えるチャレンジ
~日本人と外国人を分断する入管難民法にあらがう~
佐藤 信行
外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会(外キ協)
「永住取り消し法案」の成立
現在、日本に暮らす外国人は約330万人となりました(在留資格を失った人びと8万人も含む)。そのうち、日本の植民地支配に起因する在日韓国朝鮮人・台湾人の「特別永住者」は28万人、中国・フィリピン・ブラジル・韓国などからのニューカマーの「永住者」は89万人にも上り、彼ら彼女らは地域社会において、「多民族・多文化共生」のための働きを担っています。
それにもかかわらず政府は今年3月、「出入国管理及び難民認定法」(入管難民法)の改定案として、「育成就労制度の創設」とともに、「永住資格取り消し」「マイナンバーカードとの一体化」の法案を閣議決定して、国会に上程しました。
永住取り消し法案は、①在留カードの常時携帯や7年ごとの在留カード更新、転居後14日以内の住所変更届出など、入管難民法上の義務に違反した場合、②不法侵入などの罪で1年以下の懲役(執行猶予を含む)の判決を受けた場合、③税金や社会保険料を納付しなかった場合、入管局が永住資格を取り消せる、としています。
しかし、①の入管難民法のこれらの義務規定はそもそも国際人権条約に違反するものであり、②は二重の制裁と言うべきものです。③の税金や社会保険料の滞納に対しては、督促や差し押さえなど現在の制裁制度に加えて、永住資格を取り消すのは、「外国人であるが故の」人種差別的な立法です。
この法案に対しては在日本大韓民国民団や華僑総会、在日コリアン弁護士協会をはじめ、多くの市民団体と弁護士会、そして外キ協や在日大韓基督教会、カトリック大阪高松大司教区などの各教団・教区が相次いで反対声明を出しました。特にカトリック教会もプロテスタント教会も、今や多くの外国籍信徒・教役者を迎え入れているからです。
私たち外キ協は、東日本大震災の翌年から福島県の国際結婚移住女性たちと協働の取り組みを進めてきました。移住女性たちは震災後、県内で自助組織を起ち上げて、子どもたちの継承語(母語)教室を自力で開き、地元市民とのさまざまな交流プログラムを実施しています。郡山市、須賀川市、いわき市と、それはまだ小さな点と点にすぎませんが、「共に生き、共に生かし合う」地域社会をめざす働きを続けてきました。
そして彼女たちの多くは、震災後13年の間で、「日本人の配偶者等」の在留資格から「永住者」となりました。それこそ、過去5年分の収入と納税に関する資料、直近2年分の社会保険料納付の資料などたくさんの書類を揃え、厳しい審査を経て、彼女たちにとっては文字通りの「永住権」を獲得していったのです。その彼女たちが先月、永住取り消し法案について、口を揃えてこう言うのです。
「私たちの永住権がなくなるというのなら、日本人は滞納したら国籍も住民票もなくなるの?」
私は、彼女たちの当然の問いに答えることができませんでした。
このような当事者からの強い反対、市民団体・教会・労組の国会前シットインなどさまざまな反対運動にもかかわらず、国会は6月14日にこの法案を可決しました。

この法案の実施は3年以内となっていますが、国連の人種差別撤廃委員会は6月27日、永住取り消し法は人種差別撤廃条約に抵触するものであり、「見直しと廃止を含む緊急措置」を求める、という書簡を日本政府に送りました。
「難民申請者追い出し法」の実施
このように、外国人に対する締め付けが相次いで強化される中で、昨年国会で成立した、もう一つの「改悪」入管難民法が今年6月10日から実施されました。その改悪法とは、①難民申請者を国外追放してはならないという国際的原則を無視して、3回以上難民申請をする者を強制送還する、②送還を拒否する者へ刑事罰を科す、③自主出国をしない者を無期限に収容するか、監理措置とする――という過酷なものです。これらは、いずれも難民条約をはじめ国際人権条約に違反しています。
そのうえ日本は、難民認定率が極端に低いのです。たとえば2020年、コロナ・パンデミックで全世界の空港・海港が封鎖される中、G7諸国の難民認定数を見ると、ドイツ63,456人(認定率41.7%)、カナダ19,596人(55.2%)、フランス18,868人(14.6%)、米国18,177人(25.7%)、英国9,108人(47.6%)となっていたのに、日本の認定数はわずか47人、認定率0.5%なのです。
そして空港・海港封鎖が解かれた昨年、日本の難民申請者は13,823人に上りました。しかし、難民として認定された人はわずか303人、つまり認定率2%です。そのため難民申請者のうち、「難民認定303人+補完的保護2人+人道配慮1,005人=1,310人」以外の人びと12,513人は、出国を迫られ、出国を拒否すれば在留資格を失ったり、あるいは仮放免/入管収容のまま置かれています。すなわち、認定率1~2%という最悪の日本の難民認定制度が根本的に改善されない限り、今後も「難民認定から排除された人びと」は増えていく一方なのです。
私たち外キ協は昨年6月の改悪法の成立に抗議し、「難民・移民と共に生きる教会共同声明」を126の教派・団体・教区・個教会の連名で出しました。その共同の意思を起点として8月、「難民・移民なかまのいのちの緊急基金」を起ち上げました。「期間:1年間/基金目標:1000万円/難民申請者・仮放免者ら300人支援」を目標として出発した緊急基金は、現在まで献金総額が10,288,134円となり、その献金から難民申請者・仮放免者ら313人を支援することができました。
緊急基金が支援した難民申請者・仮放免者らの国籍別では、1位がトルコ98人(36%)となっていて、その大半がクルド人です。また難民申請別では、申請中181人、異議申し立て中18人、訴訟中2人、認定不認定のまま41人となります。在留資格別に見ると、仮放免中の人が196人で、全体の73%となっています。それ以外の「在留資格あり」の人でも、さまざまな経緯の中できわめて切迫している状況に置かれていることが、支援申請書からうかがわれました。
また、年代別では0歳~19歳の子どもが90人となり、全体の33%となっています。本国の迫害から逃れて親と共に日本に来たものの、難民鎖国の壁に阻まれている、あるいは、親の難民申請が何年も認められないうちに子どもが生まれた――そのような中で、子どもたちが増えてきた状況が反映されているのです。ある一家の支援申請書には、こう書かれています。
「娘たちは、両親に在留資格がなかったため、日本で生まれた時から在留資格がありません。父は心臓病、母は統合失調症、娘二人の中学・高校進学準備の制服代などは、父の友人からの借金でまかなっています。医療費・生活費・教育費の全般で困窮」
私たちが1年前の教会共同声明で、「私たちは教会において、とりわけ難民申請者や無登録外国人、その一人一人の命と生活を支える市民社会の働きに連帯し、具体的な取り組みを始めていく」と決意した第一歩が、この「難民・移民なかまのいのちの緊急基金」でした。その緊急基金は今年7月で一旦完了しましたが、今秋から中長期的な基金へとスタートさせようと準備しています。なぜなら、この1年間で緊急基金に献金を寄せてくれた教会は133、個人は247人に上り、「祈りを合わせ、共に歩む」教会のネットワーク、キリスト者のネットワークをさらに拡げたい、と願うからです。