平和への祈りを込め、窮迫するミャンマーを支援するために
ロザリン カヤ
イエズス会信徒協働者
東南アジアの中心に位置するミャンマーは、現在、破滅的な騒乱と悲劇の渦中にあります。人口5,660万人のミャンマーは、政情不安、経済的混乱、紛争の激化という複雑な要因が絡み合い、国民は耐え難い苦難を強いられています。1962年、1988年、そして最近では2021年2月と、近代史において3度の軍事クーデターを経験しています。

| ミャンマー国軍によって焼き払われたロイコー教区の教会 |
2021年のクーデターは、大規模な市民運動のうねりに火をつけました。ミャンマーの若者による勇敢な参画がその特徴でした。これらのデモは平和的なものであったにもかかわらず、軍の反応は抗議者たちに対する暴力以外の何ものでもありませんでした。そのため、平和的な抵抗から武装した市民的な防衛行動へと拍車がかかり、民族武装グループと同盟を結ぶにつれて勢力を拡大していきました。このように変容した抵抗運動は、双方に大きな犠牲を払いながらも、あらゆる困難をものともせず、依然として続いています。
一般市民の犠牲者は驚くほど多く、2024年4月現在、600人以上の子どもを含む4,900人以上の民間人が命を落としています。拘束された人々の数も同様の壮絶な状況を物語っており、26,000人以上の民間人が逮捕され、その中には700人以上の子どもたちが含まれています。更に、礼拝施設を含む78,000以上の民有財産が損なわれました。
教育を受けている1,300万人のうち、約450万人の子どもたちが、コロナ禍と紛争の相乗的要因により、教育へのアクセスが制限されているか、まったく受けられない状況に陥っています。子どもたちは、児童労働、薬物やギャンブルへの依存、少年兵としての徴用、早過ぎる結婚、性的搾取や虐待、人身売買などの危険にさらされています。多くの若者が安全やチャンスを求めて国外へ流出しており、ミャンマーの将来に何世代にもわたって影響を及ぼしかねない若年層の深刻な流出につながる可能性があります。

| 多くの子どもたちが学習の機会を失った |
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の報告によると、280万人以上が国内避難民であり、その90%が2021年のクーデター以降に避難生活を送っています。 さらに、100万人以上のミャンマーからの難民がバングラデシュ、タイ、インド、あるいはマレーシア、少数ではあるもののインドネシアなどの近隣諸国に逃れました。2024年現在、ミャンマー総人口のほぼ3分の1に相当する1,860万人が人道的支援を必要としています。
このような苛酷な状況にもかかわらず、かすかな希望の光が見えています。私たちイエズス会協働者と支援者は、自らが避難生活を余儀なくされているにもかかわらず、困窮する兄弟姉妹を支えることに尽力しています。食料、住居用資材、毛布、マットなど、命をつなぐために必要不可欠な支援を、私たちにできる範囲で行っています。また、地域コミュニティと協力し、子どもたちのために継続して学べる機会を設けています。

| ロイコー教区の避難民のための一時避難所 |
皆さんの祈りと支援は、苦境にあるミャンマーの人々に希望と癒しを与え、変化をもたらすことでしょう。力を合わせ、絶望に包まれた暗闇に光をもたらしましょう。私たちは一丸となって、数多くの人々の暮らしに変化をもたらし、平和と安定を乞い願うこの国に変革をもたらすことができるはずです。
アルペ研究養成センター (CARF)
~今日の多面的な社会的・環境的危機に対するイエズス会の応答~
トゥサン カファヒレー ムフーラ SJ
アルペ研究養成センター所長
はじめに
アルペ研究養成センター(Centre Arrupe pour la Recherche et la Formation、以下CARF)は、コンゴ民主共和国のルブンバシ市にあるイエズス会の社会センターです。2013年に設立され、翌年4月2日、「コンゴのイエズス会の神父たち」のNPOとして発足しました。CARFの設立は、カタンガ地域におけるイエズス会の活動開始50周年を記念するものでした。実際にイエズス会は、1965年にキンシャサに設立されたCEPAS(社会活動研究センター)を反映するこの社会センターを始動することに同意していました。CEPASは、コンゴの社会と国家の発展と変革に携わる最もよく知られた拠点でありシンクタンクです。
しかし、CARFの設立につながる識別は、イエズス会中央アフリカ管区(基本的にアンゴラとコンゴ民主共和国の2か国で構成されている)の会員たちが2009年にカタンガ州における活動開始50周年を祝う準備をしていた時にすでに始まっていました。19世紀末の植民地国家の始まりから現在に至るまでの現代コンゴの歴史は、イエズス会の宣教活動と密接に絡み合っていますが、植民地当局は福音宣教を目的として、様々な地域を様々な修道会に割り当てていたことを念頭に置くことが重要です。イエズス会がベネディクト会の伝統的領地であったルブンバシに移り、新設の大学を支援するようになったのは、1950年代後半、国家のほぼ独立前夜のことでした。
そして、その後50年間(1959年~2009年)、イエズス会はルブンバシ大学で教鞭をとり、同大学に神学生を送って学ばせ、大学のチャペルを運営しながら地元のカテドラルへの指導力も発揮しました。にもかかわらず、イエズス会のプロジェクトの特徴である使徒職の別の形を持っていませんでした。
コンゴ共和国におけるイエズス会の存在
コンゴのイエズス会は、ベルギーによる植民地事業の初期から教育制度の発展に深く関わってきました。それを歴史的な観点から見てみましょう。
聖イグナチオ・デ・ロヨラ自身が命じた最初の福音宣教の失敗の後、19世紀末に植民地計画のもとで二度目の宣教が試みられました。実際に16世紀のコンゴの国王たちは、「教会の運営を直接管理し、リスボンやローマに司祭の派遣を要請していた」ことが知られています。当時、コンゴ王国はアフリカ全土で唯一のカトリック王国だったのです。それゆえ、聖イグナチオ・デ・ロヨラは早くも1548年に4人のイエズス会員をコンゴ王国に派遣しましたが、この宣教は1555年までしか続きませんでした。おそらく、国王がカトリック司祭たちの神学的見解に反対していたためだと思われます。
イエズス会宣教師のコンゴへの第二波は、19世紀末の植民地計画とともに起こりました。国王レオポルド2世の要請により、ベルギーのイエズス会の一団が、1893年3月30日に、植民地のコンゴ自由国(CFS)に到着しました。1885年のベルリン会議で国王は、地元住民の福祉を向上し、国を国際貿易に開放する――誰でもコンゴ国内で自由に商売ができるように――という彼の善意をヨーロッパの指導者たちに巧みに信じ込ませましたが、イエズス会員をその植民地事業に引き込むことには二度も失敗していました。ヨーロッパの宗主国間の競争とコンゴの戦略的重要性を考慮した結果、レオポルド2世の要求に応じ、コンゴを中立国ベルギーの管理下に置くことを決めました。コンゴ国内で自由貿易を主張できると知っていたからです。
レオポルド2世は、コンゴ自由国の行政官に宛てた直筆の手紙の中で、三つの大きな児童ゲットーを設立するという構想を記していました。植民地教育プログラムでは、ほとんどの人に初等教育が施され、少数の人が植民地計画の必要性を満たすために中等教育や職業教育を受けました。独立の理想が国際社会で広く共有されるようになったのは第二次世界大戦が終わってからのことで、ベルギー人は独立のわずか6年前の1950年代半ばに、最初の大学を急遽設立しました。
イエズス会は、学校、小教区、病院を建設することで植民地教育制度とコンゴ社会の発展に深く関わってきました。その結果、イエズス会はすぐに、最初のロヴァニウム大学が建設される場所の土地探しと取得交渉に協力しました。イエズス会はまた、大学の最初の指導者たちと学長を輩出しました。逆説的ではありますが、ルーヴェン・カトリック大学と提携していたキンシャサ大学に対抗するため、2年後の1956年に宗教と関係のない公立大学がルブンバシに設立されたとき、イエズス会員は引き続き、新設の大学の様々な学部に勤務するように求められていました。
それから50年後、ルブンバシのイエズス会は、社会において高まる要求と期待、そしてカタンガ地方におけるアフリカの重要な鉱物資源の新たな争奪競争をめぐって継続中の議論に直面して、自分たちがどのような存在でありたいか、どのように貢献したいかを考えるようになりました。そのため、人々を訓練し、歴史的・社会的・環境的正義に関する問題を検討する社会センターとしてCARFを設立することを決めたのです。
CARFの活動
CARFの組織図を見れば、今日私たちが「イエズス会使徒職全体の方向付け(UAPs)」と呼んでいるものとの共鳴にすぐに気づくでしょう。実際、コンゴ民主共和国という状況において、神が今日私たちに何を求めておられるかを識別することによって、私たちは自らの使命の緊急性が、コミュニティ間に留まらず、環境や将来の世代との間においても、平和、安定、正義、和解の向上のために働くことだと認識しました。
CARFの活動のもう一つの側面は、貧しい人々のニーズに配慮し、訓練や権利擁護活動のプロセスのうちに彼らと共に歩み、コミュニティ内で弱く声を上げられない人々を守る必要性を強調することです。CARFはまた、若者が集まり、自分たちの将来に関する問題について考えるための重要な場も提供しています。要するに、私たちは持続可能な開発に関する議論の中核にいますが、歴史的に私たちの国は戦略的な原材料の貯蔵庫として扱われてきました。人々を犠牲にしながら、環境だけでなく将来世代にも関わるより大きな正義を求める声は考慮されてこなかったのです。
したがって、私たちは時代のニーズに対してイエズス会が識別した一つの応答です。私たちは様々な社会的・政治的アクターを集め、コミュニティとしての私

| ストリートチルドレンらと祝ったクリスマス(2023年) |
たちにとってだけでなく、世界と私たちの共通の家の未来にとって最も重要な問題について考えています(2023年の年次報告書を参照)。
CARFのDNAには、社会福祉への関心が刻み込まれており、それには人権と環境正義の尊重と保護が必然的に伴います。さらに、意義ある言葉を練り上げるために、私たちは研究を行い、研究成果から報告書を作成します。私たちは人々、とりわけコミュニティのリーダーたちを訓練し、彼らがコミュニティに良い影響を与えられるようにします。私たちは、人々が価値ある人生を送れるように、行為主体性を本来あるべき場所に戻し、行動と意思決定の主権を人々に取り戻そうとしています。
これらの研究や研修活動に加えて、CARFは図書館スペースを開発しました。そこでは、研究出版物をアーカイブするだけでなく、知的活動、教育、執筆、出版を通じて影響を与え続けたいと考えている地元の研究者たち向けに重要な本を提案しています。
CARFのこれから
イエズス会の創立以来、聖イグナチオ・デ・ロヨラと最初の同志たちは、神のみ旨を深く信じる者でした。彼らは、自分たちが蒔いた小さな種がイエズス会へと成長するために、神にのみより頼みました。信仰の重要性に鑑み、イグナチオはこの精神を『会憲』(第812条)に定め、「神への奉仕と賛美、そして隣人の救い」を使命とするイエズス会は人間的な手段によって設立されたものではなく、その保持と発展も人間的な手段によってではなく、設立当初から存在していた神の恵みによってのみそれが可能であったことを指摘しています。私たちは同じ信仰とビジョンを共有しています。
CARFの使命は、福音の価値を生きることを通じて、コンゴ民主共和国やアフリカに暮らす神の民に繫栄と豊かな生活をもたらす教会の働きに貢献することであると、私たちは知っています。したがって私たちは、物理的手段が限られており、それがしばしば足かせとなってしまうにもかかわらず、愛と正義と平和の神の国がこの世界に到来するのを早めるために努力し続けるのだと確信しています。
それゆえ、私たちが奉仕するコミュニティによりよいサービスを提供するために、組織的能力の向上に重点を置くという大志を共同識別しました。コンゴ民主共和国は非常に豊かな国でありながら、悲しいことに、その豊かさを実現できておらず、社会福祉のために働く人に必要な資金を配分できていないという矛盾に常に直面しています。だからこそ私たちは、コンゴのこうした傾向をひっくり返すことに貢献できることを期待しつつ、グローバル・パートナーを探さなければなりません。
私たちの大きな夢の一つは、環境研究所を開発して、鉱業活動の一部、たとえば自然界に排出された物質の負の影響の監視を助けることなどです。実際、採掘現場周辺のコミュニティは、産業採掘作業による水質や大気の汚染のため、病気を発症したという訴えや報告をしています。酸や金属を含んだこうした廃棄物はまた、土壌をも汚染し、農業開発がほぼ不可能になるほどの危険にさらしています。鉱山採掘業者は、政府の力が弱かったり、共犯関係にあったりする場合、科学的根拠に裏付けられていなければ、こうした主張に対して責任ある行動を取ることができません。それゆえ、私たちはこのような環境モニタリング研究所の設立に必要な費用を集めるための募金キャンペーンを立ち上げました。この研究所はまた、科学を専攻する若い学生たちに、研究やインターン、さらに長期的な就労のための場も提供します。
参 照
◆ Toussaint M. Kafarhire, S.J., “Jesuits—Protestants Encounter in Colonial Congo in the Late Nineteenth Century: Perceptions, Prejudices, and Competitions for African souls,” (in Robert A. Maryks and Festo Mkenda, S.J., eds., Encounters Between Jesuits and Protestants in Africa. Boston, Brill, 2018, pp.194-214).
武力で平和はつくれない!
小野 文珖(1948年生)
日蓮宗僧侶 / 群馬諸宗教者の集い代表
1.総理大臣・防衛大臣への要請書
最近の「日本」の動きを見ると、まるで戦争前夜のような、きな臭い気配が充満している。防衛費の大幅増強、敵基地攻撃能力の保有、戦闘機の輸出解禁等々、憲法九条に定められた非戦の誓いを打ち破る大転換が、国会の議論も経ず、民意をも問わず、閣議決定という一部の権力者の思惑によって進められている。南西諸島のミサイル配備の実態を見聞すると、背筋が寒くなる思いがした。特に宗教者として危機感をいだいたのは、靖国神社の復活である。

日本の権力者は、「新しい戦前」の地ならしとして、再び国家神道の象徴としての靖国神社の復活を企てている。御国のために命を捧げた戦死者を英霊に祀り上げる、あの戦時体制を準備し始めたのである。信じられないが、事実なのである。宗教者はこれを見過ごしてはならない。アジア・太平洋戦争の悪夢を再現してはならないのである。
本年4月18日、「宗教者九条の和」の呼びかけ人世話役として、内閣府に赴き、内閣官房担当官に、総理大臣・防衛大臣宛要請書「自衛隊の靖国神社公式参拝の中止を求めます ――英霊の受け入れ体制づくりを許さない――」を提出した。
第二次世界大戦後、日本の国家神道は解体されたが、靖国神社は宗教施設として残り、今なお、天皇を中心とした国家体制のために殉じた軍人らの「英霊」を、「神」として祀っている。4月1日、その神社の宮司に海上自衛隊の元海将が就任したというのである。
4月18日に、衆議院第二議員会館前で、私たち「平和をつくりだす宗教者ネット」の仲間は、『憲法を守れ! 死の商人国家に堕落するな!』の緊急行動を実施した。私もマイクを持って、国会に向かい、提出してきた「自衛隊の靖国神社公式参拝の中止を求める」要請書を読み上げ、戦争の準備ではなく平和の準備を、と訴えてきた。私たち「平和ネット」には、キリスト教・イスラム教・神道・諸宗教・仏教の聖職者や信徒、連携する市民団体の人たちが参加しているが、皆、等しく、この時代の危機を痛感し、居たたまれなくなって街に出て、スタンディングや行進を始めているのである。この横断幕を持って。「武力で平和はつくれない!」

2.行政と司法の癒着を許すな
「新安保法制違憲訴訟」の原告の一人である私は、2020年に小冊子『ある仏教者の平和宣言』を出版した。
この安保法制違憲訴訟は全国で提起されたが、原告の市民の敗訴が続いている。これまでの判決は最高裁でさえも、安保法制の違憲性には一切触れず、憲法判断を避けて、「現時点において我が国に対する武力攻撃が発生し又は切迫していないから、生命・身体に対する具体的・客観的危険はない」(『安保法制違憲訴訟・全国ネットワーク報・7号』)というのが主な理由である。全くおかしな論理で、戦争が始まったら取り返しがつかないから、集団的自衛権の行使など認めてはならないと訴えているのに、「戦争になってから考えよう」というのである。裁判官の職責を放棄したような判決が各地で下されている。この傾向は、原発再稼働反対の裁判でも、最近の追悼碑裁判(後述)でも顕著であり、三権分立の「日本国憲法」で、司法権の独立が認められているとの理解を疑わせるような法廷に立ち合わされている。
2023年5月25日、東京高等裁判所で、群馬安保法制の違憲訴訟の控訴審の判決が言い渡された。原告として傍聴した。判決は「控訴棄却」。その最後の部分を筆記する。
控訴人らの平和を希求する信念や信条は十分に尊重されるべきであるが、「平和」という概念は、理念ないし目的としての抽象的な概念であり、各人の思想・信条、世界観又は価値観等によって多義的な解釈を余儀なくされるものである上に、これを確保する手段や方法も変転する複雑な国際情勢に応じて多様な議論があり得るものであるから、控訴人らの主張する平和的生存権が裁判規範としてどのような内容と効果を有するものであるかは明らかでなく、控訴人らの主張は採用できない。
ここ10年、沖縄・朝鮮・原発・安保に関わる裁判を注目して調べてきたが、いずれの判決も政府の思惑を忖度したような内容が強く、不信感をつのらせていたが、ようやく納得する解説に出会った。それは、日本の司法界に慣行されている「判検交流」という制度が原因であるというのである。裁判官が毎年多数法務省に出向し、国側の立場で検事の仕事をし、年数がくると裁判所に戻り、判事の仕事に就くという、判事と検事の人事交流が実際行われていると報告されている(「しんぶん赤旗」2024年5月7日号、弁護士・神戸大学名誉教授阿部泰隆氏の投稿)。阿部氏はその論考で「法務省の要職を占めて、高裁裁判長になったら、国側の主張をそのまま認める判決を出す例は少なくない」と実例を挙げている。そして「憲法七六条三項」から、司法は行政の監視役であるから、監視される国会、行政機関と癒着したりしてはならず、独立していなければならない、と司法権の独立を強調している。
まさにその通り、国民は目覚めて、今の日本の司法の在り方に声を挙げなければならない。このままでは日本国憲法は空洞化どころか死に体である。憲法の番人が職務を放棄しているから当然である。今こそ、主権を持つ国民が監視役として立ち上がらなければならない。「平和」を抽象的概念、などと寝ボケたことを言わせてはならない。80年前の戦争で三百万人以上の犠牲者をだしてつかみ得た「平和」なのである。今この時に、ウクライナで、ガザで、爆撃やミサイルで市民が命を絶たれている。「平和的生存権」は日本国憲法で日本国民に具体的権利として保障されているが、それを実現するためには、憲法を守る国民の責任と義務を果たす不断の努力が必要なのである。だから今日も街に出る。「武力で平和はつくれない!」
3.「記憶 反省 そして友好」碑再建を!
2004年、群馬県の県立公園「群馬の森」に、市民団体によって建立された、戦前朝鮮半島から強制連行によって県内で労働に従事させられて亡くなった多くの犠牲者を追悼する「記憶 反省 そして友好」の碑が、本年1月29日、山本一太県知事の行政代執行によって破却撤去された。
この報を病床で聞いた「追悼碑を守る会」の共同代表であり、追悼碑裁判の弁護団長を務めた角田義一氏は、家族にこのように言い残した。「無残にも追悼碑は破壊され、瓦礫の山と化してしまった。このような暴挙は人間性を欠いた非情な仕打ちであり、恨みが残り、決して許されるものではない。強い憤りを覚える。しかし、諦めることなく、全国の有志の力を結集し、新たに追悼碑の再建に取り組んでいきたい。」2月23日に亡くなっているので、これは遺言になった。
5月11日、追悼碑を守る会の第20回の追悼式と総会が群馬県教育会館で開催された。取り外されたプレート3枚を守る会が取り戻し、式場に掲げて、300名を超える参加者全員で献花し、追悼した。総会では「守る会」と「追悼碑裁判を支える会」の解散が発表され、新たな地平に立って、新しい組織を結成し、「記憶 反省 そして友好」の運動をすすめることが決定した。角田先生の遺志を継承することが誓われたのである。

働く若者のグループJOCの本
『変わる! 〜新しい仲間とアクションの作り方〜』
宇井 彩野
作家 / 日本JOCサポーター
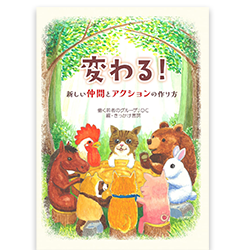
今の日本で、「自分自身がこの社会を変える一員である」と考えている人はどれだけいるでしょう。選挙の投票率を見れば、あまり多くない割合かもしれません。
「自分自身が社会を変える」という自覚を持っている人々は、「どうしたらもっと周りの人たちが、社会や政治に関心を持ってくれるのか」と、常に頭を悩ませている人々でもあります。これを読んでいる皆さんも、おそらくその一人なのではないでしょうか。
『変わる! ~新しい仲間とアクションの作り方~』という本は、働く若者のグループJOC(カトリック青年労働者連盟)が培ってきたメソッドを、現代の日本の若者たちに読みやすい形に整理して、一冊の本にまとめたものです。
JOCでは、若者たちの意識が活動の中で変化し、より広い社会に目を向けるようになっていくことが、実際に、日々起こっています。なぜJOCは若者の意識を変えられるのか。そのヒントが、本書『変わる!』によって外部の人々にも伝えられるのではないかと期待しています。
本書を商業販売向けの書籍とした理由の一つは、JOCが世の中にもっと知られてほしい、という思いからです。一人ひとりの若者の意識に変化を起こすという面では他にはない強みを持っているJOCですが、一人ひとりを養成していく活動は、地道なものになりやすく、人目につきにくいのも事実です。JOCのような活動がもっと多くの若者に届いたらと、JOCメンバーや彼らを支える協力者たちも、常々頭を悩ませています。
本書が、JOCを多くの人に知らせる第一歩となり、皆さんの周りにいる「社会や政治に興味を持たない人たち」が、「変わるかもしれない人たち」になっていく──そんな広がりを作り出せたら、と考えています。
では、そのJOCのメソッドとは一体どんなものなのか。それが、副題である「新しい仲間とアクションの作り方」の示すところです。
JOCの活動とは何かを簡潔に言い表すならば、「仲間作り」と「アクションを起こすこと」です。または、JOCの方法論である「見る・判断・実行」を知っている方も多いかもしれません。
まずは現状を「見る」ところからスタートするのがJOCですが、「見る」ためには、共に現状を話し合うグループが必要です。そのグループ作りの初期段階から、グループでのミーティングに必要な準備、役割、進め方などを、本書で詳細に記しています。
さらにどんなポイントで「見る」のか、見た上で「判断」するとはどういうことなのか、そして最後にはもちろん、「実行=アクション」があります。
アクションには、一人で行える小さなアクションから、2人~少人数でのアクション、グループで行うアクションがあります。アクションの規模が大きくなるほど、綿密な計画が必要になります。そのためのアクションプラン会議の進め方に関しても、JOCには、国際的な共通のメソッドがあり、本書で紹介しています。
これらのメソッドは、教会やカトリックの中で、社会的な活動を行うグループを作りたいと思っている人にとっても、効果的に活用できるものです。
JOCの「国際的な共通のメソッド」と書きましたが、それは国際JOC「基本三文書」として明確に文書化されています。そしてその「基本三文書」も、本書『変わる!』の最後に、全文掲載しています。
「基本三文書」は、JOCの基本原理を記した「原則の宣言(DOP=Declaration of Principle)」、JOCが社会に果たす役割と使命を記した「働く若者の教育(TOE=Task of Education)」、そしてJOCの方法論を記した「生活と労働者アクションの見直し(ROLWA=Review of Life and Worker Action)」の3つから成ります。
なぜJOCの内部的な文書であり、一般的な読み物とは言い難い「基本三文書」を全文掲載したのか。それは、この文書そのものに大きな魅力があるからです。
これらの文書が作られたのは、1975年。「原則の宣言(DOP)」に関しては、社会の発展や運動の歴史をふまえ、1987~1991年にかけて改訂されました。改訂版もすでに30年以上前となるにもかかわらず、そこには、私たちが直面している2024年の世界を描いているかのような記述があります。
以下は、DOPの中に記された「今日の世界」という箇所の一部抜粋です。
「今も、JOC運動が生まれた時と同じように、働く若者たちは資本主義の矛盾に直面しています。そしてその矛盾はこれまでよりもさらに深刻になっています。 (中略)
資本主義は、経済的に豊かな国と貧しい国との格差を拡大させます。それは確実に、国の中での富裕層と貧困層の格差拡大にもつながっています。技術革新も、情報も、権力者たちによってコントロールされ、ごく少数の富裕な人々が支配し、搾取し、大多数の貧しく排除され続けている人々になり代わって多くの決定を下します。 (中略)
環境に配慮することなく、天然資源が破壊されています。多くの国で、人種差別やナショナリズム、宗教への狂信主義が、排除の加速をもたらしています。」
また、基本三文書の各所には、「労働者階級」という言葉がたびたび登場し、JOC運動の主体はこの労働者階級の若者たちであることを強調しています。
労働者階級は、資本主義社会の中で利益を増やす元手となる資本を持たず、自分の「時間」と「労働」しか売るものがない人たちです。JOCは労働者運動ですが、その意味するところは「労働者階級に属する者の運動」。そこには失業者や学生も含まれます。
そして、JOCが目指す「新しい社会」についてこう記しています。
「それは搾取・貧困・飢餓・差別の存在しない社会。製品の生産と消費は人間が人間らしくあるためのものであり、必要とするすべての人に供給される社会。各個人、各国、それぞれの文化が尊重され、連帯が築かれる社会」
実は日本JOCの運動においても、この基本三文書は、これまで十分に生かされていませんでした。そこで2018~2019年にかけて、改めて英語から翻訳し直し、運動の中で活用できるものにするために、当初は内部向けの冊子として製作しました。しかし、翻訳を進めるうちに、ここに書かれていることの重要性を、もっと広く発信すべきではないかという思いが強くなっていきました。
しかし、三文書だけでは一般にはわかりにくいものであることや、メンバーの若者たちに向けてもよりやさしい資料が必要だったことから、「見る・判断・実行」の流れを絵本のようにまとめた第一章、実際に活動を始めるためのガイドとなる実践編の第二章、そして基本三文書全文を掲載した第三章という形になりました。
『変わる! ~新しい仲間とアクションの作り方~』は、個人ではウェブ通販(https://ikinobi.base.shop/)でお買い求めいただけるほか、書店からの取り扱いお申し込みも常時受け付けています。取引情報は、http://kikkakeshobou.ikinobi.com/にてご確認ください。FAX(03-3641-6780)でもご注文いただけます。

