Ignatian Year(イグナチオ年)の開始に向けて
―すべてのものをキリストにおいて新しく見る―
山内 保憲 SJ
イエズス会日本管区 イグナチオ年コーディネーター

2021年5月20日から2022年7月31日(聖イグナチオの記念日)まで、全世界のイエズス会はIgnatian Year(イグナチオ年)を祝います。イグナチオとは、イエズス会の創立者であるイグナチオ・デ・ロヨラのことです。2021年5月20日は、1521年にイグナチオがパンプローナの戦いで砲弾直撃を受けてから500年目にあたります。このパンプローナの砲弾は、騎士として成功したいと願っていたイグナチオの夢と人生の見取り図を打ち壊しました。しかし、イグナチオが足の傷のために療養している間に、神は彼に回心をもたらし、キリストに従う決意へと導きました。結果として、イグナチオはキリストに従うという、まったく新しい生き方へと招かれ、後にイエズス会を創立していくことになります。イエズス会は、この「回心」の出来事を記念して、イグナチオ年を祝います。
これから始まるイグナチオ年の標語は、「すべてのものをキリストにおいて新しく見る」です。1521年から1522年まで、イグナチオは故郷であるロヨラで療養していました。その時に、彼は内的な変化を体験し始め、やがてマンレサに滞在している時に、「すべてのものを新たに見るようになった」と自叙伝の中で述べています。もともとイグナチオ年は、新型コロナウィルスのパンデミックが起こる前から計画されていましたが、偶然にも私たちは特別な形でイグナチオの体験を追体験することになりました。パンデミックによって、私たちもまた、思い描いていた多くの計画が打ち壊されました。療養中のイグナチオのように、私たちもさまざまな制約の中でイグナチオ年を迎えます。このことは、イグナチオ年を形式的に祝うことで終わらせるのではなく、イグナチオの体験を真剣に見つめ直すようにとの主からの呼びかけのようにも感じられます。つまり、イグナチオと同じように、私たちもまた、「すべてのものを新しく見る」ことを通して、私たちの古い生き方やこれまでのやり方を手放していくことが求められているのです。
イグナチオ年は私たちを回心へと導く、霊的な旅でもあります。イグナチオが聖地への巡礼を望んでマンレサに到着したように、イグナチオは、神を求めるすべての人に霊的な旅を経験させてきましたし、今なお彼が残した『霊操』に導かれて多くの人々が霊的な旅を経験しています。この回心へ向かう霊的な旅は、イグナチオ年に先立ってすでに始まっています。イエズス会は2019年に「イエズス会使徒職全体の方向づけ(UAP)」(2019-2029)を打ち出しました。このUAPは、教皇を通して、聖霊からの贈り物として全世界のイエズス会に与えられました。すでにこの2年間、私たちはその方向づけに向かって進むように識別の旅を始めてきました。そして、このUAPが、イグナチオ年を通して「すべてのものをキリストにおいて新しく見る」ために重要であると考えています。つまり、私たちがUAP的な生き方、すなわち、霊操と識別を通して神への道を示し、貧しい人々、排除された人々と共に歩み、若者に寄り添い、私たちの共通の家(地球)の世話のために協力する時に、私たちの世界、教会、イエズス会、そして私たち個々人に対しての神の望みがこれまでになく、よりはっきりと示されると考えています。
特に、イグナチオは貧しい人々との交わりを通して、清貧の生活へと招かれました。このことは、彼の人生の変化の中でも特に大きなものの一つでした。そして、このことは現代のイエズス会にとっても大切な呼びかけの一つです。イグナチオ年は、多様な社会的、文化的状況の中で、貧しい人々、排除された人々、尊厳が尊重されていない人々の叫びを聞く絶好の機会としていきたいと思います。この取り組みを通して、私たちは心が動かされ、私たちを排除された人々へと近づけ、正義と和解を求めて彼らと共に歩むように導かれるように願っています。
さらに、UAPでは、私たちの個人的、共同体的、そして組織としての回心への強い呼びかけを確認しています。イグナチオや初期の同志たちのように、主からの呼びかけを共同で識別することに招かれています。さらに、イエズス会員の内だけでなく、イエズス会のミッションにおける仲間との間で、共に働くこと(「協働」)を深めていくことが使徒的刷新の条件であると呼びかけています。多様な世界の状況は複雑化し、「貧しい人々、排除された人々、尊厳が尊重されていない人々の叫び」を見出し、聞いていくことは以前にも増して困難になってきています。イエズス会員は、謙遜に自分たちの限界を認め、共に働く仲間へ耳を開いていくことが求められています。「私たちの共通の家(地球)」の叫びについても、イエズス会員よりも民間の多くの研究者や団体、企業の研究が卓越しているのは確かです。イエズス会の使徒的活動のさまざまなレベルにおいて、私たちのミッションに協働する人々の参加を促進していくことが求められています。
イグナチオ年が目指していることについて、ここまで説明してきました。これを書きながら、2年前の出来事を思い出しました。私は、高齢になったイエズス会員と共に生活をしています。この共同体では、毎年の黙想のために講師を招きます。私は、2019年に発表されたUAPを受けて、UAPに関連する分野の専門家を招いて黙想のヒントを分かち合っていただくことを考えました。そこで、社会正義の分野に関して、社会司牧センターの柳川氏を講師としてお招きしました。高齢のイエズス会員の中には、信徒が黙想の講話をすることに不満を訴える人もいました。しかし、柳川氏の講話を通して、私たちは現代社会の中で、どのような人々が排除され、尊厳が尊重されていないのかを新たに学ぶことができました。さらに、深い感銘を受けたのは、柳川氏が「私は、単に社会問題について活動するNPOで働いているのではない。イグナチオの霊性によって、神が何を望まれているのかを識別し『小さな人々との福音的連帯』を目指すイエズス会社会司牧センターにミッションを感じている」と分かち合っていただいたことです。この言葉に、イエズス会員は喜びを感じ、また勇気づけられたのです。この体験は、イグナチオが残した霊操と識別を通して、貧しい人々、排除された人々と共に歩み、協働していく中で、「すべてのものをキリストにおいて新しく見る」回心のステップの始まりのように感じました。
イエズス会のこの「社会司牧通信」を通して関わりのあるすべての皆さんに、イグナチオ年への協力を呼びかけたいと思います。このイグナチオ年を単なるイベントに終わらせるのではなく、また、重荷や義務として捉えるのでもなく、私たちの使徒職と識別の歩みを深めていくチャンスとしていきたいと思います。イエズス会員とイグナチオの霊性を共有する家族である皆さんが共に、イグナチオのように回心の体験をしていきたいと思います。まずは、皆さんとの対話を通して、イグナチオ年にすべきことを識別していきたいと思います。イグナチオ年への招きを受けて、皆さんがどのような主からの呼びかけを感じているか、イグナチオ年のコーディネーターにもお知らせいただければ幸いです。
使徒的勧告 『愛するアマゾン』
~教皇フランシスコのアマゾンにかける夢~
堀江 節郎 SJ
イエズス会司祭

最近出された『愛するアマゾン』は2020年2月に発表された教皇フランシスコの使徒的勧告“Querida Amazonia”の邦訳である。この勧告は、それより数ヶ月前に開催されたアマゾンの特別シノドス(2019年10月)を土台として、それに協力した人々への感謝をも含め、アマゾンへ、愛を込めて送られた手紙といえる。この勧告は、直接にはアマゾン地帯(九つの国が共有)の問題に関わるものだが、それは同時に全世界に向けて発信されている。アマゾンがみんなのものだから、そして、この地の課題がすべての地域にも刺激となるからである。勧告の四つの章は、それぞれアマゾンにかける教皇の、社会の夢、文化の夢、エコロジーの夢、そして教会の夢として綴られている。
第一章:社会の夢
「わたしの夢見るアマゾンは、もっとも貧しい人、先住民族、最底辺に置かれた人の権利のために闘うアマゾンです。彼らの声が聞き届けられ、尊厳が擁護される地です」(『愛するアマゾン』7)。つまり教皇の夢は、その地のすべての住民が幸福な「良い生活」を確立するようにとの強い希求に他ならない(8)。これはBem Viverと言われ、アマゾンの先住民が、生態系の恵みに包まれて営む、質素な、そして健康的な共同体的生活を指す。
現在、アマゾンが直面している「生態学的災害」はそこに住む住民の生命の危機でもある。つまり環境問題はそこに住む住民、先住民の人権を守る正義の問題、社会問題なのである(8)。アマゾンの資源を求めて、材木商、畜産業などの企業団体が乱入し、伐採、採掘が拡大しつつあり、「この事態が、昨今の先住民族の都市周縁部への移住を加速させたのです。彼らがそれで得たものは…奴隷状態、隷属、困窮のいっそうの悪化です。…こうした都市に、今や、アマゾンの地域住人の大半が住み、そこでは異民族排斥、性的搾取、人身取引も増加しています」(10)。
教皇は、アマゾンを破壊し先住民の権利を奪う国内、国際企業の行動を「不正義、犯罪」と宣告する(14)。そして不正義と犯罪に向かって、教会は「憤る」預言者的使命があると言う(15)。同時に、権力者たちの不正義に荷担したこともあった教会の歴史を見つめ、その罪を恥じ、平身低頭でゆるしを請うのである(19)。
第二章:文化の夢

「わたしの夢見るアマゾンは、傑出した文化の豊かさを守るアマゾンです。人間の美がさまざまに輝く地です」(7)。その生態系が失われているようにアマゾンの文化も失われつつある。先住民の文化の特色は、大自然と人間が一体で互いを生かし合う文化だからである。「彼らを『未開の』野蛮人と理解することは避けねばなりません。彼らは、かつては高度に発展した、ただし、異なる文化、異なる形態の文明を生み出した」(29)。
都市部に移住させられた先住民は自然との繋がりを失い、彼らの価値基準や文化的ルーツを失うのである。教皇は先住民の若者たちに、先祖伝来の文化の再生のため「自らのルーツを担う」よう願う(33)。
第三章:エコロジーの夢
「わたしの夢見るアマゾンは、その地を彩る圧倒的自然美を、川と熱帯雨林を満たすむせ返るほどのいのちを、大事に世話するアマゾンです」(7)、と序文でうたっているように、熱帯雨林の神秘の奥行きの深さに魅せられるとき、これを造られた神に心を開く。人間の保護と環境の保護が繋がっていることをここでも強調する。アマゾンの先住民の知恵は、被造界に対 する保護と敬意を促し、その限界を明確に意識して、乱用を禁じているのである。実に彼らこそアマゾンのエコロジーの真の推進者である(42)。
この勧告に頻繁に引用されるアマゾンの詩人たちにとって、川や無数の細流は生ける血管である。アマゾンの命の神秘をうたいながら、この血管の破裂、汚染の姿に涙し、彼らも預言者として叫んでいる。私たちは先住民から学ぶことで、アマゾンを「観想」できるようになり、それによって単なる分析でなく、自分たちを圧倒するその貴い神秘を認識するようになり、…アマゾンを母として愛するようになる(55)。アマゾンとの関わりは、祈りとなり、内なる回心となる(56)。
第四章:教会の夢
キリスト教共同体が、アマゾンに献身し、そこに受肉して「アマゾンの顔をもつ教会」の育成を望む夢である。アマゾンに於けるインカルチュレーションがこの章の中心テーマになっている。教会はアマゾンの深刻な社会問題に関わるが、同時に、それ以上の使命、福音宣教という使命に生きる。
「アマゾンの顔をもつ教会」が育つには、救いの最も基本的な告知、「ケリュグマ」がアマゾン全域に響き渡らなければならない(64)。福音がその文化に受肉するために、「その地の先祖伝来の知恵に耳を傾け、…先住民共同体の生活様式に内在する価値観を認める」必要がある(70)。「アマゾンの先住民は真に質の高い生活を、『良い生き方』(Bem Viver)と表現しています。それは個人の、家族の、共同体の、宇宙の和を意味しており、…質素で素朴な暮らしに喜びと充足を得る能力として、そしてさらには、次世代のために資源を守る自然保護の責任感として表れています。…彼らは、わずかなもので幸せになり、多くをため込まずに神からのささやかな贈り物を喜び、無駄に破壊せず、生態系を守っています」(71)。アマゾンのインカルチュレーションは、社会的な人権擁護を特徴とする。そしてそれは、よその地のコピーではなく、アマゾンの顔をした聖性と結ばれる必要がある(77)。
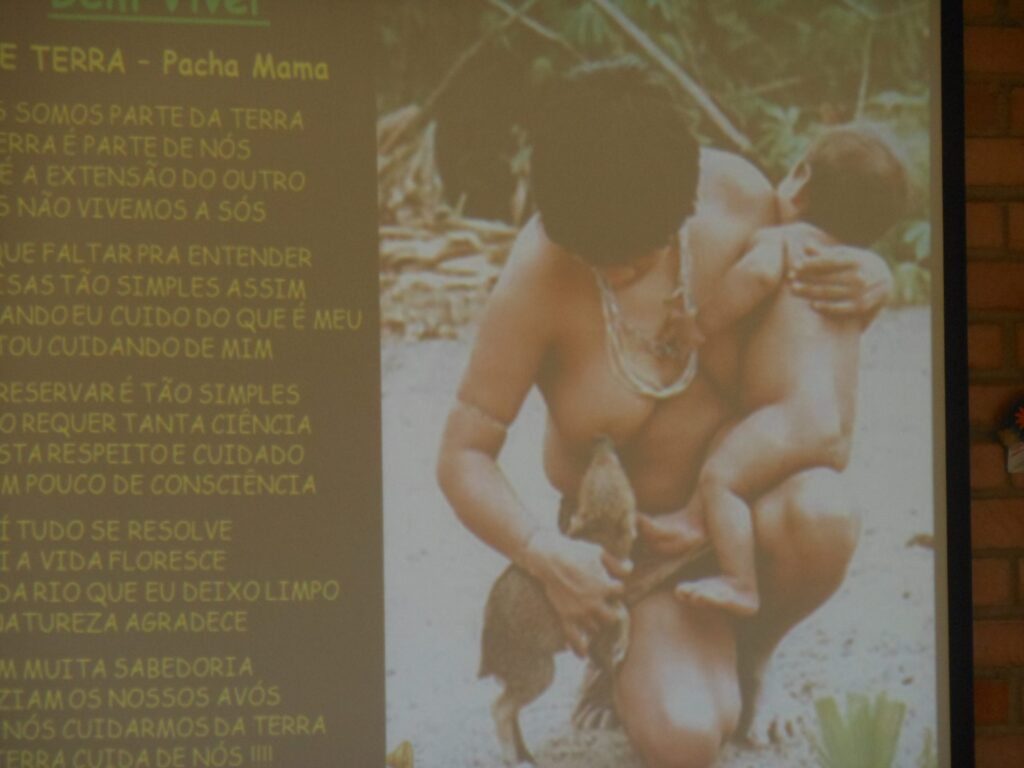
アマゾンの教会は、感謝の祭儀を執行する司祭の極度の不足を憂慮しているが、この勧告でも既婚男性や女性の叙階は肯定されていない。勧告では、信仰共同体の活性化のために、信徒たちの献身を推奨し、共同体に新たないのちを吹き込む使命があるとする。勧告は多くの奉献生活者たちの宣教活動や、先住民共同体での無数の女性たちの奉仕の偉大さを称賛するが、女性の聖職者化は「実際視野を狭めてしまい、…女性がすでにもたらしてくれた優れた価値を貶め、欠かすことのできない女性の貢献をひそかに削ぐことになる」のを懸念している(100)。勧告の結びは、アマゾンの母マリアへの賛歌と祈りに捧げられている。
この使徒的勧告に感謝し、一言加えて終わりたい。一般にアマゾンの危機を語るとき、先住民の姿は、すべて受け身の「かわいそうな被害者」の印象が強い。だが、アマゾンを守るために闘う現実の主役は彼ら自身なのである。だからこそ教会が動き、国際団体の活動も可能となるのだ。苦難を背負っているが、そこには若い力が溢れている。幾つもの民族が互いに連帯を強め、政治社会への積極的参加を実現している。
アマゾン宣教の必須はとにかく彼らの生活に近づき、そこに入り、聞き、友となり、隠れている素晴らしい生活様式を発見することである。外にいる限り、先住民は時代遅れの未開人に過ぎないが、彼らの中に招かれ、「良き生活」(Bem Viver)推進の歩みを共有するにつれて、憐憫が感嘆に変化する。勿論、そこにも無数の弱点がある。それでも彼らの、自然との融和と共存、小さな恵みから受ける幸福の思いなどに触れて、宣教師は、むしろ自分が福音を受けていると気づくようになる。教皇フランシスコはこのことを知っている。そこで彼らと共に見る「夢」はアマゾンを勇気づける最高の贈り物であり、神の預言者としての「夢」である。彼らも同じ夢を見ていて、その夢を見るあいだ、闘いは続く。

現実を直視するために ―カトリック教会と性差別問題―
栗田 隆子
文筆家
先日、プロテスタント系のクリスチャンのある知人とのやりとりで、何気ない質問をもらった。
「女性神父って世界標準で存在していないんですか?」
なるほど。例えばヨーロッパ大陸には存在するが日本にはいない、といった風に思われたのだろう。
「女性神父は世界に0人なんですよ。」
と私は答えた。先方はカトリックのことに無知で…と恐縮していたが、真に恐縮すべきはこちらだとつくづく思った。
そう、聖公会も女性司祭が存在している中で、「神父」という言葉通りカトリックに司祭職女性は存在しないのだ。
しかし私自身は今まで女性司祭がいないことにそれほど神経を尖らせてなかった。なぜなら私がいわゆる「小教区」のコミュニティで育ってきたというより、「修道院」の修道女(シスター)たちに影響を受けてきたし、修道院の存在がなければ洗礼を受けなかったと思われる信徒人生だったからである。いまだに神父の知り合いはあまりおらず、信徒の友人すらほぼほぼ女性である。
むしろ女性が教会を根っこからずっと支えてきているのに、司祭・司教といった「男性」だけが目立つことこそがまず問題であると感じていた。つまり「女性リーダー」がいないことも確かに問題だが、それ以上に問題なのは――いわゆるエッセンシャルワーカー・ケアワーカーの社会的評価が全くなされていない話と地続きだと思うのだが――、シスターや女性信徒が本当は教会内の細々したことを仕切ったり、キリスト教学や聖書学、または社会運動、あるいは霊的な歩みの蓄積を積み重ねながらも、神父・司教を前にすると一歩引いている状況に対して、とても不思議で理不尽な思いを漠然と抱いていたのである。
しかし私が本気で教会のジェンダーの問題に対峙しなければならないと思ったのは、教会内で起きた性虐待・性暴力の問題があったからである。性暴力や性虐待が起きたのみならず、その事実を組織ぐるみで隠蔽し、性虐待や性暴力を起こした司祭や司教等を、聖職者として「延命」させていたのだから、もはや組織的確信犯である。
私はその昔、ゆるしの秘跡で自分がいわゆる「付き合っている」相手との関係について語り、私の罪があれば認め赦しを乞いたいという話をしようとしたことがある。だが、付き合っていた相手について「ほとんど私のアパートにいて、性的な関係も・・・」と告解の相手である神父に言いかけたところ、「そんなことは神が許さない。早く別々に離れなさい」と即座に言われたのである。そしてゆるしも受けられなかった。そんないわゆる「お堅い」はずの組織のリーダーたちによる性虐待と性暴力。最初この複数の事件を知ったときに、私は上述のやりとりを思い出し、正直、冷笑を禁じえなかった(ちなみにこの相手との付き合いはもう四半世紀近い昔で、とうに別れ改めて違う神父からのゆるしの秘跡にあずかった)。
しかしのちにこのカトリック教会における性虐待・性暴力については聖職者の責任を追及するのみならず、まずもって私もまたきちんと反省をしなければならないとも感じた。というのも、この性虐待や性暴力の問題を2005年にイグナチオ教会でアメリカの事例を紹介されたのにもかかわらず、私自身何も動いてこなかったからである。
その理由は何の言い訳にもならないが、私自身が「神父」との付き合いがほとんどなく、どうしてそんなことになるのかがイメージできなかったというのもあったかもしれない。
そのような私がなぜこの教会の性暴力・性虐待を直視、そして対峙しようと考えたのかと言えば、皮肉にも「左翼」「労働運動」「フェミニズム」にも性差別やハラスメントなど社会構造の問題が存在していることを経験したからである。私自身はカトリック信徒でありながら(?)、労働運動やさらにフェミニズムの世界にもしっかりコミットしてきた。いわばキリスト教からは、身体や精神あるいは社会的な「脆弱さ」に対して祈りや聖書を通して向き合う意味を、社会運動やフェミニズムからは、社会的な脆弱さを抱える立場とみなされるものがいわゆる「物申し、行動する」力の意味を、それぞれ教えてもらい、どちらも重要で欠くことのできぬものだと考えていた。でも悪く言えば、それはいわばカトリック、そして社会運動やフェミニズムの「いいとこどり」だけをしようとしていたのかもしれない。
しかし、教会も社会運動も社会構造が生み出す「悪」にずぶずぶで、場合によってはこれらの組織や団体が率先してその悪を「実践」している現実が目の前にあった。その現実を目の当たりにし、もはや「いいとこどり」も「逃げ場」もないし、またそれらを「なかったこと」にもできなかった。
それならば、「カトリック教会」も「社会運動」そして「フェミニズム」に対してもどっしり構えてこれらの社会構造の悪にずぶずぶに浸っている現実そのものに自分ができうる限り対峙しようと決めたのである。
そしてこれらの組織、すなわちカトリック教会も社会運動もフェミニズムもある共通項がある。それは「きれいな言葉やかっこいい言葉をそれぞれ持っている」ということだ。カトリック教会ならば次々と発せられる愛や希望や信仰といった言葉が、社会運動ならば連帯や社会正義、フェミニズムならばエンパワーといった言葉である。しかしそれが本当に実現されているのか?あるいはそれらの言葉がキリスト教用語で言えば「受肉」されているのか?と問いたくなる現実がある。しかも怖いことにそれらのきれいな言葉こそがまた現実の直視を妨げがちなのである。

四旬節の第二金曜日が「性虐待被害者のための祈りと償いの日」と定められたが、この日こそ大斎・小斎、灰を撒き散らし、服をバリバリ切り裂いて被害者の訴えを聞いて、神と被害者に謝らねばならないと思う。しかし日本のカトリック教会で起きている性虐待・性暴力に対して、今のところ日本の教会で真っ当な謝罪がなされているとは残念ながらいえないだろう。謝罪と償いが被害者になされているならば、少なくとも教区に対する訴訟は起きていないだろうし、被害者の会もできてないだろう…と思うが読者の皆様はいかが考えられるだろうか。
おそらくこの問題は聖職者が中心の問題であるが、聖職者だけの問題ではない。それこそ信徒の一人一人が性虐待・性暴力被害者の言葉に耳を傾け、なすべきことをしてきたとは言えまい。私自身も今まで何もしてこなかったのだから、少なくともそれらの信徒を責める資格は私にはない。これはいわば私の恥と罪を語る論考でもある。
性虐待や性暴力は、子どもの頃であれば被害を受けたという認識すら困難な場合がありうる。また成人時に被害にあったとしてもPTSDなどの影響でその出来事を想起することさえ困難なこともある。それゆえ訴訟に数十年を要するケースもある。それでもなお声を上げるしかなかった現実の重みを想像できるだろうか。この現実をカトリック教会は直視すべきである。
ちなみに1998年に米国三菱のセクシュアル・ハラスメント訴訟はその補償金が3400万ドルで和解が成立した。この訴訟が世界的に企業内におけるセクハラ対策の変化の一つを促したと言われているが、日本の教会が裁判で多額の補償金を支払う羽目になれば少しは変わるのだろうか。少なくともそうなれば聖職者も私を含めた信徒も文字通り痛い目に遭うのは間違いないのだろうから。
追記
この原稿の提出後、2021年4月12日付の『クリスチャントゥデイ』のサイトに、「イエズス会神父がパワハラか、女性信者が適応障害に 日本管区が調査委設置」という見出しの記事が掲載された。「カトリック広島教区の40代の女性信者が、イエズス会所属の外国人神父からパワーハラスメントを受けたと訴え、イエズス会日本管区が調査委員会に当たる『ハラスメント防止対策委員会』を設置し、調査を行っている」といった内容である。
私はこの件の当事者を直接知っているわけでもなく、事の真偽をジャッジできる立場にはいない。だが、ハラスメントを指摘されたときに、頭ごなしに否定しないことは重要だ。そして介入が必要であれば第三者をどのような基準で選び、どのような介入が望ましいかを当事者・周囲の人間ともども模索する必要がある。そもそも私がこの出来事を「なかった」かのようにスルーするのはこの原稿の内容と著しく矛盾する行為である。ハラスメントの訴えがあったときに、被害を訴えた人に誠実に対応すること、解決とは何かを考えること、それは事件の直接の関係者ではない人間も日々考えるべきことではないだろうか。ハラスメントは他人事ではない。神父含む聖職者、信徒それぞれがいつでもハラスメントの加害者・被害者になりうるのだ。「恐れ」や面倒を避けたいがためにハラスメントの問題から目を背けるのはやめよう。教会外の「困っている人」を助けるのもいいが、足元の訴えにまずは耳を傾けるべきである。
イエズス会の教育ミッション
李 聖一 SJ
上智学院イエズス会中等教育担当理事
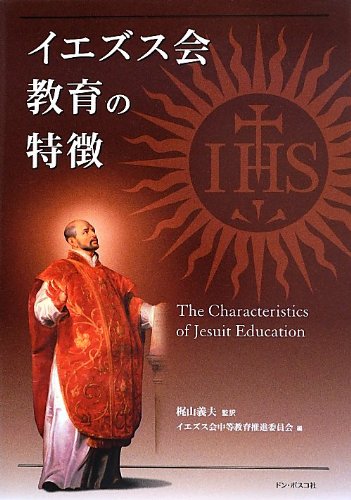
Covid-19の影響でさまざまな制約を余儀なくされた2020年は、イエズス会学校を語る上で忘れてはならない文書が発表されて40周年となる記念の年であった。アルペ神父の「イエズス会の中等教育―現状と展望―」(1980年)である。それほど注目はされなかったが、ソーサ総長はこれを記念してイエズス会学校関係者にメッセージを送ったし、イエズス会教育事務局も、この文書の価値を再確認するメッセージを送った。確かにこの文書は、今日のイエズス会学校のあり方を検討する上で、預言的な意味を持つものであったと、私は思っている。

この年にはまた、今まで、あまり深く深く考えることなく使っていた「イエズス会学校」“Jesuit School”という言葉を再考させるソーサ総長の上級長上宛書簡、“Jesuit & Companion Schools―Companions in Mission”も発表された(2020年9月17日)。『イエズス会使徒職全体の方向づけ』(Universal Apostolic Preferences of the Society of Jesus:UAPs)の発表(2019年2月19日)を受けて、イエズス会が携わる教育使徒職の方向づけも考えなければならないという意図があると思われる。それは、『イエズス会学校:21世紀に生き続ける伝統』という文書が発表(2019年11月5日)されたことを見ても明らかである。
このように矢継ぎ早に発表される文書を受けて、イエズス会の教育ミッションは今後どのように進められていくのか、イエズス会学校の原則を手掛かりに、その方向性を探ってみたい。
その原則とは「普遍性」と「無償性」である。イエズス会は設立当初から学校教育を重要なミッションとして位置づけてきたが、聖イグナチオはイエズス会の学校は常に無償であることを理想とした。ゆえに、彼自身が大原則とした清貧の規定を覆してまで、学校が一定の基金を持つことを許可した。また、アルペ神父は「中等教育の展望」の中で、次のように述べている。
「私たちは、差別なしに、すべての階層に属する人を教育する責任があります。教育使徒職は、(イエズス会の他のすべての事業同様)普遍性という消し去ることのできないイグナチオ的刻印を受けているのです。」(7)
「イエズス会の学校は、必然的に会の使徒職の手段であり、また、それゆえに原則として、会の役務の根本的無償性と清貧に基礎をおくものですから、生徒がその学校で学ぶことができるかどうかということは、彼らの支払い能力によって左右されてはなりません。この原則が理想なのです。」(8)
この原則は、すべての社会層の人々がイエズス会の学校で学ぶことができるようにということであるが、現実には、困難である。学校運営に必要な経費、人件費、教育施設費などは、学納金や助成金に依存せざるを得ないからである。
しかし、この原則と理想を追求する試みがないわけではない。たとえば、“Fe y Alegria”である。これは、1955年にベネズエラで始まった教育施設で、最貧層の子どもたちに教育の機会を与えることを目的として始まった。南米を中心に広まり、現在19か国で展開されている。Fe y Alegriaは「信仰と喜び」という意味である。
これと同様の例が“Nativity School”である。1960年にアメリカで始まった幼稚園から小学校までの初等教育を行う学校で、貧しい子どもたちに教育の機会を提供する。Nativityは「キリスト生誕」という意味である。
さらに、1996年にシカゴで始まった“Cristo Rey School”がある。メキシコ移民の子どもたちのために設立された学校で、授業料を賄うために生徒は週に1度仕事に出かけて給料を得、それを授業料に充てるというプログラムを持つ。現在は全米各地で、メキシコ移民のみならず、さまざまな貧しい家庭の子どもたちに教育の機会を与えている。Cristo Reyは「王であるキリスト」の意味であるが、メキシコ人は「万歳」を“Cristo Rey”ということに由来する。
私自身、2006年にシカゴのピールセンとニューヨークのイースト・ハーレムにある“Cristo Rey”高校を訪問したことがある。シカゴは“Cristo Rey”高校最初の学校で、メキシコ移民の子どもたち、イースト・ハーレムはヒスパニックや黒人家庭の子どもたちが学んでいた。生き生きとした顔で、喜びをもって学ぶ姿が印象的であった。この訪問を終えて、日本において何かできないかと何度も自問してみたが、答えは「日本では無理だな」であった。
しかし、私たちの教育ミッションのあり方を再検討するならば、視野に入れておかなければならないことはある。教育機会が十分に与えられていない「外国にルーツを持つ子どもたち」である。日本政府はなぜか「移民」という表現を好まない。「外国にルーツを持つ」とは、素直に言えば「移民」であるが、「外国人労働者」とか「技能実習生」として、滞在期限を設けて受け入れるゆえに、「移民」ではないのである。
定義は何であれ、日本社会の中で、「海外にルーツを持つ子どもたち」に対して、教育機会が十分に与えられていないこと示す調査は政府も行っている。ゆえに、その問題を解消するために夜間中学を増やしたり、日本語支援を行う施策も行われたりしている。また、NPOや個人的なレベルでも、日本語支援を熱心に行うグループもある。公立学校が一定の枠を設けて、子どもたちを受け入れる取り組みもある。それでもなお十分な解決とは言えない。学校にいろいろな意味でついていけないケースも報告されている。ドロップアウトしてしまい、問題行動を起こし、少年院でようやくまともに日本語を学んだという例もある。
彼らのために何が必要なのか。「やはり学校だな」と思う。教育が持つ力は大きい。学ぶ個人だけではない。家族を変え、学校のある地域に影響を与える。シカゴの“Cristo Rey”高校の例は、まさにそうであった。
彼らのために何ができるか。日本語支援だけではなく、日本において学ぶべきことが統一的にまとめられた教科カリキュラムに基づく教育と進路指導、彼らのためのアイデンティティ教育、保護者をも取り込んだ家庭教育、そしてカトリック学校としての宗教教育。そうした教育活動は、学校なしにできることではない。しかも、低所得の家庭の子どもたちのためにこそ、必要である。
このような学校は、果たして可能なのか。日本に住むすべての子どもたちに例外なく、教育機会を提供することが国としてなすべきことであれば、できないはずはないと思うのだが、実際に計画してみると、いくつもの壁がある。土地、場所、資金、人などなど。そして、ひとつ気がかりなのは、「永続性」である。学校をつくっても、数十年で役割を終えるようではあまり意味もない。これは、日本社会がこれからどうなっていくかにもかかっている。おそらく、外国人労働者の必要性はますます高くなっていくのであろう。そして、定住することが普通になれば、私たちが考える学校の必要性も高くなる。その意味では、そうした学校を始めることに意味があると思うのである。
そしてそれは、イエズス会の教育ミッションとして相応しい。「普遍性」と「無償性」に基づく学校だからである。加えて、イエズス会のミッションには次の原則もある。「必要性」「緊急性」「誰も行っていない」である。
※ 本稿で触れた文書の中で、「イエズス会の中等教育―現状と展望―」は、『イエズス会教育の特徴』(梶山義夫監訳、ドン・ボスコ社、2013年)、他の文書はすべて、『イエズス会の今日的ミッションと教育』(李聖一監修・抄訳、上智大学出版、2020年)を、それぞれ参照していただきたい。

